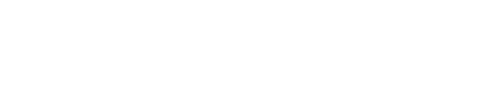健考彩都コラム
- TOP
- その不調、秋バテかも。夏バテとの違いからわかる正しい対策と予防法を完全ガイド

その不調、秋バテかも。夏バテとの違いからわかる正しい対策と予防法を完全ガイド
2025年10月10日
夏の疲れが抜けないまま、なんだか体がだるい、食欲がない…。
そんな不調に悩んでいませんか?
その症状、実は夏の疲れと秋の寒暖差による自律神経の乱れが原因の「秋バテ」かもしれません。
この記事では、夏バテとの根本的な違いを解説し、食事や入浴法など、今日からすぐに試せる具体的な解消法を7つご紹介します。
つらい不調の原因と正しい対策を知って、気持ちのよい秋を過ごしましょう。
- 1. 秋バテとは?夏バテとの違いをわかりやすく解説
- 秋バテの正体は「自律神経の乱れ」
- 夏バテとはここが違う!原因と症状を徹底比較
- あなたはどっち?秋バテセルフチェックリスト
- 2. すぐに試せる秋バテ解消法7選
- 体を内側から温める食事を摂る
- 質の高い睡眠で体を休める
- 軽い運動で血行を促進する
- ゆっくり入浴してリラックスする
- 服装を工夫して寒暖差に対応する
- ツボ押しで自律神経を整える
- 漢方薬を試してみる
- 3. 秋バテの主な症状と原因
- 秋バテによくある身体の不調
- 秋バテを引き起こす生活習慣
- 4. 今後のために知っておきたい秋バテの予防法
- 夏場の冷房対策と食生活
- 秋の生活リズムの作り方
- 5. 症状が改善しないときに相談すべき診療科
- まずはかかりつけ医や内科・総合診療科へ
- 症状別に見るおすすめの診療科
- 受診の際に医師に伝えると良いこと
- 6. まとめ
1. 秋バテとは?夏バテとの違いをわかりやすく解説
夏の厳しい暑さがようやく和らいだのに、「なんだか体がだるい」「朝すっきり起きられない」と感じること、ありませんか?
食欲がなかったり、気分が落ち込んだり…。
夏の疲れが今頃になって出てきたのかな、と感じるその不調、実は「秋バテ」かもしれません。
夏バテはよく知られていますが、秋バテは意外と見過ごされがちです。
しかし、原因や対処法が夏バテとは少し異なります。
まずは秋バテの正体をきちんと理解して、つらい不調から抜け出す第一歩を踏み出しましょう。
秋バテの正体は「自律神経の乱れ」
秋バテの最も大きな原因は、夏の間に蓄積した疲れと、秋特有の激しい寒暖差による「自律神経の乱れ」です。
私たちの体は、自律神経が体温調節や内臓の働きなどをコントロールすることで、常に一定の状態を保っています。
自律神経には、体を活動的にする「交感神経」と、リラックスさせる「副交感神経」があり、この2つがシーソーのようにバランスを取り合っています。
しかし、秋になるとこのバランスが崩れやすくなるのです。
その主な要因を詳しく見ていきましょう。
夏の疲れの蓄積と激しい寒暖差
夏の間、私たちは気づかないうちに体を酷使しています。
冷房の効いた室内と暑い屋外の行き来、冷たい飲み物や食べ物の摂りすぎ、寝苦しい夜による睡眠不足など、様々な要因で体は疲れを溜め込んでいます。
そのダメージが残ったまま秋を迎えると、体は季節の変化に対応しきれなくなります。
さらに、秋は日中の気温は高くても朝晩はぐっと冷え込むなど、一日の中での寒暖差が大きくなります。
この急激な気温の変化に体温を対応させようと、自律神経が過剰に働き続けて疲弊してしまうのです。
その結果、交感神経と副交感神経の切り替えがうまくいかなくなり、様々な不調となって現れます。
日照時間の変化による影響
秋になると、夏に比べて日照時間が短くなります。
太陽の光を浴びる時間が減ると、精神を安定させる働きのある脳内物質「セロトニン」の分泌が減少しやすくなります。
セロトニンは「幸せホルモン」とも呼ばれ、不足すると気分の落ち込みや意欲の低下、不眠などを引き起こすことがあります。
なんとなく物悲しい気分になったり、やる気が出なかったりするのは、このセロトニンの減少も関係しているかもしれません。
夏バテとはここが違う!原因と症状を徹底比較
「だるい」「食欲がない」といった症状は夏バテと似ていますが、原因をたどると大きな違いがあります。
ここで、秋バテと夏バテの違いを表で整理してみましょう。
| 比較項目 | 秋バテ | 夏バテ |
|---|---|---|
| 主な時期 | 9月~10月頃の季節の変わり目 | 7月~8月頃の真夏 |
| 主な原因 | ・夏の疲れの蓄積 ・朝晩の激しい寒暖差 ・自律神経の乱れ |
・高温多湿による体力消耗 ・発汗による水分やミネラル不足 ・食欲不振による栄養不足 |
| 身体的な症状 | だるさ、疲労感、頭痛、肩こり、めまい、立ちくらみ、胃腸の不調(食欲不振または過食)、むくみ、寝付きが悪い・眠りが浅い | 強いだるさ、極度の疲労感、食欲不振、脱水症状、立ちくらみ、下痢や便秘 |
| 精神的な症状 | 気分の落ち込み、やる気が出ない、集中力の低下、不安感 | イライラ、思考力の低下(主に体力消耗によるもの) |
このように、夏バテが「暑さ」そのものによる体力の消耗が主な原因であるのに対し、秋バテは「季節の変化」に体がついていけず、自律神経がバランスを崩すことが主な原因です。
そのため、秋バテはだるさだけでなく、頭痛や肩こり、気分の落ち込みといった、より多彩な症状が現れやすいのが特徴です。
あなたはどっち?秋バテセルフチェックリスト
ご自身の体調が秋バテによるものか、簡単なチェックリストで確認してみましょう。
最近の自分に当てはまる項目がいくつあるか、数えてみてくださいね。
- 朝、すっきりと起きられない日が増えた
- 日中もなんとなく体がだるく、重く感じる
- 食欲がなかったり、逆にお腹が空いていないのに食べてしまったりする
- 頭痛や肩こりが以前より気になるようになった
- 立ち上がったときに、めまいや立ちくらみがすることがある
- 夜、なかなか寝付けなかったり、途中で目が覚めたりする
- 理由もなく気分が落ち込んだり、イライラしたりする
- 集中力が続かず、仕事や家事がはかどらない
- 夏の終わり頃から、胃もたれや便秘・下痢など胃腸の調子が悪い
- 顔色が悪く、肌荒れや乾燥が気になる
いかがでしたか?
もし3つ以上当てはまる項目があれば、それは秋バテのサインかもしれません。
放っておくと長引くこともあるため、早めに体をいたわる対策を始めることが大切です。
2. すぐに試せる秋バテ解消法7選
夏の疲れがどっと出てくる秋。
「なんだか体がだるいな…」と感じたら、それは秋バテのサインかもしれません。
でも、ご安心ください。
日常生活のちょっとした工夫で、その不調は和らげることができます。
ここでは、今日からすぐに始められる7つの具体的な解消法をご紹介します。
自分に合ったものから、ぜひ試してみてくださいね。
体を内側から温める食事を摂る
夏の間に冷たい飲み物や食べ物を摂りすぎて、私たちの胃腸は意外と冷え切っていることがあります。
胃腸の働きが鈍ると、栄養の吸収が悪くなり、全身のエネルギー不足につながってしまいます。
秋バテ解消の第一歩は、食事で体を内側からじっくりと温め、弱った消化機能を回復させることです。
秋の旬の食材を取り入れた食事
秋は実りの季節。
この時期に旬を迎える食材には、夏の間に消耗した体力を回復させ、体を温めてくれる栄養素が豊富に含まれています。
積極的に食卓に取り入れて、季節の恵みで体を元気にしましょう。
| 食材カテゴリ | 具体的な食材例 | 期待できる働き |
|---|---|---|
| 根菜類 | さつまいも、里芋、ごぼう、れんこん、にんじん | 体を温める作用や、腸内環境を整える食物繊維が豊富です。 |
| きのこ類 | しめじ、まいたけ、エリンギ、しいたけ | 免疫機能の維持を助けるビタミンDや、代謝を促すビタミンB群がたっぷり。 |
| 青魚 | さんま、さば、いわし | 血行を促進するEPAやDHAなどの良質な脂質を含んでいます。 |
| 果物 | かぼちゃ、栗、柿、梨 | 粘膜を保護するビタミンA(β-カロテン)や疲労回復を助けるビタミンCが豊富です。 |
生姜やネギなど薬味の活用
いつもの料理に少し加えるだけで、体を温める効果をぐっと高めてくれるのが薬味の力です。
特に、生姜やネギ、ニンニクなどには血行を促進し、体をポカポカさせてくれる成分が含まれています。
お味噌汁やスープにすりおろした生姜を加えたり、炒め物に刻んだネギを散らしたりと、手軽に活用できるのが嬉しいポイントです。
質の高い睡眠で体を休める
夏の寝苦しさから解放されたはずなのに、なぜかぐっすり眠れない…そんな経験はありませんか?
季節の変わり目は、自律神経が乱れやすく、それが睡眠の質を低下させる原因になることがあります。
心と体をしっかりリセットするために、質の高い睡眠を確保することが非常に重要です。
寝る前のスマホ操作を控える
ベッドに入ってからも、ついスマートフォンを眺めてしまう習慣はありませんか?
スマホやパソコンの画面から発せられるブルーライトは、睡眠を促すホルモン「メラトニン」の分泌を抑制してしまいます。
その結果、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりする原因に。
理想は就寝の1〜2時間前には画面を見るのをやめ、代わりに読書やストレッチなどリラックスできる時間を持つこと'mark>です。
自分に合った寝具を見つける
日中は暖かくても、朝晩は意外と冷え込むのが秋の特徴です。
夏と同じ寝具のままでは、寝ている間に体が冷えてしまい、睡眠の質を下げてしまう可能性があります。
肌触りが良く、吸湿性・保温性に優れた綿やシルク素材のパジャマを選んだり、薄手の毛布や掛け布団を一枚プラスしたりして、快適な睡眠環境を整えましょう。
軽い運動で血行を促進する
体がだるいと、ついゴロゴロして過ごしたくなりますよね。
しかし、動かないでいると筋肉がこわばり、さらに血行が悪くなって不調が長引くという悪循環に陥ることも。
激しい運動は必要ありません。
心地よいと感じる程度の軽い運動を習慣にして、全身の血の巡りを良くしましょう。
おすすめは、ウォーキングや軽いジョギング、ヨガ、ストレッチなどです。
特に朝、太陽の光を浴びながら少し散歩するだけでも、体内時計がリセットされ、自律神経が整いやすくなります。
「頑張らなくては」と気負わず、まずは15分程度の散歩から始めてみてはいかがでしょうか。
ゆっくり入浴してリラックスする
忙しいとシャワーだけで済ませてしまいがちですが、秋バテ気味のときこそ、ぜひ湯船に浸かる時間を作ってみてください。
38℃〜40℃くらいのぬるめのお湯に15分ほど浸かることで、副交感神経が優位になり、心身ともにリラックスモードに切り替わります。
血行が促進されて筋肉の緊張がほぐれるだけでなく、質の良い睡眠にもつながります。
ラベンダーやカモミールなど、リラックス効果のある香りの入浴剤やアロマオイルを使うのもおすすめです。
心地よい香りに包まれながら深呼吸すれば、一日の疲れがすーっと溶けていくのを感じられるはずです。
服装を工夫して寒暖差に対応する
「朝は肌寒かったのに、日中は汗ばむ陽気」というように、一日のうちで気温が大きく変動するのも秋の特徴です。
この寒暖差は、私たちが思う以上に体にストレスを与え、自律神経のバランスを崩す大きな原因となります。
服装を上手に工夫して、体温調節をこまめに行い、体への負担を減らすことが大切です。
ポイントは「重ね着」です。
カーディガンやパーカー、ストールなど、着たり脱いだりしやすいアイテムを一枚プラスしておきましょう。
また、「首」「手首」「足首」の三つの首は、太い血管が皮膚の近くを通っているため、冷えを感じやすい部分です。
この三首を冷やさないように意識するだけでも、体感温度は大きく変わります。
ツボ押しで自律神経を整える
なんだか調子が悪いけれど、マッサージに行く時間はない…。
そんなときには、仕事の合間やテレビを見ながらでも手軽にできるツボ押しがおすすめです。
自律神経のバランスを整えたり、胃腸の働きを助けたりするツボを、気持ちいいと感じる強さでゆっくり押してみましょう。
| ツボの名前 | 場所 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 合谷(ごうこく) | 手の甲側で、親指と人差し指の骨が交わる手前のくぼみ。 | 万能のツボと呼ばれ、自律神経の乱れや全身の疲労感、頭痛、肩こりなどに。 |
| 内関(ないかん) | 手のひら側の手首のしわから、指3本分ひじ側にある2本のすじの間。 | 胃の不快感や吐き気、乗り物酔いを和らげ、精神を安定させる働きが期待できます。 |
| 足三里(あしさんり) | ひざのお皿のすぐ下、外側のくぼみから指4本分下のあたり。 | 胃腸の働きを整え、体力を補う「元気のツボ」として知られています。 |
息を吐きながら5秒ほどゆっくり押し、息を吸いながら力を抜く、というのを数回繰り返してみてください。
漢方薬を試してみる
さまざまなセルフケアを試しても、なかなか不調が改善しない場合は、漢方薬の力を借りるという選択肢もあります。
漢方医学では、不調の原因を体全体のバランスの乱れと捉え、その人の体質に合った漢方薬を用いて根本からの改善を目指します。
例えば、食欲不振で疲れやすい方には胃腸の働きを助ける「補中益気湯(ほちゅうえっきとう)」、冷えやイライラを感じやすい方には気の巡りを整える「加味逍遙散(かみしょうようさん)」などが用いられることがあります。
ただし、漢方薬は体質との相性が非常に重要です。
自己判断で選ぶのではなく、必ず医師や薬剤師、登録販売者といった専門家に相談し、自分に合ったものを選んでもらうようにしましょう。
3. 秋バテの主な症状と原因
「なんだか最近、体が重くてだるい…」「夏の疲れが今になって出てきたのかな?
」と感じること、ありませんか?
その不調、もしかしたら「秋バテ」のサインかもしれません。
効果的な対策を行うためには、まず自分の体に何が起きているのか、その原因はどこにあるのかを正しく知ることが大切です。
ここでは、秋バテの代表的な症状と、その引き金となる生活習慣について詳しく見ていきましょう。
秋バテによくある身体の不調
秋バテの症状は人によって様々ですが、いくつかの共通したサインが見られます。
身体的なものから精神的なものまで、思い当たる不調がないかチェックしてみてください。
| 症状の種類 | 具体的な症状の例 |
|---|---|
| 身体的な症状 |
|
| 精神的な症状 |
|
これらの症状は、一つひとつは些細なことのように思えるかもしれません。
しかし、複数が重なって現れる場合は、季節の変わり目で体がSOSサインを出している証拠。
特に、夏バテと違って食欲不振よりも「だるさ」や「気分の落ち込み」が強く出やすいのが秋バテの特徴とも言われています。
秋バテを引き起こす生活習慣
では、なぜ秋になるとこのような不調が現れるのでしょうか。
その原因は、夏から秋へと移り変わるこの時期特有の環境の変化と、夏の間に積み重ねてきた生活習慣に隠されています。
夏の疲れの蓄積と自律神経の乱れ
夏のあいだ、私たちは知らず知らずのうちに体に負担をかけています。
例えば、暑い屋外と冷房が効いた室内との頻繁な出入り、冷たい飲み物や食べ物の摂りすぎ、寝苦しい夜の睡眠不足などです。
こうした生活は、体温調節や内臓の働きをコントロールしている自律神経に大きな負担をかけ、そのバランスを乱してしまいます。
夏の間はなんとか乗り切れていても、その疲れが蓄積し、気温が下がり始める秋口に一気に表面化してしまうのです。
激しい寒暖差による身体へのストレス
秋は「一日の中に四季がある」と言われるほど、朝晩と日中の気温差が激しい季節です。
日中は汗ばむ陽気なのに、夜になると急に肌寒くなることも珍しくありません。
私たちの体は、この激しい寒暖差に対応しようと、自律神経をフル稼働させて体温を一定に保とうとします。
この体温調節のためのエネルギー消費が、想像以上に体を疲れさせ、だるさや疲労感の原因となってしまうのです。
日照時間の減少による気分の変化
秋になると、夏に比べて太陽が出ている時間が短くなります。
日光を浴びる時間が減ると、私たちの脳内では「セロトニン」という神経伝達物質の分泌が減少しがちになります。
セロトニンは精神を安定させ、幸福感をもたらす働きがあるため、「幸せホルモン」とも呼ばれています。
このセロトニンの分泌が減ることで、気分の落ち込みや意欲の低下、睡眠の質の悪化などを感じやすくなるのです。
なんとなく物悲しい気分になるのは、秋の気候だけでなく、こうした体内の変化も影響しているのかもしれません。
秋の長雨と気圧の変化
秋は台風シーズンでもあり、秋雨前線の影響でぐずついた天気が続くことも多い時期です。
雨が続くと、気圧が低くなる傾向があります。
この気圧の低下が、人によっては自律神経のバランスに影響を与え、頭痛やめまい、古傷の痛みなどを引き起こすことがあります。
特に、普段から天候によって体調が左右されやすい方は、秋の長雨が不調の引き金になるケースも少なくありません。
4. 今後のために知っておきたい秋バテの予防法
「毎年、秋になるとどうも体調がすぐれない…」と感じていませんか?
実は、秋バテはその年になってから対策するのではなく、夏からの過ごし方が大きく影響しています。
一度乱れてしまった自律神経を整えるのは時間がかかるもの。
来年こそは元気に秋を迎えるために、今からできる予防法を知っておきましょう。
夏場の冷房対策と食生活
秋の不調の種は、夏の間にまかれています。
厳しい暑さを乗り切るための冷房や冷たい食べ物が、知らず知らずのうちに体に負担をかけ、自律神経のバランスを崩す原因になっているかもしれません。
夏の過ごし方を見直すことが、秋バテ予防の第一歩です。
夏の「隠れ冷え」を防ぐ服装のポイント
屋外は猛暑でも、オフィスや電車の中は冷房が効きすぎて寒い、ということはよくありますよね。
この急激な温度差が、体温調節機能を担う自律神経を疲れさせてしまいます。
カーディガンやストールなど、さっと羽織れるものを常に一枚持ち歩く習慣をつけましょう。
また、足首や首元など、太い血管が通る場所を冷やさないようにするのも効果的です。
レッグウォーマーやスカーフなどを活用して、体を「隠れ冷え」から守ってあげてください。
胃腸を疲れさせない夏の食事メニュー
暑いとつい、そうめんやアイスクリームなど、冷たくて喉越しの良いものばかりを選んでしまいがちです。
しかし、これが胃腸の機能を低下させ、夏全体のスタミナ不足につながります。
冷たいものばかりでなく、意識的に温かい食事を取り入れることが大切です。
例えば、夏野菜は体を冷やす作用がありますが、スープや炒め物など加熱調理することで、その作用を和らげることができます。
また、生姜やミョウガ、ネギなどの薬味には体を温めたり、血行を促進したりする働きがあるので、上手に活用しましょう。
夏の食事で意識したいポイントを、具体的なメニュー例とともにまとめました。
| 意識したいポイント | 具体的なメニュー例 |
|---|---|
| 温かい汁物をプラスする | 豚汁、かぼちゃのポタージュ、わかめと豆腐の味噌汁 |
| 香味野菜・スパイスを活用する | 冷奴に生姜とネギをたっぷり乗せる、カレー、ガパオライス |
| 夏野菜は加熱調理を心がける | 夏野菜の揚げ浸し、ラタトゥイユ、ゴーヤチャンプルー |
| タンパク質をしっかり摂る | 豚肉の生姜焼き、鶏むね肉の棒棒鶏(バンバンジー)、焼き魚 |
秋の生活リズムの作り方
夏から秋へと季節が移り変わる時期は、日照時間が短くなり、朝晩の気温差も大きくなります。
このような環境の変化に体がスムーズに対応できるよう、生活リズムを整えることが非常に重要です。
規則正しい生活は、乱れがちな自律神経を安定させるための土台となります。
体内時計を整える朝の習慣
健やかな一日をスタートさせる鍵は、朝の過ごし方にあります。
まず、休日でもできるだけ同じ時間に起きるように心がけましょう。
目が覚めたら、カーテンを開けて太陽の光をたっぷりと浴びてください。
朝日を浴びることで、幸せホルモンと呼ばれる「セロトニン」の分泌が促され、体内時計がリセットされます。
そして、朝食をしっかり食べることも忘れずに。
朝食は、体にエネルギーを補給し、体温を上昇させて活動モードへのスイッチを入れる大切な役割を担っています。
秋の夜長を快適に過ごすリラックス法
秋は物思いにふけりやすい季節とも言われますが、心と体をしっかり休ませるためのリラックスタイムを作るのに最適な時期でもあります。
ぬるめのお湯にゆっくり浸かる、好きな香りのアロマを焚く、ヒーリング音楽を聴くなど、自分に合ったリラックス法を見つけましょう。
特に、寝る前の1時間はスマートフォンやパソコンの画面を見るのをやめ、心穏やかに過ごす時間を作るのがおすすめです。
ブルーライトは脳を覚醒させ、睡眠の質を低下させる原因になります。
読書をしたり、軽いストレッチをしたりして、自然な眠気を誘うようにしましょう。
5. 症状が改善しないときに相談すべき診療科
セルフケアをいろいろ試してみたけれど、どうも体調がすっきりしない…。
そんなときは、一人で抱え込まずに専門家である医師に相談することも大切です。
もしかしたら、その不調は単なる秋バテではなく、別の病気が隠れているサインかもしれません。
ここでは、どのような症状のときに、どの診療科を受診すればよいのかを具体的に解説します。
ご自身の症状と照らし合わせながら、適切な相談先を見つけるための参考にしてください。
まずはかかりつけ医や内科・総合診療科へ
「どの科に行けばいいのかわからない」と迷ったときは、まずはお近くの内科や総合診療科を受診するのがおすすめです。
かかりつけ医がいる場合は、まずそちらに相談しましょう。
内科や総合診療科では、体全体の不調を総合的に診察してくれます。
問診や検査を通して、症状の原因を幅広く探り、必要に応じて専門の診療科を紹介してくれるため、最初の窓口として最も適しています。
秋バテのような、はっきりしない様々な症状が重なっている場合には特に心強い存在です。
症状別に見るおすすめの診療科
特に気になる症状がはっきりしている場合は、その症状に合わせた専門の診療科を受診するのも一つの方法です。
以下の表を参考に、ご自身の状態に最も近いものを選んでみましょう。
| 主な症状 | 考えられる原因・関連する状態 | 相談先の診療科 |
|---|---|---|
| だるさ、倦怠感、微熱、食欲不振、胃腸の不調など、全身の症状が気になる | 自律神経の乱れ、内臓機能の低下、他の内科系疾患の可能性 | 内科、総合診療科 |
| 気分の落ち込み、やる気が出ない、不安感、イライラ、眠れない、集中力の低下など、精神的な不調が強い | 自律神経の乱れによる精神的な影響、うつ病や適応障害などの可能性 | 心療内科、精神科 |
| めまい、ふらつき、耳鳴りが主な症状 | 自律神経の乱れによる平衡感覚への影響、メニエール病など耳に関する疾患の可能性 | 耳鼻咽喉科、内科 |
| 月経不順、生理痛の悪化、PMS(月経前症候群)の症状がひどい、のぼせやほてりがある(女性の場合) | ホルモンバランスの乱れ、更年期障害との関連 | 婦人科 |
| 慢性的な頭痛、ひどい肩こりや首のこり、腰痛 | 血行不良、自律神経の乱れによる筋肉の緊張、緊張型頭痛、整形外科的疾患の可能性 | 内科、整形外科、脳神経内科 |
受診の際に医師に伝えると良いこと
病院を受診する際は、ご自身の症状をできるだけ正確に、そして具体的に伝えることが的確な診断への近道です。
事前に以下のポイントをメモにまとめておくと、診察がスムーズに進みます。
- いつから症状が始まったか:「先週の連休明けから」「1ヶ月くらい前から」など
- どのような症状があるか:「朝起きるのがつらい」「体が鉛のように重い」「食後に胃がもたれる」など具体的に
- 症状が出るタイミングや頻度:「一日中だるい」「夕方になると特にひどくなる」「週に2〜3回、急にめまいがする」など
- 生活習慣の変化:最近の睡眠時間、食生活、仕事やプライベートでのストレスの有無など
- ご自身で試した対策と効果:「市販の胃薬を飲んだがあまり変わらなかった」「早く寝るようにしたら少し楽になった」など
- 持病や現在服用中の薬:お薬手帳を持参すると確実です
「ただの秋バテだから」と自己判断で放置してしまうと、回復が遅れたり、隠れた病気を見逃してしまったりすることもあります。
つらい症状が続く場合は、ためらわずに医療機関を受診してくださいね。
6. まとめ
夏の終わりから続くそのだるさ、もしかしたら秋バテかもしれません。
秋バテは、夏の間に溜まった疲れと、急な気温の変化に体がついていけず、自律神経が乱れてしまうことが大きな原因です。
でも、ご安心ください。
この記事でご紹介した、体を温める食事や質の良い睡眠、軽い運動などを少しずつ生活に取り入れてみませんか?
自分の体をいたわる習慣で、過ごしやすい季節を元気に楽しみましょう。
来年のためにも、今から予防を意識することが大切です。
商品カテゴリから探す