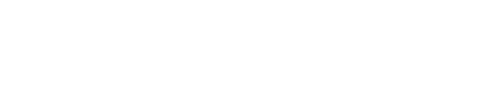健考彩都コラム
- TOP
- 夏の疲れをリセット!秋の夜長を快眠に変える睡眠習慣のコツ

夏の疲れをリセット!秋の夜長を快眠に変える睡眠習慣のコツ
2025年9月30日
過ごしやすいはずの秋なのに、「なんだか寝つきが悪い」「夏の疲れが抜けず、朝すっきり起きられない」と感じていませんか?
その不調の正体は、夏の間に蓄積した疲れと、秋特有の気温の変化や日照時間の減少が原因かもしれません。
この記事では、秋の睡眠の質が下がる3つの原因を解説し、今日から実践できる朝・昼・夜の時間帯別快眠習慣を具体的にお伝えします。
生活リズムを整え、秋の夜長を最高の休息時間に変えましょう。
1. あなたの睡眠は大丈夫?秋の睡眠習慣セルフチェック
夏の猛暑がようやく過ぎ去り、過ごしやすい季節がやってきましたね。
心地よい秋風を感じながら、「これでようやくぐっsり眠れる」と期待していたのに、「なぜか寝つきが悪い…」「朝起きても疲れが全然取れていない…」なんてことはありませんか?
もしかしたら、その不調は季節の変わり目である秋特有の「隠れ睡眠負債」が原因かもしれません。
本格的な対策を始める前に、まずはご自身の今の睡眠状態を客観的に把握してみましょう。
以下のリストで、最近のあなたに当てはまる項目がいくつあるか、ぜひチェックしてみてください。
秋の睡眠習慣チェックリスト
この1ヶ月のあなたの状態に最も近いものにチェックを入れてみてください。
| 時間帯 | チェック項目 |
|---|---|
| 朝 | 目覚ましが鳴っても、すっきりと起き上がれないことが多い。 |
| 朝 | 起きたときに、首や肩のこり、体の重さを感じる。 |
| 朝 | 午前中、頭がボーッとして仕事や家事に集中できない。 |
| 日中 | 昼食後に、耐えがたいほどの強い眠気に襲われることがある。 |
| 日中 | 以前よりもイライラしやすかったり、気分が落ち込んだりすることが増えた。 |
| 日中 | 甘いものやカフェイン飲料を無性に欲することが多くなった。 |
| 夜 | 布団に入ってから30分以上、なかなか寝付けない。 |
| 夜 | 眠りが浅く、夜中に何度も目が覚めてしまう。 |
| 夜 | 寝る前にスマートフォンやパソコンを見ている時間が多い。 |
| 夜 | 休日になると、平日より2時間以上長く寝てしまう「寝だめ」をしている。 |
さて、いくつ当てはまりましたか?
もし3つ以上当てはまる項目があったなら、それは夏の間に蓄積した疲れや季節の変化によって、あなたの睡眠の質が低下しているサインかもしれません。
睡眠は、単なる休息ではありません。
心と体の両方をメンテナンスし、翌日の活力を生み出すための大切な時間です。
でも、ご安心ください。
これらの不調は、秋という季節が体に与える影響を正しく理解し、少しだけ生活習慣を見直すことで、十分に改善することが可能です。
次の章からは、なぜ秋に睡眠の質が下がりやすいのか、その具体的な原因と誰でも簡単に始められる対策を詳しく解説していきます。
2. 秋の睡眠の質が下がる3つの原因と対策
過ごしやすい季節のはずなのに、「なんだか最近よく眠れない…」「朝起きるのがつらい」と感じていませんか?
実は、秋は気候や体の変化によって、知らず知らずのうちに睡眠の質が低下しやすい季節なのです。
ここでは、その主な原因を3つに分けて、今日からできる具体的な対策とあわせて詳しく解説します。
原因1 夏の疲れと生活リズムの乱れ
厳しい夏の暑さを乗り切った体には、自分でも気づかないうちに疲れが蓄積しています。
冷房による体の冷えや、冷たい飲み物・食べ物の摂りすぎで内臓が疲弊し、いわゆる「秋バテ」の状態になっていることも。
この夏の間に溜め込んだ「睡眠負債」が、秋の不調として現れ、深い眠りを妨げる一因になります。
また、夏休みや長期休暇などで夜更かしや朝寝坊が習慣になり、生活リズムが乱れたまま秋を迎えてしまうケースも少なくありません。
一度ずれてしまった体内時計は、意識しないとなかなか元には戻らず、寝つきの悪さや日中の眠気につながってしまうのです。
【対策】乱れた体内時計をリセットし、体をいたわる
まずは、乱れた生活リズムを整えることから始めましょう。
ポイントは、休日も平日と同じ時間に起きることです。
朝、決まった時間に太陽の光を浴びることで、体内時計がリセットされ、夜の自然な眠気へとつながります。
また、夏の疲れを回復させるために、栄養バランスの取れた食事を心がけ、特に疲労回復を助けるビタミンB群や、睡眠の質を高めるアミノ酸(トリプトファン)などを意識して摂るのがおすすめです。
原因2 気温の変化と自律神経
秋の特徴といえば、日中は暖かくても朝晩はぐっと冷え込む「寒暖差」。
この急激な気温の変化に体温を対応させようと、私たちの自律神経はフル稼働しています。
自律神経には、体を活動的にする「交感神経」と、リラックスさせる「副交感神経」があり、この2つのバランスが健康の鍵を握っています。
しかし、寒暖差が激しいと自律神経の切り替えがうまくいかなくなり、バランスが乱れがちに。
その結果、夜になっても交感神経が優位な状態が続き、心身が興奮してなかなか寝付けなかったり、眠りが浅くなったりするのです。
【対策】体を温め、副交感神経を優位にする
自律神経のバランスを整えるためには、体を「温める」ことと「リラックスする」ことが重要です。
具体的な対策を下の表にまとめました。
| 対策 | 具体的な方法とポイント |
|---|---|
| 服装の工夫 | カーディガンやパーカーなど、着脱しやすい羽織りものを活用しましょう。 日中と朝晩の気温差に合わせてこまめに調節し、体が冷えすぎるのを防ぎます。 特に首元、手首、足首の「三首」を温めると効果的です。 |
| 入浴 | 就寝の90分〜120分前に、38〜40℃のぬるめのお湯に15分ほどゆっくり浸かるのが理想です。 体の深部体温が一度上がり、その後下がっていくタイミングで自然な眠気が訪れます。 リラックス効果のある入浴剤を使うのも良いでしょう。 |
| 軽いストレッチ | 寝る前に布団の上でできる簡単なストレッチを取り入れましょう。 筋肉の緊張がほぐれ、血行が促進されることで、リラックスモードの副交感神経が優位になります。 呼吸を止めず、ゆっくりと行うのがコツです。 |
原因3 日照時間とセロトニン不足
秋になると、夏に比べて太陽が出ている時間が短くなります。
実はこの日照時間の変化が、私たちの睡眠に大きく影響していることをご存知でしたか?
太陽の光を浴びる時間が減ると、脳内で作られる「セロトニン」という神経伝達物質の分泌が減少してしまいます。
セロトニンは、精神を安定させて幸福感をもたらすことから「幸せホルモン」とも呼ばれていますが、もう一つ重要な役割があります。
それは、夜になると「睡眠ホルモン」と呼ばれる「メラトニン」に変化することです。
つまり、日中のセロトニン分泌が少ないと、夜に作られるメラトニンも不足してしまい、寝つきが悪くなったり、夜中に目が覚めやすくなったりするのです。
【対策】意識的に太陽光を浴び、セロトニンの材料を補給する
セロトニン不足を防ぐには、「太陽光」「リズム運動」「食事」の3つが鍵となります。
特に朝の過ごし方が重要です。
まず、朝起きたらすぐにカーテンを開け、15分ほど太陽の光を浴びましょう。
曇りや雨の日でも、屋外の光にはセロトニンの分泌を促す効果があります。
通勤時に一駅分歩いたり、軽いウォーキングをしたりといった「リズム運動」も、セロトニンを活性化させるのに非常に効果的です。
また、食事ではセロトニンの材料となる必須アミノ酸「トリプトファン」を積極的に摂ることをおすすめします。
トリプトファンは、バナナ、牛乳やヨーグルトなどの乳製品、豆腐や納豆などの大豆製品、ナッツ類に多く含まれています。
3. 実践編 秋の夜長を快眠に変える時間帯別の睡眠習慣
夏の疲れが残り、なんとなく寝付けない…そんな秋の夜を、心地よい眠りのためのゴールデンタイムに変えてみませんか?
ここでは、朝・昼・夜の時間帯別に、今日からすぐに始められる具体的な快眠習慣をご紹介します。
一つでも取り入れることで、きっと変化を感じられるはずです。
【朝の習慣】すっきり目覚めるためのモーニングルーティン
「夜の睡眠は朝から始まっている」と言われるほど、朝の過ごし方は重要です。
乱れがちな体内時計をリセットし、夜の自然な眠気を誘うためのスイッチを入れましょう。
カーテンを開けて太陽光を浴びる
朝、目が覚めたら、まずはカーテンを思いっきり開けて太陽の光を浴びる習慣をつけましょう。
これは、私たちの体に備わっている体内時計をリセットするための、最も簡単で効果的な方法です。
太陽光を浴びることで、睡眠ホルモンである「メラトニン」の分泌が止まり、代わりに幸せホルモンと呼ばれる「セロトニン」が活発に分泌されます。
このセロトニンは、夜になるとメラトニンの材料になるため、朝にしっかり分泌させておくことが、夜の快眠につながるのです。
曇りや雨の日でも、室内灯よりはるかに光量が多いため、窓際に立つだけでも効果が期待できます。
まずは5分から始めてみませんか?
コップ一杯の白湯で体を温める
睡眠中に汗などで失われた水分を補給し、冷えた体を内側から優しく温めるために、コップ一杯の白湯を飲むのがおすすめです。
胃腸が温まることで血行が促進され、体全体が活動モードへとスムーズに切り替わります。
熱湯ではなく、50℃〜60℃くらいの少し冷ましたお湯を、ゆっくりと時間をかけて飲むのがポイントです。
レモンスライスや生姜を少し加えると、風味も変わり、リフレッシュ効果も高まりますよ。
【日中の習慣】夜の睡眠につながる過ごし方
日中の活動量も、夜の睡眠の質を左右する大切な要素です。
体を動かし、脳を適度に疲れさせることが、夜のスムーズな入眠をサポートします。
軽い運動で心地よい疲労感を
質の良い睡眠のためには、日中に適度な運動を取り入れ、「睡眠圧」と呼ばれる眠気の素を高めておくことが効果的です。
激しい運動をする必要はありません。
心地よい疲労感を得られる程度の有酸素運動を心がけましょう。
- ウォーキング:一駅手前で降りて歩く、お昼休憩に公園を散歩するなど、日常生活の中で気軽に取り入れられます。
- ヨガやストレッチ:深い呼吸を意識しながら行うことで、心身のリラックス効果も期待できます。
- 軽いジョギング:夕方の涼しい時間帯に行うと、一時的に上がった深部体温が夜にかけて下がり、自然な眠気を誘います。
運動のタイミングは、就寝の3時間前までに終えるのが理想です。
寝る直前の運動は体を興奮させてしまうため、逆効果になる可能性があるので注意しましょう。
効果的な昼寝の時間と方法
日中にどうしても眠気を感じるときは、我慢せずに短い昼寝を取り入れるのがおすすめです。
ただし、長い昼寝は夜の睡眠を妨げる原因になってしまいます。
効果的な昼寝のポイントは「時間」と「タイミング」です。
- 時間:15分〜20分程度にとどめる。
- タイミング:15時までに行う。
- 姿勢:ソファや椅子に座ったままなど、深く眠りすぎない体勢をとる。
昼寝の直前にコーヒーや緑茶などカフェインを含む飲み物を飲む「コーヒーナップ」も効果的です。
カフェインの効果が現れるのが20分後くらいなので、ちょうど目覚める頃に頭がすっきりします。
【夜の習慣】スムーズな入眠を促すナイトルーティン
一日の終わりには、心と体をリラックスさせ、おやすみモードへと切り替えるための準備が必要です。
自分だけのリラックスできる時間を作り、質の高い睡眠へとつなげましょう。
就寝3時間前までの食事とメニューの工夫
夕食は、胃腸に負担をかけないよう、就寝の3時間前までに済ませておくのが理想です。
就寝時に胃の中に食べ物が残っていると、消化活動のために体が休まらず、眠りが浅くなる原因になります。
また、食事のメニューを少し工夫することで、睡眠の質を高める効果が期待できます。
睡眠に良いとされる栄養素を意識的に取り入れてみましょう。
| 栄養素 | 働き | 多く含まれる食材 |
|---|---|---|
| トリプトファン | メラトニンの材料となり、心を落ち着かせる | 乳製品(牛乳、チーズ)、大豆製品(豆腐、納豆)、バナナ、ナッツ類 |
| GABA(ギャバ) | 興奮を鎮め、リラックス効果をもたらす | トマト、かぼちゃ、発芽玄米、きのこ類 |
| グリシン | 体の深部体温を下げ、スムーズな入眠を促す | エビ、ホタテ、カジキマグロ、豚肉 |
例えば、豆腐とキノコのお味噌汁や、鶏むね肉とカボチャの煮物などは、これらの栄養素を手軽に摂れるおすすめのメニューです。
ぬるめのお湯での入浴法
シャワーだけで済ませてしまうのはもったいないかもしれません。
湯船にゆっくりつかることで、心身のリラックスはもちろん、睡眠の質を高める効果が期待できます。
ポイントは「お湯の温度」と「タイミング」です。
就寝の90分〜2時間前に、38℃〜40℃のぬるめのお湯に15分〜20分ほどつかるのがベスト。
入浴によって一時的に上がった体の深部体温が、お風呂から上がった後に徐々に下がっていく過程で、自然な眠気が訪れます。
ラベンダーやカモミールなど、リラックス効果のあるアロマオイルを数滴垂らすのもおすすめです。
照明を落としてリラックスできる環境作り
私たちの体は、光の量によって体内時計を調整しています。
夜に強い光、特にスマートフォンやパソコンから発せられるブルーライトを浴びると、脳が「まだ昼だ」と勘違いし、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌が抑制されてしまいます。
就寝1〜2時間前からは、部屋の照明を暖色系の間接照明に切り替え、できるだけスマートフォンやテレビから離れて過ごしましょう。
穏やかな音楽を聴いたり、カフェインの入っていないハーブティー(カモミールティーやルイボスティーなど)を飲んだり、好きな香りのアロマを焚いたりするのも良いでしょう。
紙の本を読むのも、心穏やかに入眠準備ができるのでおすすめです。
4. これはNG!秋の夜に避けたい睡眠の質を下げる行動
秋の夜長を快適な睡眠時間にするために、良かれと思ってやっている習慣が、実は眠りを妨げているかもしれません。
ここでは、ぐっすり眠るために秋の夜に避けたいNG行動を具体的に解説します。
ご自身の生活習慣と照らし合わせて、チェックしてみてくださいね。
寝る直前の食事や飲酒
「お腹が空いて眠れないから、少しだけ…」「リラックスするために一杯だけ…」そんな経験はありませんか?
しかし、寝る直前の食事や飲酒は、快眠を妨げる大きな原因になってしまいます。
食事をすると、私たちの体は食べ物を消化するために胃や腸が活発に働き始めます。
これは、体が休息モードであるべき睡眠中も、消化器系が働き続けてしまうことを意味します。
脳は休もうとしているのに体は働いている、というアンバランスな状態になり、深い眠りを得にくくなってしまうのです。
特に、脂っこいものや消化に時間のかかる食べ物は、胃もたれの原因にもなり、睡眠の質をさらに低下させます。
また、アルコールは寝つきを良くするように感じられるかもしれませんが、これは大きな落とし穴です。
アルコールが体内で分解される過程で生まれる「アセトアルデヒド」という物質には覚醒作用があります。
そのため、飲み始めは眠くても、数時間後には目が覚めやすくなり、結果的に睡眠が浅く、断続的になってしまうのです。
利尿作用によって夜中にトイレに行きたくなることも、中途覚醒の大きな原因となります。
「寝酒」は百害あって一利なし、と心得ておきましょう。
カフェインの過剰摂取
コーヒーや紅茶、緑茶などに含まれるカフェインは、眠気を覚ます効果があることで知られています。
この覚醒作用は、脳内で眠りを誘う物質「アデノシン」の働きをブロックすることで起こります。
カフェインの効果は個人差がありますが、一般的に摂取してから30分ほどで効き始め、その効果は4時間から長い人では8時間以上続くこともあります。
そのため、夕方以降にカフェインを摂取すると、いざ眠ろうという時間になっても脳が覚醒したままになり、寝つきが悪くなる原因になります。
また、眠れたとしても、睡眠が浅くなる傾向があります。
カフェインは意外な飲み物や食べ物にも含まれているため、注意が必要です。
夜のリラックスタイムには、カフェインレスのコーヒーやハーブティーなどを選ぶのがおすすめです。
| 種類 | カフェインを含む主な飲食物の例 |
|---|---|
| 飲み物 | コーヒー、紅茶、緑茶、ほうじ茶、ウーロン茶、玉露、エナジードリンク、栄養ドリンク、コーラなど |
| 食べ物 | チョコレート、ココア、一部のアイスクリームや菓子類 |
| その他 | 一部の風邪薬や鎮痛剤などの医薬品 |
熱すぎるお風呂や激しい運動
「体を芯から温めてぐっすり眠ろう」と、熱いお風呂にゆっくり浸かっていませんか?
実は、42℃を超えるような熱すぎるお湯は、安眠のためには逆効果になってしまうことがあります。
私たちの体は、体の内部の温度(深部体温)が下がる過程で自然な眠気を感じるようにできています。
熱すぎるお風呂に入ると、交感神経が刺激されてしまい、心拍数が上がり、体と脳が興奮・覚醒モードに入ってしまいます。
深部体温が上がりすぎてしまうと、就寝に適した温度まで下がるのに時間がかかり、かえって寝つきを悪くしてしまうのです。
快眠のためには、就寝の90分ほど前に38℃から40℃のぬるめのお湯に15分程度浸かるのが理想的です。
同様に、寝る前の激しい運動も避けましょう。
日中の適度な運動は心地よい疲労感をもたらし、夜の快眠につながりますが、就寝直前のランニングや筋力トレーニングといった激しい運動は、お風呂と同じく交感神経を活発にし、心拍数や体温を上昇させます。
体が「これから活動するぞ!」という状態になってしまうため、リラックスして眠りにつくことが難しくなります。
夜に運動をする場合は、軽いストレッチやヨガなど、心身を落ち着かせるものに留めておきましょう。
5. まとめ
夏の疲れを引きずったまま、秋の夜長をなんとなく過ごしていませんか?
この記事では、秋に睡眠の質が下がりやすい原因と、それを解消するための時間帯別の習慣をご紹介しました。
大切なのは、朝の太陽光で体内時計をリセットし、日中の適度な活動で心地よい疲労感を得て、夜は心と体をリラックスさせる一連の流れを作ることです。
まずは一つ、あなたに合った習慣から試してみてください。
質の高い睡眠が、明日への活力をきっと与えてくれますよ。
商品カテゴリから探す