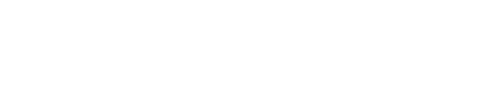健考彩都コラム
- TOP
- 寒暖差疲労の症状・原因・対策を完全網羅!自律神経を整えてだるさを解消する方法

寒暖差疲労の症状・原因・対策を完全網羅!自律神経を整えてだるさを解消する方法
2025年9月12日
季節の変わり目やクーラーが効いた室内で、原因不明のだるさや頭痛を感じること、ありませんか?
その不調、もしかしたら「寒暖差疲労」かもしれません。
実は、その根本原因は急激な温度変化による自律神経の乱れにあります。
この記事を読めば、ご自身の症状のチェックから、原因の理解、そして食事や入浴法など今日からできる具体的な対策まで、つらいだるさを解消する方法がすべてわかります。
- 1. まずはセルフチェック 寒暖差疲労の主な症状
- 全身に現れる症状 だるさや倦怠感
- 体の一部に現れる症状 頭痛や肩こり
- 精神的な症状 イライラや気分の落ち込み
- 2. なぜ起こる?寒暖差疲労の根本的な原因は自律神経の乱れ
- 急激な温度変化が自律神経を疲弊させる
- 寒暖差疲労になりやすい人の特徴とは
- 3. 今日からできる 寒暖差疲労の具体的な対策5選
- 対策1 食事で体を内側から温める
- 対策2 服装で温度調節をこまめに行う
- 対策3 簡単な運動で血行を促進する
- 対策4 入浴で副交感神経を優位にする
- 対策5 睡眠の質を高めて体をしっかり休める
- 4. つらい症状が続く場合は病院へ 何科を受診すべきか
- まずは「内科」か「総合診療科」がおすすめ
- 症状別に見る受診先の目安
- 医師に正しく症状を伝えるための準備
- 5. まとめ
1. まずはセルフチェック 寒暖差疲労の主な症状
季節の変わり目に感じる、なんだかよくわからない体の不調。「しっかり寝たはずなのに、朝から体が重い…」「理由もなくイライラしてしまう…」なんてこと、ありませんか?
もしかしたら、そのだるさや気分の落ち込みは「寒暖差疲労」が原因かもしれません。
寒暖差疲労とは、その名の通り、急激な気温の変化に体がついていけず、自律神経が乱れてしまうことで起こるさまざまな不調のことです。
私たちの体は、自律神経が働くことで体温を一定に保っていますが、気温差が激しいと、この体温調節にエネルギーを使いすぎてしまい、心身ともに疲弊してしまうのです。
まずは、ご自身の症状が寒暖差疲労に当てはまるか、下のリストでチェックしてみましょう。
全身に現れる症状 だるさや倦怠感
寒暖差疲労のサインとして最も多くの方が感じるのが、全身の倦怠感です。
自律神経が体温調節にフル稼働することで、自分でも気づかないうちにエネルギーを大量に消耗してしまいます。
その結果、十分な休息をとっても疲れが抜けず、常に体がだるい、重いといった状態に陥りやすくなります。
特に、以下のような症状に心当たりはありませんか?
- 全身の倦怠感、疲労感
- 朝、すっきりと起きられない
- 手足や体の冷え
- めまいや立ちくらみ
- 食欲がない、または食べ過ぎてしまう
- 寝つきが悪い、夜中に何度も目が覚める
これらの症状は、体が「少し休んでほしい」と送っているサインかもしれません。
見過ごさずに、自分の体調と向き合うことが大切です。
体の一部に現れる症状 頭痛や肩こり
自律神経の乱れは、全身の血行にも影響を及ぼします。
体温を維持しようと血管が収縮を繰り返すことで血流が悪くなり、筋肉が緊張しやすくなるのです。
その結果、体の一部に痛みや不調として現れることがあります。
代表的な症状としては、以下のようなものが挙げられます。
- ズキズキ、あるいは締め付けられるような頭痛
- 慢性的な肩こりや首のこり
- 関節の痛みや古傷の痛み
- 鼻水、くしゃみ、鼻づまり(花粉症などのアレルギーと間違えやすい)
- 胃痛や腹痛、便秘や下痢など胃腸の不調
特に、頭痛や肩こりは、寒暖差による血行不良が直接的な原因となりやすいため、注意が必要です。
「いつものことだから」と放置せず、寒暖差疲労の可能性を考えてみましょう。
精神的な症状 イライラや気分の落ち込み
体の不調は、心の状態にも大きく影響します。
自律神経は、私たちの感情や気分をコントロールする働きも担っているため、そのバランスが崩れると精神的にも不安定になりがちです。
「体の不調」と「心の不調」がセットで現れるのが、寒暖差疲労の大きな特徴とも言えます。
もし、以下のような心の変化を感じていたら、それは体がSOSを出しているサインかもしれません。
- ささいなことでイライラしてしまう
- 理由もなく不安な気持ちになる
- 気分が落ち込み、やる気が出ない
- 物事に集中できない
- 人付き合いが億劫に感じる
体の疲れだけでなく、心の疲れも感じている場合は、無理をせず、自分をいたわってあげることが何よりも重要です。
それでは、ここまでの症状をまとめてチェックしてみましょう。
当てはまる項目がいくつあるか、数えてみてください。
| 分類 | 症状 | チェック |
|---|---|---|
| 全身の症状 | 全身がだるく、疲れがとれない | □ |
| 朝すっきりと起きられない | □ | |
| 体が冷えやすい | □ | |
| めまいや立ちくらみがする | □ | |
| 寝つきが悪い、眠りが浅い | □ | |
| 体の一部の症状 | 頭痛や肩こりがひどい | □ |
| 鼻水や鼻づまりがある | □ | |
| 胃腸の調子が悪い(食欲不振、胃もたれなど) | □ | |
| 関節や古傷が痛む | □ | |
| 精神的な症状 | ささいなことでイライラする | □ |
| 気分が落ち込みやすい | □ | |
| 集中力が続かない、やる気が出ない | □ |
いかがでしたか?
もし、3つ以上当てはまる項目があれば、あなたは「寒暖差疲労」の可能性が高いかもしれません。
しかし、心配しすぎる必要はありません。
原因を知り、正しく対策することで、つらい症状は改善できます。
次の章からは、なぜ寒暖差疲労が起こるのか、そのメカニズムと具体的な対策について詳しく解説していきます。
2. なぜ起こる?寒暖差疲労の根本的な原因は自律神経の乱れ
季節の変わり目に感じる原因不明のだるさや、夏場にクーラーが効いた室内と暑い屋外を行き来したときのぐったり感。
あなたも一度は経験したことがあるのではないでしょうか。
こうした不調の多くは、「寒暖差疲労」が原因かもしれません。
私たちの体は、暑いときも寒いときも体温を一定に保とうとする素晴らしい機能を持っています。
この重要な役割を担っているのが「自律神経」です。
しかし、急激な温度の変化に何度もさらされると、この自律神経が対応しきれずに疲弊し、バランスを崩してしまうのです。
これが、寒暖差疲労を引き起こす根本的なメカニズムです。
急激な温度変化が自律神経を疲弊させる
自律神経には、体を活動的にする「交感神経」と、リラックスさせる「副交感神経」の2種類があります。
これらがシーソーのようにバランスを取りながら、私たちの意思とは関係なく心臓や血管、内臓の働きを24時間コントロールしてくれています。
体温調節もその一つです。
例えば、気温が高いときは血管を広げて熱を逃がし、汗をかいて体を冷やそうとします。
逆に気温が低いときは、血管をキュッと収縮させて熱が逃げるのを防ぎ、筋肉を震わせて熱を生み出します。
このとき、自律神経は目まぐるしく働いて、体を環境に適応させようと頑張っているのです。
しかし、一般的に7度以上の急な温度差に繰り返し対応していると、自律神経は常にフル稼働の状態になります。
これは、スマートフォンのアプリをたくさん立ち上げっぱなしにして、バッテリーがどんどん消耗していく状態と似ています。
エネルギーを過剰に消費し続けた結果、自律神経の働きが鈍くなり、バランスが崩れてしまいます。
その結果、体温調節がうまくいかなくなるだけでなく、全身の倦怠感や頭痛、肩こり、めまいといった様々な不調となって体に現れるのです。
寒暖差疲労になりやすい人の特徴とは
寒暖差疲労は誰にでも起こりうるものですが、特に影響を受けやすい人がいます。
ご自身の生活習慣や体質と照らし合わせて、チェックしてみてください。
| 特徴 | 寒暖差疲労になりやすい理由 |
|---|---|
| 冷え性の人 | もともと血行が悪く、手足などが冷えやすい方は体温調節機能がうまく働いていない傾向があります。 そのため、わずかな温度変化でも自律神経に大きな負担がかかりやすくなります。 |
| 運動不足の人 | 筋肉は体内で熱を生み出す大切な役割を担っています。 運動不足で筋肉量が少ないと、熱を産生する力が弱く、血行も滞りがちになるため、寒暖差に対応しにくくなります。 |
| ストレスを溜めやすい人 | 精神的なストレスは、自律神経のバランスを乱す直接的な原因になります。 仕事や人間関係などで強いストレスを感じていると、寒暖差という身体的なストレスが加わったときに、不調が出やすくなります。 |
| 不規則な生活を送っている人 | 睡眠不足や食事の時間がバラバラといった不規則な生活は、自律神経のリズムそのものを崩してしまいます。 生活リズムが乱れていると、環境の変化に対する体の適応力も低下してしまいます。 |
| エアコンの効いた環境で長時間過ごす人 | 特に夏や冬に、一日中エアコンの効いたオフィスで過ごす方は注意が必要です。 屋内外の激しい温度差に体が何度もさらされるため、自律神経が常に緊張状態を強いられます。 |
もし、これらの特徴に複数当てはまるようであれば、あなたは寒暖差疲労になりやすいタイプかもしれません。
しかし、落ち込む必要はありません。
これは、ご自身の生活を見直す良いきっかけになります。
次の章でご紹介する対策を実践して、自律神経をいたわってあげましょう。
3. 今日からできる 寒暖差疲労の具体的な対策5選
つらい寒暖差疲労ですが、実は日々のちょっとした工夫で和らげることができます。
自律神経は私たちの意識とは関係なく働いていますが、生活習慣を整えることで、その働きをサポートすることが可能です。
ここでは、誰でも今日からすぐに始められる5つの具体的な対策をご紹介します。
ぜひあなたの生活に取り入れて、季節の変わり目も元気に過ごしましょう。
対策1 食事で体を内側から温める
私たちの体は、食べたもので作られています。
特に冷えを感じやすい方は、食事を見直すことが寒暖差疲労対策の第一歩です。
体を内側からじっくり温める「温活」を意識して、自律神経が働きやすい体内環境を整えていきましょう。
おすすめの食べ物と飲み物
体を温める作用のある食材を積極的に摂ることが大切です。
特に、冬が旬の野菜や寒い土地で採れる食材は、体を温める効果が期待できます。
毎日の食事に少しずつプラスしてみてください。
| 分類 | 具体的な食材・飲み物 | ポイント |
|---|---|---|
| 根菜類 | しょうが、にんにく、ごぼう、にんじん、れんこん、玉ねぎ | 血行を促進する成分が含まれています。 スープや煮込み料理に加えるのがおすすめです。 |
| タンパク質 | 鶏肉、ラム肉、サバ、アジ、納豆、味噌 | 筋肉や血液の材料となり、熱を生み出す基礎代謝をサポートします。 発酵食品である味噌や納豆も体を温めます。 |
| スパイス | 唐辛子、こしょう、シナモン、山椒 | 料理のアクセントに使うことで、発汗を促し血流を良くする効果が期待できます。 |
| 飲み物 | 白湯、ハーブティー(ジンジャー、カモミール)、ココア | 常温以上の飲み物を選びましょう。 特に白湯は、胃腸を温め、内臓の働きを活発にしてくれます。 |
避けるべき食事
体を温める食材がある一方で、体を冷やしやすい食べ物や飲み物も存在します。
これらを完全に断つ必要はありませんが、摂りすぎには注意が必要です。
特に体調が優れないと感じるときは、意識して控えるようにしましょう。
| 分類 | 具体的な食材・飲み物 | 注意点 |
|---|---|---|
| 体を冷やす食べ物 | きゅうり、トマト、なすなどの夏野菜、バナナ、パイナップルなどの南国の果物 | 水分が多く、体を内側から冷やす性質があります。 食べるときは加熱調理するなどの工夫をしましょう。 |
| 冷たい飲み物・食べ物 | アイスクリーム、かき氷、氷入りのジュース | 胃腸を直接冷やし、消化機能の低下や全身の冷えにつながります。 |
| その他 | 白砂糖を多く使ったお菓子、カフェインを多く含む飲み物(コーヒー、緑茶など) | 白砂糖は血糖値を急激に変動させ、自律神経に負担をかけます。 カフェインの過剰摂取は交感神経を刺激しすぎる可能性があります。 |
対策2 服装で温度調節をこまめに行う
屋外の寒さと、暖房が効いた室内の暑さ。
この激しい温度差に体が対応しようとすることで、自律神経はエネルギーを大量に消費してしまいます。
こまめに着脱できる服装で、体が感じる温度差をできるだけ小さくすることが、疲労を防ぐカギとなります。
- 基本は「重ね着(レイヤリング)」:薄手の服を何枚か重ね着するのが基本です。
カーディガンやパーカー、ストールなど、暑いと感じたらすぐに脱げる、寒いと感じたらすぐに羽織れるアイテムを活用しましょう。 - インナー選びも重要:吸湿性や保温性に優れた機能性インナーを選ぶと、汗をかいても体が冷えにくくなります。
綿やシルクなどの天然素材もおすすめです。 - 「三首」を温める:「首」「手首」「足首」は皮膚のすぐ下に太い血管が通っているため、ここを温めると効率よく全身を温めることができます。
ネックウォーマーやマフラー、アームウォーマー、レッグウォーマー、厚手の靴下などを上手に使いましょう。 - 夏場の冷房対策:季節は冬に限りません。
夏場もオフィスや電車内の冷房が効きすぎていることがあります。
常に薄手の羽織ものを一枚カバンに入れておくと安心です。
対策3 簡単な運動で血行を促進する
じっとしている時間が長いと、筋肉が硬くなり血行が悪化してしまいます。
血流が滞ると、体の隅々まで酸素や栄養が届きにくくなり、疲労物質も溜まりがちに。
特別な運動でなくても、意識的に体を動かして血の巡りを良くするだけで、自律神経の働きを大きくサポートできますよ。
オフィスでもできるストレッチ
デスクワーク中、同じ姿勢が続いているなと感じたら、1時間に1回程度、簡単なストレッチを取り入れてみましょう。
座ったままでもできるので、仕事の合間にぜひ試してみてください。
- 首のストレッチ:ゆっくりと首を前後左右に倒したり、大きく回したりして、首周りの筋肉をほぐします。
- 肩のストレッチ:両肩をぐっと耳に近づけるように引き上げ、ストンと力を抜いて下ろします。
これを数回繰り返しましょう。 - 背伸び:両手を組んで、天井に向かってぐーっと伸びをします。
背中や脇腹が伸びているのを感じましょう。 - 足首のストレッチ:椅子に座ったまま、かかとを床につけたままつま先を上げ下げしたり、足首をぐるぐる回したりします。
ウォーキングなどの有酸素運動
本格的な運動が苦手な方でも、ウォーキングなら気軽に始められるのではないでしょうか。
リズミカルな有酸素運動は、血行促進だけでなく、セロトニンという心のバランスを整えるホルモンの分泌を促す効果も期待できます。
1日20~30分を目安に、少し汗ばむくらいのペースで歩いてみましょう。
エレベーターを階段に変える、一駅手前で降りて歩くなど、日常生活の中で体を動かす機会を増やすだけでも効果的です。
対策4 入浴で副交感神経を優位にする
忙しい毎日を送っていると、ついシャワーだけで済ませてしまいがちですが、それはとてももったいないこと。
ゆっくりと湯船に浸かることは、寒暖差疲労対策において非常に効果的です。
体を芯から温め、心と体をリラックスモードに切り替えましょう。
ポイントは、38℃~40℃くらいのぬるめのお湯に、10分~15分ほど浸かること。
これにより、心身をリラックスさせる働きを持つ「副交感神経」が優位になります。
血行が促進され、筋肉の緊張がほぐれることで、質の良い睡眠にもつながります。
逆に、42℃以上の熱いお湯は体を興奮させる「交感神経」を刺激してしまうため、寝る前には避けたほうが良いでしょう。
ラベンダーやカモミールなど、リラックス効果のある香りの入浴剤やアロマオイルを使うのもおすすめです。
対策5 睡眠の質を高めて体をしっかり休める
日中の活動で疲弊した自律神経を回復させるためには、何よりも質の高い睡眠が不可欠です。
ただ長時間寝るのではなく、「ぐっすり眠る」ための環境を整え、心身をしっかりと休ませてあげることが重要になります。
- 就寝前のスマホ・PCは控える:スマートフォンやパソコンの画面から発せられるブルーライトは、脳を覚醒させ、睡眠を促すホルモン「メラトニン」の分泌を抑制してしまいます。
少なくとも就寝1~2時間前には使用を終えるように心がけましょう。 - 寝室の環境を整える:部屋の照明を暖色系の暗めのものにしたり、遮光カーテンを利用したりして、光の刺激を減らしましょう。
また、静かで快適な温度・湿度を保つことも大切です。 - 自分に合った寝具を選ぶ:枕の高さやマットレスの硬さが合っていないと、体に負担がかかり、睡眠の質が低下する原因になります。
- 毎日同じ時間に起きる:休日でも平日と同じ時間に起きることで、体内時計のリズムが整いやすくなります。
規則正しい生活リズムは、自律神経の安定に直結します。
4. つらい症状が続く場合は病院へ 何科を受診すべきか
セルフケアを続けてもなかなか症状が改善しない、あるいは日常生活に支障が出るほどのつらさを感じているなら、我慢せずに医療機関を受診することを考えましょう。
寒暖差疲労の症状は、他の病気が隠れているサインかもしれません。
専門家である医師に相談することで、的確な診断と治療につながり、つらい症状から解放される近道になります。
とはいえ、「何科に行けばいいの?」と迷ってしまいますよね。
ここでは、症状に合わせてどの診療科を受診すればよいのか、その目安を具体的にお伝えします。
まずは「内科」か「総合診療科」がおすすめ
どの症状が一番つらいのかはっきりしない、あるいは全身にだるさや倦怠感といった症状が出ている場合は、まず「内科」か「総合診療科」を受診するのがおすすめです。
全身の状態を総合的に診察し、症状の原因を幅広く探ってくれます。
必要に応じて、より専門的な診療科を紹介してくれるので、最初の相談窓口として最適です。
寒暖差疲労の背景に、貧血や甲状腺の病気など、他の内科的な疾患が隠れていないかを確認する意味でも重要です。
症状別に見る受診先の目安
特定の症状が特に気になる場合は、その症状に合わせた専門の診療科を受診することも選択肢の一つです。
以下の表を参考に、ご自身の症状に合った診療科を選んでみてください。
| 特に気になる症状 | 考えられる診療科 | 受診のポイント |
|---|---|---|
| 頭痛・めまい・耳鳴り | 耳鼻咽喉科・神経内科 |
ぐるぐる回るような回転性のめまいや、耳鳴り・難聴を伴う場合は「耳鼻咽喉科」へ。 |
| ひどい肩こり・首こり・腰痛 | 整形外科 |
マッサージやストレッチでは改善しない、つらいこりや痛みがある場合に適しています。 |
| 気分の落ち込み・不安感・不眠 | 心療内科・精神科 |
イライラや不安感が強く、夜もよく眠れないなど、精神的な不調が続く場合は相談してみましょう。 |
| ほてり・のぼせ・動悸(女性の場合) | 婦人科 |
特に40代以降の女性で、顔のほてりや急な発汗、動悸といった症状がある場合、寒暖差疲労だけでなく更年期障害の可能性も考えられます。 |
医師に正しく症状を伝えるための準備
診察を受ける際には、ご自身の症状をできるだけ正確に、そして具体的に伝えることが大切です。
事前に以下のポイントをメモにまとめておくと、診察がスムーズに進み、医師も的確な判断をしやすくなります。
- いつから症状が始まったか:「1ヶ月前の季節の変わり目から」など
- どんな症状があるか:だるさ、頭痛、めまい、気分の落ち込みなど、具体的に
- 症状が起こるタイミング:「朝起きた時が一番つらい」「冷房の効いた部屋に入ると頭が痛くなる」など
- 症状の頻度や継続時間:「週に3回ほど、半日くらい続く」など
- 生活への影響:「仕事に集中できない」「外出するのが億劫になった」など
- すでに行っている対策:「入浴や食事に気をつけているが、あまり変わらない」など
- 他に気になる体の変化や持病、服用中の薬など
大切なのは、自己判断で「ただの疲れ」と決めつけないことです。
つらい症状には必ず原因があります。
専門家の力を借りて、心と体の両方から健康な状態を取り戻していきましょう。
5. まとめ
季節の変わり目に感じる、なんだかスッキリしないそのだるさ。
もしかしたら、それは「寒暖差疲労」が原因かもしれませんね。
急激な温度変化で自律神経が乱れることで起こるこの症状は、食事や服装、入浴といった日々のちょっとした工夫で和らげることができます。
この記事でご紹介した5つの対策は、今日からすぐに始められるものばかり。
ぜひ生活に取り入れて、つらい不調を乗り越えていきましょう。
商品カテゴリから探す