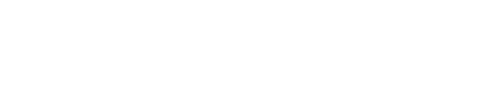健考彩都コラム
- TOP
- 残暑を乗り切る!つらい残暑バテを解消する体調管理と免疫力アップの秘訣

残暑を乗り切る!つらい残暑バテを解消する体調管理と免疫力アップの秘訣
2025年9月5日
夏の終わりが見えてきたのに、なんだか疲れが取れず体がだるい…そんな不調を感じていませんか?
実はその症状、夏バテとは少し違う「残暑バて」が原因かもしれません。
つらい残暑バテを乗り切る鍵は、夏の間に蓄積した自律神経の乱れを整え、低下した免疫力を回復させることにあります。
この記事では、食事や睡眠、簡単な運動から免疫力を高める生活習慣まで、今日から実践できる体調管理の秘訣をわかりやすく解説します。
- 1. 夏バテとは違う?残暑バテ特有のメカニズム
- 夏バテと残暑バテ、似ているようで違う「原因」
- 残暑バテを引き起こす3つの大きな要因
- こんな症状は要注意!残暑バテのサイン
- 2. 残暑を乗り切るための体調管理の基本は自律神経
- 食事で整える自律神経バランス
- 睡眠で整える自律神経バランス
- 軽い運動で整える自律神経バランス
- 3. 免疫力アップに特化 残暑に負けない体づくりの方法
- 免疫細胞の7割が集まる腸を元気にする食事術
- 体温を上げて免疫力を高める入浴法と服装の工夫
- 心と体の相関関係 ストレスケアで免疫力を維持する
- 4. 今日から実践できる残暑対策のチェックリスト
- 食事編:残暑バテ知らずの体を作る食生活
- 生活習慣編:自律神経を整える毎日のルーティン
- 心と体のセルフケア編:ストレスを上手に解消する工夫
- 5. まとめ
1. 夏バテとは違う?残暑バテ特有のメカニズム
「夏の疲れがなかなか抜けない…」「なんだか体が重くて、やる気が出ない…」
暦の上では秋が近づいているのに、真夏よりも体調が優れないと感じること、ありませんか?
それは多くの人が経験する「夏バテ」とは少し違う、この時期特有の「残暑バテ」かもしれません。
夏バテも残暑バテも、だるさや食欲不振といった似た症状が現れますが、その原因には大きな違いがあります。
まずはそのメカニズムを正しく理解することが、つらい不調から抜け出すための第一歩です。
夏バテと残暑バテ、似ているようで違う「原因」
夏真っ盛りの不調である「夏バテ」は、主に高温多湿の環境に体が対応しきれず、体温調節がうまくいかなくなることで起こります。
大量の汗をかくことによる水分・ミネラル不足や、暑さによる食欲不振、寝苦しさによる睡眠不足が主な原因です。
一方、「残暑バテ」は、これらの夏の疲れが体に蓄積した状態で、さらに秋口特有の要因が加わることで引き起こされます。
その最大の原因こそが、日中と朝晩、また室内と屋外で生じる「激しい寒暖差」です。
夏の間に溜め込んだダメージと、急な気温の変化というダブルパンチが、私たちの体に大きな負担をかけてしまうのです。
残暑バテを引き起こす3つの大きな要因
では、具体的にどのような要因が残暑バテにつながるのでしょうか?
ここでは、体に起こっていることを3つのポイントに分けて詳しく見ていきましょう。
① 体内外の「寒暖差」による自律神経の乱れ
残暑の時期は、日中はまだ30℃を超える厳しい暑さが続く一方で、朝晩は涼しい風が吹くなど、一日の中での気温差が大きくなります。
また、屋外の蒸し暑さと、冷房が効いた室内との温度差も依然として大きいままです。
私たちの体は、この激しい温度変化に対応しようと、体温をコントロールする「自律神経」をフル稼働させます。
しかし、この状態が続くと自律神経が過剰に働きすぎて疲弊してしまい、交感神経と副交感神経のバランスが崩れてしまいます。
その結果、だるさ、めまい、頭痛、不眠といった、原因のわからない様々な不調となって現れるのです。
② 夏の間の「冷え」の蓄積
暑い夏の間、私たちは冷たい飲み物や食べ物、そうめんやアイスクリームなどを口にする機会が増えます。
さらに、一日中冷房の効いた環境で過ごすことも少なくありません。
こうした生活習慣は、知らず知らずのうちに体、特に内臓を芯から冷やしてしまいます。
内臓の温度が下がると、胃腸の働きが弱まって消化不良や食欲不振を招くだけでなく、全身の血行も悪くなります。
血行不良は、肩こりや頭痛、疲労感の直接的な原因となり、残暑の時期になって一気に不調として表面化することが多いのです。
③ 夏の疲れの「蓄積」と日照時間の変化
ひと夏を越した体は、私たちが思う以上にエネルギーを消耗し、疲労を溜め込んでいます。
十分な休息が取れないまま秋口を迎えると、わずかな環境の変化でも体調を崩しやすくなります。
また、夏至を過ぎて少しずつ日照時間が短くなっていくことも、心身に影響を与える一因です。
太陽の光を浴びる時間が減ると、精神を安定させる働きのある神経伝達物質「セロトニン」の分泌が減少し、なんとなく気分が落ち込んだり、やる気が出なくなったりすることがあります。
これも残暑バテに見られる特徴的な症状の一つです。
こんな症状は要注意!残暑バテのサイン
ご自身の体調が夏バテなのか、それとも残暑バテなのか、具体的な症状からチェックしてみましょう。
下の表で、残暑バテで特に顕著に現れやすい症状を確認してみてください。
| 症状 | 夏バテとの共通点 | 残暑バテで特に見られやすい特徴 |
|---|---|---|
| 全身の倦怠感・疲労感 | 〇(共通して見られる) | 夏の疲れが抜けず、朝起きるのが特につらい。 |
| 食欲不振・胃腸の不調 | 〇(共通して見られる) | 内臓の冷えによる消化機能の低下が顕著で、下痢や便秘を伴いやすい。 |
| 頭痛・肩こり・めまい | △(夏バテでも起こる) | 寒暖差による自律神経の乱れや血行不良が原因で、症状が強く出やすい。 |
| 睡眠の質の低下 | △(寝苦しさは夏バテ) | 寝付きが悪い、夜中に何度も目が覚めるなど、自律神経の乱れによる不眠が特徴。 |
| 気分の落ち込み・イライラ | ✕(あまり見られない) | わけもなく不安になったり、やる気が出なかったりと、精神的な不調を伴いやすい。 |
もし、リストの中でも特に「胃腸の不調」や「頭痛・肩こり」、そして「精神的な落ち込み」といった症状に心当たりがあれば、それは残暑バテのサインかもしれません。
次の章からは、このつらい残暑バテを乗り切るための具体的な体調管理術について詳しく解説していきます。
2. 残暑を乗り切るための体調管理の基本は自律神経
夏の疲れがドッと出てくる残暑の季節。
「なんだか体がだるい」「やる気が出ない」と感じるなら、それは自律神経の乱れが原因かもしれません。
私たちの体は、活動モードの「交感神経」とリラックスモードの「副交感神経」という2つの自律神経が、まるでシーソーのようにバランスを取りながら心身の調子を整えています。
しかし、夏の間に続いた猛暑や冷房による屋内外の激しい気温差、そして残暑の時期特有の朝晩の気温変化によって、このシーソーのバランスが崩れやすくなってしまうのです。
この自律神経の乱れこそが、残暑バテを引き起こす最大の原因。
だからこそ、残暑を元気に乗り切るためには、この自律神経のバランスを意識的に整える生活習慣が何よりも大切になります。
食事で整える自律神経バランス
毎日何気なく摂っている食事が、実は自律神経のバランスに大きな影響を与えていることをご存知ですか?
「何を食べるか」はもちろん、「いつ、どのように食べるか」も重要なポイント。
まずは、自律神経を整える働きを持つ栄養素を積極的に食事に取り入れてみましょう。
特に意識して摂りたい栄養素と、それが豊富な食材を下の表にまとめました。
| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食材の例 |
|---|---|---|
| トリプトファン | 精神を安定させるセロトニンの材料。 セロトニンは夜になると睡眠を促すメラトニンに変わる。 |
大豆製品(豆腐・納豆・味噌)、乳製品(牛乳・ヨーグルト・チーズ)、バナナ、ナッツ類 |
| ビタミンB群(特にB6, B12) | 神経の働きを正常に保ち、エネルギー代謝をサポート。 セロトニンの合成にも不可欠。 |
豚肉、うなぎ、レバー、まぐろ、かつお、玄米、卵 |
| GABA(ギャバ) | 興奮を鎮め、リラックス効果をもたらすアミノ酸の一種。 ストレス緩和に役立つ。 |
トマト、かぼちゃ、発芽玄米、じゃがいも |
| ビタミンC | ストレスに対抗するためのホルモンを作る際に大量に消費される。 抗酸化作用も高い。 |
パプリカ、ブロッコリー、キウイフルーツ、柑橘類 |
これらの食材をバランス良く取り入れることに加えて、朝食を抜かずに毎日決まった時間に食べることも大切です。
朝食は、乱れがちな体内時計をリセットし、自律神経のリズムを整えるスイッチの役割を果たします。
また、よく噛んでゆっくり食べることで副交感神経が優位になり、消化吸収も助けてくれますよ。
睡眠で整える自律神経バランス
日中に活発に働いた交感神経を鎮め、心と体を修復する副交感神経が優位になるのが睡眠の時間です。
つまり、質の良い睡眠をとることは、自律神経のバランスをリセットするための最も重要な時間と言えるでしょう。
しかし、残暑の時期は夜になっても気温が下がらず、寝苦しさから睡眠が浅くなりがち。
だからこそ、意識的に睡眠の質を高める工夫が必要です。
質の高い睡眠は、最高の疲労回復薬であり、自律神経の調整役です。
今日からできる快眠のコツをいくつかご紹介します。
- 就寝1~2時間前に入浴する: 38~40℃くらいのぬるめのお湯に15分ほど浸かりましょう。
体の深部体温が一旦上がり、その後下がっていく過程で自然な眠気が訪れます。
熱すぎるお湯は交感神経を刺激してしまうので逆効果です。 - 就寝前のスマホやPC操作を控える: スマートフォンやPCの画面から発せられるブルーライトは、脳を覚醒させ、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を抑制してしまいます。
就寝1時間前には画面から離れ、リラックスする時間を設けましょう。 - 快適な寝室環境を整える: エアコンのタイマー機能を活用し、室温を26~28℃程度に保つのがおすすめです。
直接体に風が当たらないように風向きを調整し、通気性や吸湿性に優れたパジャマや寝具を選ぶと、より快適に眠れます。
「たかが睡眠」と侮ってはいけません。
睡眠不足が続くと、自律神経の乱れはますます深刻になってしまいます。
まずはできることから試してみてくださいね。
軽い運動で整える自律神経バランス
「疲れているのに運動なんて…」と思うかもしれませんが、実は適度な運動は自律神経のバランスを整えるのに非常に効果的です。
体を動かすことで全身の血行が良くなり、乱れがちな自律神経のリズムを整えるきっかけになります。
ポイントは、激しい運動ではなく、心地よいと感じる程度の「軽い運動」を習慣にすること。
汗だくになるようなハードなトレーニングは、かえって交感神経を過剰に刺激し、疲労を蓄積させてしまう可能性があります。
残暑の時期におすすめなのは、次のような運動です。
- 朝夕のウォーキング: 比較的涼しい時間帯を選んで、20~30分程度歩いてみましょう。
一定のリズムで行う運動は、精神を安定させるセロトニンの分泌を促す効果も期待できます。 - 就寝前のストレッチ: 固まった筋肉をゆっくりとほぐすストレッチは、副交感神経を優位にし、心身をリラックスモードに切り替えてくれます。
深い呼吸を意識しながら行うのがコツです。 - 室内でできるヨガやピラティス: 涼しい室内で、自分のペースで行えるヨガやピラティスもおすすめです。
特に呼吸を重視する動きは、自律神経のバランス調整に直接働きかけます。
運動を続けるコツは、完璧を目指さないこと。
「今日は5分だけ」という日があっても大丈夫です。
まずは体を動かす気持ちよさを感じてみてください。
その心地よさが、きっとあなたの心と体のバランスを整える手助けをしてくれるはずです。
3. 免疫力アップに特化 残暑に負けない体づくりの方法
夏の間に蓄積した疲れと、朝晩の気温差が大きくなる残暑の時期。
私たちの体は知らず知らずのうちにストレスを感じ、免疫力が低下しがちになります。
ここからは、残暑バテに負けない体を作るために、免疫力を高めることに特化した具体的な方法をご紹介します。
体の内側からコンディションを整えて、秋を元気に迎えましょう。
免疫細胞の7割が集まる腸を元気にする食事術
「腸は第二の脳」とも呼ばれるほど、私たちの健康に深く関わっています。
実は、体を守る免疫細胞の約7割は腸に集中していると言われているのです。
つまり、腸内環境を整える「腸活」こそが、免疫力アップへの一番の近道。
日々の食事を少し見直すだけで、腸は応えてくれますよ。
発酵食品と食物繊維を積極的に摂る
元気な腸内環境を育むためには、「善玉菌」を増やすことがカギとなります。
そのために意識したいのが、「発酵食品」と「食物繊維」をセットで摂ることです。
発酵食品には、乳酸菌やビフィズス菌といった善玉菌そのものが豊富に含まれています。
日本の食卓に馴染み深い、納豆や味噌、ぬか漬け、ヨーグルト、甘酒などを毎日の食事にプラスしてみましょう。
そして、その善玉菌のエサとなるのが食物繊維です。
特に、わかめなどの海藻類や、ごぼう・きのこ類、大豆製品に多く含まれています。
善玉菌を食事で補給し、そのエサとなる食物繊維を一緒に摂ることで、効率よく腸内で善玉菌を育てることができるのです。
例えば、わかめと豆腐の味噌汁にきのこを加えたり、ヨーグルトにきな粉をトッピングしたりするだけで、手軽に実践できます。
体を冷やす食べ物と温める食べ物
残暑の時期は、つい冷たい飲み物や食べ物に手が伸びがちですが、内臓が冷えると血行が悪くなり、腸の働きも鈍ってしまいます。
これが免疫力の低下につながることも。
体を冷やす食べ物と温める食べ物を上手に使い分けて、内側から体を守りましょう。
体を冷やす性質のある夏野菜なども、加熱調理をしたり、体を温める香味野菜(生姜、ネギなど)と組み合わせたりすることで、バランスをとることができます。
すべてを避けるのではなく、賢く取り入れる工夫が大切です。
| 体を温める食べ物・飲み物 | 体を冷やす食べ物・飲み物 |
|---|---|
| 生姜、にんにく、ネギ、唐辛子、かぼちゃ、ごぼう、人参、玉ねぎ、納豆、味噌、チーズ、鶏肉、羊肉、サバ、アジ、鮭、玄米、紅茶、ほうじ茶、ココア | きゅうり、トマト、なす、レタス、ゴーヤ、スイカ、メロン、バナナ、パイナップル、豆腐、牛乳、緑茶、コーヒー、ジュース類、白砂糖 |
体温を上げて免疫力を高める入浴法と服装の工夫
体温は、免疫力と密接な関係にあります。
一般的に、体温が1℃下がると免疫力は約30%低下し、逆に1℃上がると一時的に最大5~6倍もアップすると言われています。
残暑の時期こそ、体を芯から温める習慣を意識しましょう。
まず、夏の間にシャワーだけで済ませていた方も、ぜひ湯船に浸かる習慣を取り戻してください。
ポイントは、38℃~40℃くらいのぬるめのお湯に、15分~20分ほどゆっくり浸かること。
これにより副交感神経が優位になり、心身ともにリラックスできるだけでなく、血行が促進されて内臓の働きも活発になります。
熱すぎるお湯はかえって体を緊張させてしまうので注意しましょう。
炭酸ガス系の入浴剤などを活用するのもおすすめです。
また、服装の工夫も大切です。
日中はまだ暑いですが、スーパーやオフィスなど、屋内は冷房が効いていて体が冷えやすい環境です。
カーディガンやストールなど、さっと羽織れるものを一枚持ち歩くようにしましょう。
特に「首」「手首」「足首」の三首は、皮膚の薄い部分で太い血管が通っているため、冷えやすいポイント。
靴下やレッグウォーマーで足首を温めるだけでも、体感温度は大きく変わりますよ。
心と体の相関関係 ストレスケアで免疫力を維持する
「病は気から」ということわざがあるように、心と体の健康は深くつながっています。
過度なストレスは自律神経のバランスを乱し、免疫細胞の働きを抑制してしまうことがわかっています。
残暑の疲れが出やすいこの時期は、意識的に自分をいたわる時間を作ることが、免疫力の維持につながります。
難しく考える必要はありません。
まずは、ゆっくりと深い呼吸を意識してみましょう。
目を閉じて、鼻からゆっくり息を吸い込み、口から長く吐き出す。
これを数回繰り返すだけでも、高ぶった神経が落ち着き、リラックス効果が得られます。
また、あなたが「心地よい」と感じる時間を作ることも立派なストレスケアです。
好きな音楽を聴く、お気に入りのアロマを焚く、面白い映画を見て思いっきり笑う、気の置けない友人とおしゃべりするなど、なんでも構いません。
「~しなければならない」という思考から離れて、心が喜ぶ時間を持つことが、結果的に免疫力を高めることにつながるのです。
頑張りすぎず、上手に心と体を休ませてあげましょう。
4. 今日から実践できる残暑対策のチェックリスト
夏の疲れがどっと出てくる残暑の季節。
何から手をつければ良いかわからない…と感じていませんか?
ここでは、これまでの内容を踏まえ、今日からすぐに始められる残暑バテ対策をチェックリスト形式でまとめました。
ご自身の生活習慣と照らし合わせながら、できることから取り入れてみてくださいね。
食事編:残暑バテ知らずの体を作る食生活
毎日の食事は、体調管理の基本です。
乱れがちな食生活を見直して、体の内側から元気になるためのチェックポイントを確認しましょう。
-
1日3食、なるべく決まった時間に食べていますか?
食事のリズムを整えることは、体内時計を正常に保ち、自律神経のバランスを整える第一歩です。
特に朝食は、心と体に活動のスイッチを入れる重要な役割を果たします。 -
発酵食品や食物繊維を意識して摂っていますか?
免疫細胞の約7割が集まる腸の環境を整える「腸活」は、残暑を乗り切る鍵となります。
納豆や味噌、ヨーグルトなどの発酵食品と、きのこや海藻、根菜などの食物繊維をバランス良く食事に取り入れましょう。 -
体を冷やしすぎていませんか?
冷たい飲み物や食べ物は、胃腸の働きを弱め、夏バテを悪化させる原因になります。
体を温める食材を意識的に選ぶことで、内臓の冷えを防ぎ、血行を促進しましょう。
体を温める食べ物・冷やす食べ物の選び方
食材には体を温める性質のものと、冷やす性質のものがあります。
下の表を参考に、日々の食材選びに役立ててみてください。
もちろん、体を冷やす食材を全く食べてはいけないわけではありません。
香味野菜やスパイスと組み合わせる、加熱調理するなど、工夫次第でバランスを取ることができます。
| 性質 | 特徴 | 食材の例 |
|---|---|---|
| 体を温める食べ物 | 寒い土地で採れるもの、冬が旬のもの、土の中で育つもの、色の濃いものなど | 生姜、にんにく、ねぎ、唐辛子、かぼちゃ、ごぼう、にんじん、玉ねぎ、納豆、味噌、羊肉、鶏肉、サバ、鮭 |
| 体を冷やす食べ物 | 暑い土地で採れるもの、夏が旬のもの、土の上で育つもの、水分の多いものなど | きゅうり、トマト、なす、レタス、スイカ、メロン、バナナ、豆腐、牛乳、豚肉、小麦 |
生活習慣編:自律神経を整える毎日のルーティン
日々の何気ない習慣が、自律神経のバランスに大きく影響します。
睡眠、運動、体温調節の3つのポイントから、生活習慣を見直してみましょう。
-
質の良い睡眠をとるための工夫をしていますか?
就寝1~2時間前には、38~40℃程度のぬるめのお湯に15分ほど浸かるのがおすすめです。
リラックス効果で副交感神経が優位になり、自然な眠りへと導きます。
また、寝る前のスマートフォンやパソコンの使用は、ブルーライトが脳を覚醒させてしまうため、控えましょう。 -
軽い運動を日常に取り入れていますか?
激しい運動は必要ありません。
朝の涼しい時間帯にウォーキングをしたり、寝る前に軽いストレッチをしたりするだけで、血行が促進され、自律神経が整いやすくなります。
エレベーターを階段にするなど、日常生活の中で少し動く意識を持つだけでも効果的です。 -
屋外と室内の温度差に対応できていますか?
冷房の効いた室内と暑い屋外の行き来は、体温調節機能を担う自律神経に大きな負担をかけます。
カーディガンやストールなどを一枚持ち歩き、こまめに着脱して急激な温度変化から体を守りましょう。
「首」「手首」「足首」の三首を冷やさないようにするのがポイントです。
心と体のセルフケア編:ストレスを上手に解消する工夫
心の疲れは、体の不調に直結します。
忙しい毎日の中でも、意識的に自分をいたわる時間を作ることが、免疫力を維持する上でとても大切です。
-
1日の中で、意識的にリラックスする時間を作っていますか?
好きな音楽を聴く、温かいハーブティーを飲む、アロマの香りを楽しむなど、5分でも10分でも構いません。
心から「心地よい」と感じる時間を持つことで、ストレスで緊張した心と体を解放してあげましょう。 -
ゆっくりと深い呼吸を意識していますか?
緊張や不安を感じたときは、呼吸が浅くなりがちです。
そんな時は、意識的にゆっくりと鼻から息を吸い、口から長く吐き出す腹式呼吸を試してみてください。
数回繰り返すだけで、乱れた自律神経が整い、気持ちが落ち着くのを感じられるはずです。
5. まとめ
厳しい残暑が続くと、なんだか体がだるい…なんてこと、ありませんか?
実はその不調、夏の疲れがどっと出る「残暑バテ」が原因かもしれません。
この記事でご紹介したように、残暑バテの鍵は自律神経と免疫力にあります。
食事や睡眠、軽い運動で自律神経のバランスを整え、腸活や体を温める習慣で免疫力を高めることが大切です。
まずは一つでもできることから始めて、夏の疲れをリセットし、元気に秋を迎えましょう。
商品カテゴリから探す