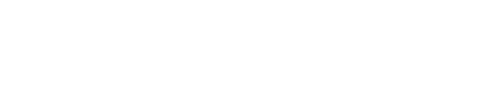健考彩都コラム
- TOP
- 【クーラー病とは】冷房病の症状や原因を解説|だるさや疲れは自律神経の異常がサイン

【クーラー病とは】冷房病の症状や原因を解説|だるさや疲れは自律神経の異常がサイン
2025年8月18日
夏の冷房が効いた部屋で、原因不明のだるさや疲れを感じていませんか?
その不調、もしかしたら「クーラー病(冷房病)」のサインかもしれません。
実はその正体は、室内外の温度差によって引き起こされる自律神経の乱れです。
この記事では、クーラー病の具体的な症状から原因、今日からできる簡単な対処法や予防策までを分かりやすく解説します。
つらい夏の不調を解消するヒントがここにあります。
- 1. クーラー病(冷房病)とは?その正体は自律神経の乱れ
- クーラー病は正式な病名ではありません
- クーラー病の正体は「自律神経の乱れ」
- クーラー病と夏バテ、何が違うの?
- 2. そのだるさや疲れはサインかも?クーラー病の主な症状セルフチェック
- 全身にあらわれる症状
- 身体的な症状
- 精神的な症状
- 3. なぜクーラー病になるの?主な原因は自律神経の異常
- 原因1 室内外の急激な温度差による自律神経の乱れ
- 原因2 体の冷えすぎによる血行不良
- 原因3 女性ホルモンのバランスの乱れ
- 4. 今日からできる!クーラー病のつらい症状を和らげる対処法
- 体を内側から温める食事と飲み物
- ぬるめのお湯で入浴し血行を促進する
- 簡単なストレッチで筋肉をほぐす
- 服装やグッズで体を冷えから守る工夫
- 5. クーラー病を繰り返さないための予防策
- クーラー(冷房)の適切な設定温度と使い方
- 適度な運動で汗をかく習慣をつける
- 生活リズムを整えて自律神経の働きをサポートする
- 6. 症状が改善しない場合は何科へ?病院受診の目安
- まずは内科や総合診療科に相談
- 女性特有の症状が気になる場合は婦人科も選択肢に
- 7. まとめ
1. クーラー病(冷房病)とは?その正体は自律神経の乱れ
夏の暑い日、涼しい室内に入るとホッとしますよね。
でも、その快適なはずのクーラーが原因で、「なんだか体がだるい」「頭が重い」「食欲がない」といった不調を感じたことはありませんか?
もしかしたら、それは「クーラー病(冷房病)」かもしれません。
クーラー病とは、冷房が効いた室内と暑い屋外との急激な温度差に体がついていけず、さまざまな体調不良を引き起こす状態のことです。
特に、私たちの体の調子を整える「自律神経」の働きが乱れることが、その大きな原因とされています。
クーラー病は正式な病名ではありません
実は、「クーラー病」や「冷房病」という名前は、医学的に正式に認められた病名ではありません。
これらは一般的に使われている俗称で、医学的には「自律神経失調症」の一種として捉えられています。
とはいえ、夏特有の体調不良として多くの人が経験しており、そのつらい症状は決して気のせいではないのです。
クーラー病の正体は「自律神経の乱れ」
私たちの体には、自分の意思とは関係なく、体温や血圧、心拍、消化などを24時間自動でコントロールしてくれる「自律神経」というシステムが備わっています。
自律神経には、体を活動的にする「交感神経(アクセル役)」と、体をリラックスさせる「副交感神経(ブレーキ役)」の2種類があり、この2つがバランスを取り合うことで健康を維持しています。
しかし、暑い屋外から寒い室内へ移動すると、体は急激な温度変化に対応しようと大忙しになります。
体温を一定に保つため、自律神経は血管を収縮させたり拡張させたりと、何度も指令を出すのです。
この急激な温度差(一般的に5℃以上)が何度も繰り返されると、自律神経の切り替えがうまくいかなくなり、バランスが崩れてしまいます。
この自律神経の混乱が、血行不良やホルモンバランスの乱れなどを引き起こし、結果として頭痛やだるさ、冷えといったクーラー病特有のさまざまな症状としてあらわれるのです。
クーラー病と夏バテ、何が違うの?
夏に起こる体調不良として「夏バテ」もよく知られていますが、クーラー病とは原因が少し異なります。
どちらも夏の不調ですが、原因と主な症状を理解することで、より適切な対策ができます。
その違いを下の表で確認してみましょう。
| クーラー病(冷房病) | 夏バテ | |
|---|---|---|
| 主な原因 | 室内外の急激な温度差による自律神経の乱れ、体の冷えすぎ | 高温多湿による発汗での水分・ミネラル不足、体温上昇、食欲不振による栄養不足 |
| 主な症状 | 体の冷え、だるさ、頭痛、肩こり、むくみ、腹痛、下痢など | 全身の倦怠感、疲労感、食欲不振、めまい、立ちくらみなど |
| 特徴 | 冷えに関する症状が目立つ。 冷房の効いた環境に長時間いる人に多い。 |
暑さそのものによる体力消耗が中心。 屋外での活動が多い人や汗をかきやすい人に多い。 |
もちろん、クーラー病と夏バテの症状が合併することもあります。
いずれにせよ、夏の不調の裏には、私たちの体が過酷な環境に適応しようと必死に頑張っているサインが隠されているのです。
2. そのだるさや疲れはサインかも?クーラー病の主な症状セルフチェック
「なんだか体が重い」「しっかり寝たはずなのに疲れがとれない」夏になると、そんな原因不明の不調を感じることはありませんか?
それは単なる夏バテではなく、クーラー病(冷房病)のサインかもしれません。
クーラー病は、正式な病名ではありませんが、冷房が効いた室内と暑い屋外との温度差によって自律神経が乱れ、心身にさまざまな不調を引き起こす状態を指します。
症状は人それぞれですが、ここでは代表的なものをリストアップしました。
ご自身の体調と照らし合わせながら、いくつ当てはまるかチェックしてみましょう。
| 症状の分類 | 具体的な症状の例 |
|---|---|
| 全身にあらわれる症状 |
|
| 身体的な症状 |
|
| 精神的な症状 |
|
もし、これらの項目に3つ以上当てはまるようなら、クーラー病の可能性があります。
それぞれの症状について、もう少し詳しく見ていきましょう。
全身にあらわれる症状
クーラー病の初期サインとして現れやすいのが、体全体に広がる不調です。
特定の部位が痛むわけではないため、「気のせいかな?」と見過ごしてしまいがちなので注意が必要です。
倦怠感やだるさ
「朝から体が鉛のように重い」「何もする気が起きない」といった倦怠感は、クーラー病の代表的な症状です。
これは、自律神経が体温調節にエネルギーを使いすぎてしまい、体がエネルギー不足に陥っていることが原因の一つ。
常に体が緊張状態にあるため、休んでも休んでもだるさが抜けにくくなります。
体の冷え
夏なのに「手足の指先が氷のように冷たい」「お腹を触るとひんやりする」といった症状も特徴的です。
クーラーの冷気に長時間さらされると、体は熱を逃がさないように血管を収縮させます。
この状態が続くと血行が悪くなり、体の末端まで温かい血液が届きにくくなるため、体の芯から冷えてしまう「内臓型冷え性」のような状態に陥ることがあります。
疲労感
十分な睡眠時間を確保しているにもかかわらず、日中に強い眠気に襲われたり、疲労感が抜けなかったりするのもサインの一つです。
私たちの体は、自律神経の働きによって無意識のうちに体温を一定に保っています。
しかし、室内外の激しい温度差に繰り返しさらされると、この体温調節機能が過剰に働き続け、知らず知らずのうちに疲労が蓄積してしまうのです。
身体的な症状
自律神経の乱れや血行不良は、体のさまざまな部位に具体的な痛みや不調として現れます。
頭痛や肩こり
体の冷えによる血行不良は、筋肉の緊張を引き起こします。
特に、首や肩周りの筋肉が硬直すると、頭部への血流が悪くなり、ズキズキとした痛みではなく、頭全体が締め付けられるような「緊張型頭痛」を誘発しやすくなります。
もともと肩こりに悩んでいる人は、夏になると症状が悪化する傾向があります。
腹痛や下痢
胃や腸といった消化器の働きは、自律神経によってコントロールされています。
体が冷えると、胃腸の血管も収縮して働きが鈍くなります。
その結果、消化不良を起こして食欲がなくなったり、腸のぜん動運動が乱れて便秘や下痢を繰り返したりすることがあります。
むくみや食欲不振
血行不良は、水分の排出にも影響を与えます。
体内の余分な水分や老廃物がうまく排出されず、特に重力の影響を受けやすい足を中心にむくみやすくなります。
また、前述の通り消化機能が低下することで、「胃がもたれる」「あまり食べたくない」といった食欲不振につながることも少なくありません。
精神的な症状
クーラー病の影響は、身体だけでなく心にも及びます。
見過ごされがちな精神的な不調も、実は自律神経の乱れが原因かもしれません。
イライラや集中力の低下
自律神経は、体の活動を司る「交感神経」と、リラックスを司る「副交感神経」の2つから成り立っています。
クーラーによる寒冷ストレスは、体を常に緊張状態(交感神経が優位な状態)に保ちます。
このバランスが崩れることで、些細なことでカッとなったり、逆に気分が落ち込んだりと、感情のコントロールが難しくなることがあります。
また、脳への血流低下が集中力や思考力の低下を招くこともあります。
寝つきが悪い・眠りが浅い
本来、夜になるとリラックスモードの副交感神経が優位になり、心身は休息状態に入ります。
しかし、自律神経が乱れていると、夜になっても交感神経が活発なままとなり、なかなか寝付けません。
眠れたとしても眠りが浅く、夜中に何度も目が覚めてしまうため、朝起きてもすっきりしないという悪循環に陥りがちです。
3. なぜクーラー病になるの?主な原因は自律神経の異常
夏の快適な室内環境が、なぜつらい体調不良を引き起こしてしまうのでしょうか。
その鍵を握っているのが、私たちの体をコントロールする「自律神経」です。
クーラー病は正式な病名ではなく、自律神経のバランスが崩れることで起こる、さまざまな症状の総称なのです。
ここでは、クーラー病を引き起こす3つの主な原因について、詳しく見ていきましょう。
原因1 室内外の急激な温度差による自律神経の乱れ
クーラー病の最大の原因は、なんといっても「室内外の急激な温度差」です。
猛暑の屋外から、キンキンに冷えた室内へ。
この環境の変化に、私たちの体は必死で適応しようとします。
私たちの体温は、自律神経によって常に一定に保たれています。
自律神経には、体を活動的にする「交感神経」と、リラックスさせる「副交感神経」の2種類があり、シーソーのようにバランスを取りながら働いています。
- 暑い場所(屋外):交感神経が働き、血管を広げて汗をかき、体内の熱を逃がそうとします。
- 寒い場所(室内):交感神経が働き、血管を収縮させて熱が逃げるのを防ぎ、体を震えさせて熱を作り出そうとします。
このように、暑い場所と寒い場所を行き来するたびに、自律神経は体温を調節するために大忙しになります。
一般的に、5℃以上の温度差が頻繁にある環境では、自律神経のスイッチングが追いつかなくなり、混乱してしまうのです。
この自律神経の酷使が、だるさや疲労感といった不調となってあらわれます。
原因2 体の冷えすぎによる血行不良
クーラーの冷たい風に直接当たり続けたり、長時間冷えた室内にいたりすると、体が芯から冷えてしまいます。
特に、足元は心臓から遠く、冷たい空気がたまりやすいため、冷えやすい部分です。
体が冷えると、私たちの体は熱を逃がさないように血管をキュッと収縮させます。
その結果、全身の血行が悪くなってしまうのです。
血液は、全身に酸素や栄養を届け、二酸化炭素や老廃物を回収するという大切な役割を担っています。
血行不良が起こると、筋肉には疲労物質がたまりやすくなり、肩こりや頭痛の原因になります。
また、胃腸などの内臓の働きも低下するため、食欲不振や下痢、便秘といった消化器系の症状を引き起こすことも少なくありません。
女性に多い「むくみ」も、血行不良が原因で起こる症状のひとつです。
原因3 女性ホルモンのバランスの乱れ
「クーラー病は女性に多い」と聞いたことはありませんか?
これには、女性ホルモンが深く関係しています。
実は、自律神経の働きをコントロールしている脳の「視床下部」という場所は、女性ホルモンの分泌を指令する場所でもあります。
そのため、自律神経と女性ホルモンは互いに影響しやすく、どちらかのバランスが崩れると、もう一方も乱れやすいという特徴があるのです。
月経や妊娠、更年期など、女性はライフステージを通じてホルモンバランスが大きく変動します。
このような時期は、ただでさえ自律神経が不安定になりがち。
そこにクーラーによる冷えや温度差のストレスが加わることで、クーラー病の症状がより強く出てしまうことがあります。
また、一般的に女性は男性に比べて筋肉量が少ない傾向にあります。
筋肉は体内で熱を生み出す大きな役割を担っているため、筋肉量が少ないと体が冷えやすく、クーラー病になりやすい要因のひとつと考えられています。
4. 今日からできる!クーラー病のつらい症状を和らげる対処法
クーラー病のつらい症状は、日々のちょっとした工夫で和らげることができます。
なんだか体がだるい、疲れが取れないと感じたら、ぜひ今日から試してみてください。
大切なのは、自律神経のバランスを整える「温める」「ほぐす」「守る」の3つのアプローチです。
体を内側から温める食事と飲み物
冷たい食べ物や飲み物は、胃腸を直接冷やし、体全体の冷えにつながります。
クーラー病の症状を感じるときは、体を内側から温める食材を意識的に取り入れることが、血行を促進し、弱った内臓の働きを助ける第一歩です。
夏だからといって冷たいものばかり摂るのではなく、温かい食事を1日1回は心がけましょう。
具体的にどのような食材を選べばよいか、下の表で確認してみましょう。
| 積極的に摂りたい体を温めるもの | なるべく控えたい体を冷やすもの |
|---|---|
| 食材:生姜、にんにく、ネギ、唐辛子などの薬味、ごぼう、にんじん、かぼちゃなどの根菜類、鶏肉、羊肉、サバなど | 食材:きゅうり、トマト、なすなどの夏野菜、バナナ、マンゴーなどの南国の果物、白砂糖を多く使ったお菓子 |
| 飲み物:白湯、生姜湯、ハーブティー(カモミール、ルイボスなど)、ココア、常温の水 | 飲み物:氷入りのジュース、アイスコーヒー、ビール、緑茶(玉露) |
| 調理法:加熱調理(煮る、焼く、蒸す)、スープや味噌汁、鍋物 | 調理法:生食(サラダなど) |
体を温める食材の代表格である生姜は、チューブタイプのものでも構いませんので、味噌汁や紅茶に少し加えるだけでも効果的です。
また、食事から摂るタンパク質は筋肉の材料となり、熱を生み出す基礎代謝を上げる助けになります。
ぬるめのお湯で入浴し血行を促進する
夏は暑いからとシャワーだけで済ませていませんか?
実は、クーラーで冷えた体をリセットするには、湯船にしっかり浸かることがとても大切です。
入浴には、全身の血行を促進するだけでなく、心身をリラックスさせて副交感神経を優位にし、乱れた自律神経のバランスを整える効果が期待できます。
ただし、入り方にはポイントがあります。
熱すぎるお湯はかえって交感神経を刺激してしまうため、38℃~40℃程度のぬるめのお湯に15分ほどゆっくり浸かるのがおすすめです。
額がじんわりと汗ばむくらいが目安です。
炭酸ガス系の入浴剤を使えば、血管を広げて血行をさらに促進してくれるので、疲労回復にもつながります。
寝る1~2時間前に入浴を済ませておくと、体温が自然に下がるタイミングでスムーズな入眠をサポートしてくれます。
簡単なストレッチで筋肉をほぐす
長時間同じ姿勢でいることが多いデスクワークでは、筋肉が硬直し、血行が悪くなりがちです。
特にクーラーの冷気は足元にたまりやすいため、下半身の冷えやむくみを引き起こします。
仕事の合間や寝る前に簡単なストレッチを取り入れて、凝り固まった筋肉をほぐし、血流を改善しましょう。
オフィスでも座ったままできる簡単ストレッチ
肩まわし・首のストレッチ:
椅子に座ったまま、両肩をゆっくりと前回し・後ろ回しを5回ずつ行います。
その後、首をゆっくり右に倒して5秒キープ、左に倒して5秒キープします。
肩こりや頭痛の緩和に効果的です。
足首のストレッチ:
椅子に浅く腰かけ、片足を少し前に出します。
つま先をゆっくりと上げ下げしたり、足首をぐるぐると回したりしましょう。
ふくらはぎの筋肉が刺激され、「第二の心臓」とも呼ばれるポンプ機能が働き、足元の血流改善に役立ちます。
自宅でできるリラックスストレッチ
ふくらはぎのストレッチ:
床に座って足を伸ばし、タオルをつま先にかけて手前にゆっくりと引っ張ります。
ふくらはぎが心地よく伸びるのを感じながら20秒ほどキープしましょう。
呼吸は止めず、自然な呼吸を続けてください。
ストレッチは、痛みを感じない「気持ちいい」範囲で行うことが大切です。
無理なく続けることで、筋肉の柔軟性を高め、冷えにくい体づくりにつながります。
服装やグッズで体を冷えから守る工夫
自分自身で温度調節が難しいオフィスなどでは、服装や便利グッズを上手に活用して、クーラーの冷気から体を守る工夫が欠かせません。
特に「首」「手首」「足首」の三首は、皮膚のすぐ下を太い血管が通っているため、ここを冷やすと体全体が冷えやすくなります。
逆に、この三首を温めることで効率よく全身を温めることができます。
カーディガンやストールなどの羽織りものを一枚常備しておくのは基本中の基本です。
その他にも、以下のようなアイテムを取り入れてみましょう。
- レッグウォーマーや靴下:冷えやすい足元を直接温めます。
夏用の薄手のシルク素材などは、蒸れにくく快適です。 - 腹巻き:お腹周りを温めることで内臓の冷えを防ぎ、胃腸の不調を和らげる効果が期待できます。
- ひざ掛け:デスクワーク中に下半身をすっぽり覆うことで、足元にたまる冷気をシャットアウトします。
- 温かい飲み物を入れるタンブラー:いつでも温かい飲み物が飲めるようにしておくと、手軽に体を内側から温められます。
また、クーラーの風が直接体に当たらないように、風向きを調整したり、サーキュレーターで空気を循環させたりするのも有効な対策です。
少しの工夫で、クーラーによる体への負担を大きく減らすことができます。
5. クーラー病を繰り返さないための予防策
つらい症状が出てから慌てて対処するのも大切ですが、もっと重要なのは、そもそもクーラー病にならないための体づくりと生活習慣です。
一度なってしまうと繰り返しやすいクーラー病。
だからこそ、夏を元気に乗り切るための「予防」という視点が欠かせません。
ここでは、今日からすぐに始められる3つの予防策をご紹介します。
少し意識を変えるだけで、体はきっと応えてくれますよ。
クーラー(冷房)の適切な設定温度と使い方
夏の快適な生活に欠かせないクーラーですが、使い方を間違えると自律神経の乱れを招く最大の原因になってしまいます。
体を冷やしすぎず、快適に過ごすための上手な使い方をマスターしましょう。
最も大切なポイントは、室内と屋外の温度差を5℃以内に保つことです。
例えば、外の気温が33℃であれば、設定温度は28℃が目安となります。
温度差が激しいと、体温を調節しようと自律神経が過剰に働き、疲弊してしまうのです。
「28℃では暑い」と感じるかもしれませんが、扇風機やサーキュレーターを併用して空気を循環させると、体感温度が下がり快適に過ごせます。
また、クーラーの風が直接体に当たるのも避けたいところ。
風が長時間当たり続けると、その部分だけが急激に冷えて血行不良の原因となります。
風向きは常に上向きに設定し、スイング機能を活用して、冷たい空気が部屋全体を優しく循環するように工夫しましょう。
湿度が高い日本の夏では、温度を下げる「冷房」だけでなく、「除湿(ドライ)」機能を活用するのも効果的です。
湿度が下がるだけで体感温度はぐっと下がり、設定温度をそこまで下げなくても快適に感じられます。
特に注意したいのが就寝時です。
寝ている間は体温が下がるため、クーラーをつけたまま寝ると体を冷やしすぎてしまいます。
就寝タイマーを活用し、眠りについてから1〜2時間後には切れるように設定するのがおすすめです。
| 項目 | 具体的な工夫 |
|---|---|
| 設定温度 | 外気温との差を5℃以内に保つ(28℃が目安) |
| 風向き | 直接体に当てず、上向きやスイング機能を活用する |
| 併用アイテム | 扇風機やサーキュレーターで空気を循環させ、体感温度を下げる |
| 機能の使い分け | 湿度が高い日は「除湿(ドライ)」機能を活用する |
| 就寝時 | タイマー機能を使い、1〜2時間で切れるように設定する |
適度な運動で汗をかく習慣をつける
「夏は暑くて動きたくない…」と感じるかもしれませんが、実は適度な運動こそがクーラー病の予防に繋がります。
普段から汗をかく習慣がないと、汗腺の機能が低下し、いざという時にうまく汗をかいて体温を調節することができなくなってしまいます。
これが、自律神経の負担を増やす一因となるのです。
なにも、ハードなトレーニングをする必要はありません。
大切なのは、無理なく楽しみながら続けられることです。
まずは、以下のような軽い運動から始めてみませんか?
- ウォーキング:少し早歩きを意識して20〜30分歩くだけでも、全身の血行が良くなります。
涼しい朝や夕方の時間帯がおすすめです。 - ヨガ・ストレッチ:深い呼吸を意識しながら筋肉をゆっくり伸ばすことで、心身ともにリラックスでき、自律神経のバランスを整える効果が期待できます。
- 水中ウォーキング:プールの中なら体に負担をかけずに運動できます。
水の抵抗で効率よく筋肉を使い、浮力でリラックス効果も得られます。
日常生活の中でも、エスカレーターを階段に変えたり、一駅手前で降りて歩いてみたりと、少し意識するだけで運動量を増やすことができます。
心地よく汗をかく習慣を身につけて、環境の変化に強い体を作りましょう。
生活リズムを整えて自律神経の働きをサポートする
クーラー病の根本的な原因である自律神経の乱れは、日々の生活リズムと深く関わっています。
不規則な生活は、自律神経のバランスを崩す大きな要因。
夏バテにも負けない体を作るために、毎日の暮らし方を見直してみましょう。
規則正しい睡眠で体内時計をリセット
自律神経を整える上で、質の良い睡眠は不可欠です。
毎日できるだけ同じ時間に寝て、同じ時間に起きることを心がけましょう。
休日でも、寝坊は1〜2時間程度にとどめるのが理想です。
規則正しい睡眠リズムは、体の体内時計を正常に保ち、自律神経の切り替えをスムーズにしてくれます。
朝起きたらカーテンを開けて太陽の光を浴びる習慣をつけると、心と体を活動モードに切り替えるスイッチが入り、より効果的です。
1日3食、バランスの取れた食事を心がける
暑いと食欲が落ちて、そうめんや冷たいものばかり食べてしまいがちではありませんか?
しかし、栄養バランスの偏りは自律神経の乱れに直結します。
特に、1日の活動を始めるためのエネルギー源となる朝食は、抜かずにしっかり摂りましょう。
体を温めるスープや味噌汁などを一品加えるだけでも、体の中から調子を整えることができます。
ビタミンB群やミネラル、タンパク質などを意識して、バランス良く食べることが大切です。
自分なりのリラックス方法を見つける
ストレスは自律神経の天敵です。
仕事や人間関係などで知らず知らずのうちに溜まったストレスは、交感神経を優位にさせ、心身の緊張状態を長引かせます。
1日の終わりに、心からリラックスできる時間を作りましょう。
ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる、好きな音楽を聴く、アロマを焚く、軽い読書をするなど、あなたに合った方法で構いません。
意識的に副交感神経を優位にさせる時間を持つことで、自律神経のバランスが整いやすくなります。
6. 症状が改善しない場合は何科へ?病院受診の目安
セルフケアを試してみても、クーラー病(冷房病)のつらい症状がなかなか改善しないと、「このまま放っておいて大丈夫かな?」「もしかして他の病気かも?」と不安になってしまいますよね。
そんなときは、我慢せずに専門家である医師に相談することが大切です。
しかし、いざ病院へ行こうと思っても、どの診療科を受診すればよいのか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。
ここでは、クーラー病が疑われる場合に受診すべき診療科の目安と、診察時に医師に伝えるとよいポイントを解説します。
「たかがクーラー病」と自己判断せず、適切な医療機関を受診することで、症状の早期改善や、背後に隠れた別の病気の発見につながることもあります。
まずは内科や総合診療科に相談
「どの科に行けばいいか全くわからない」という場合は、まず内科、あるいは総合診療科を受診するのが最も一般的です。
クーラー病の症状は、頭痛、倦怠感、腹痛、食欲不振など非常に多岐にわたるため、体全体を総合的に診てもらえる内科や総合診療科が最初の窓口として適しています。
診察では、症状が自律神経の乱れによるものなのか、あるいはウイルス性の風邪や他の内臓疾患など、別の原因がないかを診断してくれます。
必要に応じて血液検査などを行い、隠れた病気がないかを確認した上で、症状を和らげる薬(例えば、血行を促進する薬や漢方薬など)を処方してもらえたり、生活習慣に関する具体的なアドバイスを受けたりすることができます。
もし、より専門的な治療が必要だと判断された場合は、適切な診療科を紹介してもらえるため、安心して相談できます。
受診の際は、以下の点をまとめておくと、医師に症状が伝わりやすくなり、スムーズな診断につながります。
- いつからどのような症状があるか(例:7月上旬から、一日中体がだるい)
- 特にどの症状が一番つらいか(例:めまいと立ちくらみがひどい)
- どのような状況で症状が強くなるか(例:職場の冷房が効いた部屋にいると悪化する)
- 自分で試した対処法と、その効果(例:温かい飲み物を飲んだが、あまり変わらない)
- 他に持病があるか、服用中の薬はあるか
女性特有の症状が気になる場合は婦人科も選択肢に
クーラー病の原因の一つに、女性ホルモンのバランスの乱れが関係していることがあります。
特に、生理周期に伴って症状が変化したり、ほてりやのぼせ、イライラといった更年期障害に似た症状が強く出たりする場合は、婦人科に相談するのも有効な選択肢です。
女性の体は年代によってホルモンバランスが大きく変動するため、冷えがその乱れを助長してしまうことがあります。
婦人科では、ホルモンバランスの観点から診察を行い、必要であればホルモン補充療法や漢方薬の処方など、専門的なアプローチで治療を進めることができます。
月経前症候群(PMS)や更年期障害の症状が、冷房によって悪化している可能性も考えられるため、気になる方は一度相談してみることをおすすめします。
症状別・診療科の目安一覧
ご自身の症状に合わせて、どの診療科が適しているか、以下の表も参考にしてみてください。
| 診療科 | こんな症状・こんな人におすすめ |
|---|---|
| 内科・総合診療科 | 原因がはっきりしない全身の倦怠感、だるさ、微熱、頭痛、腹痛、下痢など、症状が多岐にわたる場合。 まずは全体的に診てほしい方。 |
| 婦人科 | 生理不順や重い生理痛、PMS(月経前症候群)の悪化、ほてり、のぼせ、イライラなど、女性ホルモンの乱れが疑われる症状がある方。 |
| 整形外科 | 他の症状よりも、肩こり、首のこり、腰痛、手足のしびれなどが特にひどい場合。 血行不良による筋肉の緊張が原因と考えられるケース。 |
| 心療内科・精神科 | 体の症状に加えて、気分の落ち込み、不安感、不眠、集中力の低下といった精神的な不調が強く、日常生活に支障が出ている場合。 自律神経失調症の治療も専門としています。 |
いずれの診療科を受診するにしても、大切なのは一人で抱え込まずに専門家の助けを求めることです。
つらい症状が続く場合は、ためらわずに医療機関の扉をたたきましょう。
7. まとめ
夏のオフィスや電車で感じる、原因不明のだるさや頭痛。
もしかしたら、それは「クーラー病」のサインかもしれません。
クーラー病の正体は、室内外の急激な温度差によって、体温を調節する自律神経が乱れてしまうこと。
この記事でご紹介したように、体を温める食事や入浴、服装の工夫など、今日からできる簡単な対策で症状は和らげられます。
つらい不調を我慢せず、小さな工夫を積み重ねて、快適な夏を過ごしましょう。
商品カテゴリから探す