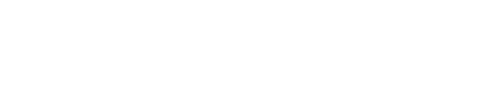健考彩都コラム
- TOP
- 知らないと危険!夏の感染症|人が集まるプールやレジャーの意外なリスクと効果的な予防法

知らないと危険!夏の感染症|人が集まるプールやレジャーの意外なリスクと効果的な予防法
2025年7月29日
夏休みを楽しみにしているあなた、実は夏は感染症が増える季節だということをご存知ですか?
プールや海水浴、キャンプにBBQ、お祭りなど、人が集まる楽しいイベントが目白押しの夏。
でも、高温多湿の環境と人混みが重なることで、手足口病やプール熱、食中毒など様々な感染症のリスクが高まってしまうんです。
この記事では、夏に流行しやすい感染症の特徴と、シーン別の具体的な予防法をわかりやすくお伝えします。
正しい知識を身につけて、安心して夏を満喫しましょう。
- 1. 夏はなぜ感染症が増えるの?高温多湿が引き起こすリスク
- 気温と湿度が感染症リスクを高める3つの理由
- 夏特有の生活習慣が感染リスクを上げている
- 体の抵抗力が落ちる「夏バテ」も要因に
- 人が集まる夏のイベントがもたらす集団感染リスク
- 2. 【症状別】夏に注意すべき代表的な感染症とその特徴
- 手足口病 主な症状と感染経路
- ヘルパンギーナ 突然の高熱と喉の痛みが特徴
- プール熱(咽頭結膜熱) プール以外でも感染するリスク
- 感染性胃腸炎(食中毒) O-157やカンピロバクターに注意
- その他に注意したい夏の感染症
- 3. 人が集まる場所は危険がいっぱい シーン別の感染症リスクと予防法
- プールや海水浴で注意すべき感染症と予防法
- キャンプやBBQの食中毒リスクと予防法
- お祭りやイベントなど人が集まる場所での感染リスクと予防法
- 4. 今日からできる!夏の感染症を防ぐための基本的な予防法
- 基本のきほん 正しい手洗いと手指消毒
- 夏バテを防ぎ免疫力を高める生活習慣
- 脱水症状は感染症のリスクを高める こまめな水分補給を
- 5. もし夏風邪や感染症にかかってしまったら?家庭での対処法と受診の目安
- 安静と水分補給が第一 家庭でのケア方法
- こんな症状が出たらすぐ病院へ 受診の目安
- 6. まとめ
1. 夏はなぜ感染症が増えるの?高温多湿が引き起こすリスク
夏休みや連休で楽しい計画を立てている方も多いのではないでしょうか?
でも、実は夏は感染症が増えやすい季節なんです。
「暑いから菌も死んでしまうのでは?」と思うかもしれませんが、高温多湿の環境は、むしろ多くの細菌やウイルスにとって繁殖しやすい条件になってしまいます。
気温と湿度が感染症リスクを高める3つの理由
日本の夏は、気温30度以上、湿度70%を超える日が続きます。
この環境が感染症を広げやすくする理由を見ていきましょう。
細菌やウイルスが活発になる温度帯
多くの病原体は、25~37度の温度帯で最も活発に増殖します。
特に食中毒を引き起こす細菌は、この温度帯で爆発的に増えることがあります。
例えば、黄色ブドウ球菌は30~37度で2~3時間ごとに倍増し、朝作ったお弁当が昼には危険な状態になることも。
湿度が高いと飛沫が遠くまで飛ぶ
湿度が高いと、咳やくしゃみで出る飛沫の水分が蒸発しにくくなります。
その結果、ウイルスを含んだ飛沫が空気中に長く漂い、感染範囲が広がりやすくなるのです。
エアコンの効いた室内でも、人が多い場所では注意が必要です。
汗や皮脂が病原体の温床に
暑さで汗をかくと、皮膚表面の環境が変化します。
汗に含まれる塩分や皮脂は細菌の栄養源となり、とびひなどの皮膚感染症が起こりやすい状態を作ってしまいます。
夏特有の生活習慣が感染リスクを上げている
気候だけでなく、夏ならではの生活スタイルも感染症を広げる要因になっています。
| 夏の生活習慣 | 感染リスクが高まる理由 | 特に注意すべき感染症 |
|---|---|---|
| エアコンの使用 | 空気が乾燥し、喉や鼻の粘膜の防御機能が低下 | 夏風邪、咽頭炎 |
| 冷たい飲食物の摂取 | 胃腸の働きが弱まり、免疫力が低下 | 感染性胃腸炎 |
| 薄着・素足 | 皮膚が露出し、接触感染のリスクが増加 | とびひ、水虫 |
| プールや海水浴 | 多くの人と水を共有、目や耳に水が入りやすい | プール熱、外耳炎 |
体の抵抗力が落ちる「夏バテ」も要因に
暑さによる疲労や食欲不振、睡眠不足...これらはすべて免疫力を低下させ、感染症にかかりやすい体を作ってしまいます。
特に、室内外の温度差による自律神経の乱れは、体の防御システムを弱めてしまう大きな要因です。
「暑いから仕方ない」と諦めてしまいがちですが、夏バテを防ぐことは感染症予防の第一歩。
規則正しい生活リズムを保ち、バランスの良い食事を心がけることが大切です。
人が集まる夏のイベントがもたらす集団感染リスク
夏祭り、花火大会、野外フェス...夏は人が集まるイベントが目白押しです。
楽しいイベントですが、密集した環境では感染症が一気に広がるリスクがあります。
2019年の調査では、夏季の大規模イベント後に感染性胃腸炎の患者が例年の3倍に増えた地域もありました。
屋台の食べ物による食中毒だけでなく、トイレの共用や、汗をかいた状態での接触も感染経路となっています。
このように、夏の感染症リスクは気候条件と私たちの行動パターンが複雑に絡み合って生まれています。
でも心配しすぎる必要はありません。
リスクを知って適切な対策をとれば、楽しい夏を健康に過ごすことができるのです。
2. 【症状別】夏に注意すべき代表的な感染症とその特徴
夏休みが始まると、子どもも大人もレジャーに出かける機会が増えますよね。
でも、楽しい時間を過ごしている間に、思わぬ感染症にかかってしまうことがあります。
「なんだか体調が悪いな...」と思ったら、実は夏特有の感染症だったということも。
ここでは、夏に流行しやすい代表的な感染症について、その症状や特徴を詳しく見ていきましょう。
手足口病 主な症状と感染経路
保育園や幼稚園でよく「手足口病が流行っています」というお知らせを見かけたことはありませんか?
手足口病は、主に5歳以下の子どもに多く見られる夏の代表的な感染症です。
病名の通り、手のひら、足の裏、口の中に水ぶくれのような発疹ができるのが特徴です。
最初は「あれ?口内炎かな?」と思うような症状から始まることも多く、その後手足に発疹が広がっていきます。
発熱は38度以下の微熱程度で、高熱になることは少ないのですが、口の中の発疹が痛くて食事が取りにくくなることがあります。
| 感染経路 | 詳細 |
|---|---|
| 飛沫感染 | 咳やくしゃみによってウイルスが飛び散り感染 |
| 接触感染 | ウイルスが付着した手やタオルなどを介して感染 |
| 糞口感染 | 便に排出されたウイルスが手などを介して口に入ることで感染 |
特に注意したいのは、症状が治まった後も2〜4週間は便からウイルスが排出されることです。
「もう元気になったから大丈夫」と油断せず、トイレの後の手洗いは特に念入りに行いましょう。
ヘルパンギーナ 突然の高熱と喉の痛みが特徴
「昨日まで元気だったのに、急に39度以上の熱が出た!」そんな経験はありませんか?
ヘルパンギーナは、突然の高熱で始まることが多い夏風邪の一種です。
最大の特徴は、のどの奥に小さな水ぶくれができることです。
この水ぶくれが破れると潰瘍になり、とても痛みます。
「のどが痛くて水も飲めない」という状態になることもあり、特に小さなお子さんの場合は脱水症状に注意が必要です。
ヘルパンギーナはエンテロウイルスが原因で、6月から8月にかけて流行のピークを迎えます。
潜伏期間は2〜4日程度で、発熱は2〜4日で下がることがほとんどです。
ただし、のどの痛みはもう少し長く続くことがあります。
プール熱(咽頭結膜熱) プール以外でも感染するリスク
「プール熱」という名前から、プールでしか感染しないと思っていませんか?
実は、プール熱はプール以外の場所でも十分に感染する可能性があるんです。
正式名称は「咽頭結膜熱」といい、アデノウイルスが原因で起こります。
主な症状は以下の3つです。
| 主な症状 | 特徴 |
|---|---|
| 高熱 | 39〜40度の高熱が4〜5日続く |
| のどの痛み | のどが真っ赤に腫れ、強い痛みを伴う |
| 結膜炎 | 目が充血し、目やにが出る |
プールで感染しやすいのは、塩素消毒が不十分な場合にウイルスが残存しやすいためです。
しかし、タオルの共有や、感染者との接触によっても感染するため、家庭内での二次感染にも注意が必要です。
感染性胃腸炎(食中毒) O-157やカンピロバクターに注意
夏のBBQやキャンプ、楽しいですよね。
でも、「お腹が痛い...」「吐き気がする...」なんて症状が出たら、それは食中毒かもしれません。
夏は気温が高く、細菌が繁殖しやすい環境になるため、食中毒のリスクが格段に上がります。
特に注意したい原因菌をまとめました。
| 原因菌 | 主な原因食品 | 潜伏期間 | 主な症状 |
|---|---|---|---|
| O-157(腸管出血性大腸菌) | 生肉、生野菜、井戸水 | 3〜8日 | 激しい腹痛、血便、発熱 |
| カンピロバクター | 鶏肉、生乳、生水 | 2〜5日 | 下痢、腹痛、発熱、頭痛 |
| サルモネラ菌 | 卵、肉類、ペット | 6〜72時間 | 腹痛、下痢、発熱、嘔吐 |
| 黄色ブドウ球菌 | おにぎり、弁当、調理済み食品 | 30分〜6時間 | 激しい嘔吐、下痢 |
O-157は特に重症化しやすく、溶血性尿毒症症候群(HUS)を引き起こすことがあるため、血便が出た場合はすぐに医療機関を受診しましょう。
カンピロバクターは鶏肉の生食や加熱不足が原因となることが多く、「新鮮だから大丈夫」という考えは危険です。
その他に注意したい夏の感染症
ここまで紹介した感染症以外にも、夏に流行しやすい感染症があります。
「虫刺されかな?」「目が赤いだけだから大丈夫」と軽く考えていると、実は感染症だったということも。
それぞれの特徴を知っておきましょう。
とびひ(伝染性膿痂疹)
虫刺されをかきむしったところから始まることが多いとびひ。
正式には「伝染性膿痂疹」といい、黄色ブドウ球菌や溶連菌が原因で起こる皮膚の感染症です。
最初は小さな水ぶくれから始まりますが、これが破れると中の液体が周りの皮膚について、まるで「火事が飛び火する」ように広がっていきます。
だから「とびひ」と呼ばれるんですね。
特に夏は汗をかきやすく、皮膚が不潔になりがちなので注意が必要です。
とびひの特徴として、かゆみが強く、つい触ってしまうことで他の部位や他の人にうつしやすいことがあります。
プールなどでは感染を広げる可能性があるため、完治するまでは控えましょう。
はやり目(流行性角結膜炎)
「朝起きたら目が真っ赤!目やにで目が開かない!」こんな症状が出たら、はやり目の可能性があります。
正式名称は「流行性角結膜炎」で、アデノウイルスが原因で起こる目の感染症です。
プール熱と同じアデノウイルスが原因ですが、はやり目の場合は目の症状が中心で、発熱はあっても軽度です。
感染力が非常に強く、感染者が目を触った手でドアノブなどを触ると、そこから他の人に感染することがあります。
両目に症状が出ることが多いのですが、片目から始まって数日後にもう片方の目にも症状が出るパターンもあります。
完治までに2〜3週間かかることもあり、その間は学校や職場を休む必要があることも覚えておきましょう。
3. 人が集まる場所は危険がいっぱい シーン別の感染症リスクと予防法
夏休みになると、プールや海、キャンプ場など、楽しいレジャー施設に多くの人が集まりますよね。
でも実は、人が密集する場所ほど感染症のリスクが高まることをご存知でしょうか?
楽しい思い出作りが、思わぬ病気で台無しになってしまうことも。
ここでは、夏のレジャーシーン別に潜む感染症リスクと、具体的な予防法をご紹介します。
プールや海水浴で注意すべき感染症と予防法
プールや海は夏の定番レジャースポットですが、水を介して感染する病気が意外と多いんです。
特に子どもたちが集まる市民プールでは、プール熱(咽頭結膜熱)やはやり目(流行性角結膜炎)の集団感染が毎年のように報告されています。
| 感染症名 | 主な症状 | 感染経路 |
|---|---|---|
| プール熱(咽頭結膜熱) | 高熱、喉の痛み、目の充血 | プールの水、タオルの共有 |
| はやり目(流行性角結膜炎) | 目の充血、目やに、涙が止まらない | 手指を介した接触感染 |
| 外耳炎(プール耳) | 耳の痛み、かゆみ、耳だれ | 汚染された水が耳に入る |
プール前後のシャワーを徹底する
プールに入る前のシャワーって、面倒に感じるかもしれません。
でも、プール前のシャワーは他の人への感染予防、プール後のシャワーは自分への感染予防という大切な役割があるんです。
特にプール後は、塩素で消毒されているとはいえ、目や耳、鼻の中に入った水をしっかり洗い流すことが重要です。
シャワーを浴びる際は、石鹸を使って全身をくまなく洗い、特に手指は念入りに洗いましょう。
タオルやゴーグルの共有は避ける
家族や友達同士でも、タオルやゴーグルの共有は感染症の温床になります。
はやり目の原因となるアデノウイルスは、タオルに付着すると数日間も感染力を保つことがあるんです。
プールバッグには必ず自分専用のタオルを2枚以上持参し、顔を拭くタオルと体を拭くタオルを分けるのがおすすめです。
ゴーグルも使用後は水道水でよく洗い、乾燥させてから保管しましょう。
キャンプやBBQの食中毒リスクと予防法
屋外での調理は楽しいイベントですが、高温多湿の環境下では細菌が急速に繁殖するため、食中毒のリスクが格段に上がります。
特に生肉の取り扱いには細心の注意が必要です。
生肉の取り扱いに注意 食材の管理方法
BBQでよく起こる食中毒の原因は、生肉に付着した病原菌が他の食材に移ることです。
生肉を触った箸やトングで、そのまま野菜や焼けた肉を触るのは絶対にNGです。
| 食材 | 保管温度 | 注意点 |
|---|---|---|
| 生肉・生魚 | 10℃以下 | クーラーボックスの一番下に置く |
| 野菜・果物 | 15℃以下 | 生肉とは別の容器で保管 |
| 調理済み食品 | 10℃以下 | 2時間以内に食べきる |
また、まな板も肉用と野菜用で必ず分け、使用後はすぐに洗剤で洗いましょう。
手指も生肉を触るたびにウェットティッシュで拭き、調理が終わったら石鹸でしっかり洗うことが大切です。
虫刺されから始まる感染症にも警戒を
キャンプ場では、蚊やブヨ、マダニなどの虫刺されにも注意が必要です。
虫刺されをかきむしると、そこから細菌が入って「とびひ」になることもあります。
虫除けスプレーは2〜3時間おきに塗り直し、長袖・長ズボンで肌の露出を減らしましょう。
もし刺されてしまったら、かゆみ止めを塗って、爪でかかないようにガーゼなどで保護することが大切です。
お祭りやイベントなど人が集まる場所での感染リスクと予防法
夏祭りや花火大会、野外フェスなど、大勢の人が集まるイベントも感染症のリスクが高い場所です。
人混みでは1メートル以内に感染者がいる可能性が高く、飛沫感染のリスクが急上昇します。
飛沫感染と接触感染への対策
人混みでの感染予防には、次のような対策が効果的です。
まず、こまめな手指消毒と、顔を触らない習慣を身につけましょう。
屋台の食べ物を素手で食べる前には、必ずアルコール消毒液で手を清潔にすることが大切です。
また、人が密集する場所では、できるだけ他の人との距離を保ち、咳やくしゃみをしている人からは離れるようにしましょう。
帰宅後は、すぐに手洗い・うがいをして、着ていた服も洗濯することをおすすめします。
楽しい夏のイベントを満喫するためにも、これらの予防法を実践して、感染症から身を守りましょう。
少しの心がけで、安全で楽しい夏の思い出が作れるはずです。
4. 今日からできる!夏の感染症を防ぐための基本的な予防法
夏のレジャーシーズン、楽しい思い出を作りたいのに感染症で台無しに...なんてことは避けたいですよね。
実は、ちょっとした心がけで感染リスクは大幅に減らせるんです。
今日から実践できる、効果的な予防法をご紹介します。
基本のきほん 正しい手洗いと手指消毒
「手洗いなんて当たり前」と思うかもしれませんが、夏は汗や日焼け止めで手が汚れやすく、病原体が付着しやすい季節です。
プールの更衣室のドアノブ、BBQの調理器具、お祭りの屋台...どこにでも感染リスクは潜んでいます。
| タイミング | 手洗いのポイント | 注意事項 |
|---|---|---|
| 外出から帰った時 | 指の間、爪の周り、手首まで30秒以上 | 玄関にアルコール消毒液を置くと習慣化しやすい |
| 食事の前後 | 石けんをよく泡立てて洗う | BBQなど屋外では携帯用消毒液が便利 |
| トイレの後 | 特に親指の付け根を念入りに | ペーパータオルで蛇口を閉めると二次感染予防に |
| プール・海の後 | 塩素や海水をしっかり洗い流す | 目や鼻の周りも優しく洗浄 |
アルコール消毒液を使う場合は、手が完全に乾くまでしっかりすり込むことが大切です。
濡れた手では効果が半減してしまいます。
夏バテを防ぎ免疫力を高める生活習慣
暑さで体力が奪われやすい夏。
実は、夏バテで免疫力が低下すると、普段なら跳ね返せる病原体にも感染しやすくなってしまうんです。
まず大切なのは、規則正しい生活リズムです。
夏休みだからといって夜更かしが続くと、体内時計が乱れて免疫機能も低下します。
できるだけ毎日同じ時間に起床・就寝を心がけましょう。
| 免疫力を高める習慣 | 具体的な方法 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 質の良い睡眠 | エアコンを27~28度に設定、就寝1時間前はスマホを控える | 成長ホルモンの分泌促進、免疫細胞の活性化 |
| バランスの良い食事 | 夏野菜(トマト、きゅうり、なす)を積極的に摂取 | ビタミン・ミネラル補給、抗酸化作用 |
| 適度な運動 | 朝夕の涼しい時間に20~30分のウォーキング | 血行促進、ストレス解消 |
| 体温調節 | 冷房の効いた場所では薄手の羽織りものを | 自律神経の安定、体調維持 |
特に注意したいのが、冷たいものの摂りすぎによる胃腸の冷えです。
アイスクリームや冷たい飲み物は美味しいですが、胃腸が冷えると消化機能が低下し、結果的に免疫力も下がってしまいます。
脱水症状は感染症のリスクを高める こまめな水分補給を
「喉が渇いてから飲む」では遅いんです。
体内の水分が2%失われただけで、免疫機能は著しく低下することがわかっています。
脱水状態では、粘膜が乾燥して病原体が侵入しやすくなり、感染症にかかりやすくなってしまいます。
理想的な水分補給のタイミングは、起床時、食事の30分前、入浴前後、就寝前です。
特に外出時は、15~20分おきに少量ずつ飲むことを心がけましょう。
| シーン | 推奨する飲み物 | 1回の摂取量目安 |
|---|---|---|
| 日常生活 | 水、麦茶、ルイボスティー | コップ1杯(200ml) |
| スポーツ・屋外活動時 | スポーツドリンク(2~3倍に薄めたもの) | 100~150ml |
| プール・海水浴 | 水または薄めたスポーツドリンク | 30分ごとに100ml |
| 発熱・下痢時 | 経口補水液(OS-1など) | 医師の指示に従う |
カフェインやアルコールは利尿作用があるため、水分補給には適しません。
また、一度に大量の水を飲むと、体内の電解質バランスが崩れて「水中毒」になる危険性もあるので、少量をこまめに摂ることが大切です。
これらの予防法は、どれも今すぐ始められる簡単なものばかり。
でも、その効果は絶大です。
楽しい夏の思い出を守るために、ぜひ今日から実践してみてくださいね。
5. もし夏風邪や感染症にかかってしまったら?家庭での対処法と受診の目安
夏の暑さで体力が落ちているときに感染症にかかってしまうと、思った以上に症状が長引いてしまうことがあります。
「ちょっと体調が悪いかな」と思ったら、早めの対処が肝心です。
でも、すぐに病院に行くべきなのか、家で様子を見ていいのか、判断に迷うこともありますよね。
ここでは、夏の感染症にかかってしまったときの適切な対処法と、病院を受診すべきタイミングについて詳しく解説します。
安静と水分補給が第一 家庭でのケア方法
夏の感染症にかかったら、まず大切なのは十分な休養と水分補給です。
暑さで汗をかきやすい夏は、発熱によってさらに脱水症状を起こしやすくなります。
体を休めるときは、エアコンを適切に使って室温を26~28度に保ちましょう。
冷やしすぎは逆効果ですが、暑すぎる環境では体力の回復が遅れてしまいます。
水分補給については、以下の点に注意してください:
| 飲み物の種類 | おすすめ度 | 注意点 |
|---|---|---|
| 経口補水液(OS-1など) | ◎ | 塩分と糖分のバランスが良く、吸収が早い |
| スポーツドリンク | ○ | 糖分が多いので薄めて飲むのがおすすめ |
| 麦茶・ほうじ茶 | ○ | カフェインが少なく、体に優しい |
| 冷たい水 | △ | 一気に飲むと胃腸に負担がかかる |
| 炭酸飲料・ジュース | × | 糖分が多く、胃腸への刺激も強い |
食事については、無理に食べる必要はありませんが、食欲があるときは消化の良いものを少しずつ摂るようにしましょう。
おかゆ、うどん、豆腐、ヨーグルトなどがおすすめです。
発熱時の対処法として、額や首筋、脇の下を冷やすと楽になります。
保冷剤をタオルで包んで使うか、濡れタオルを当てるだけでも効果があります。
ただし、急激に冷やしすぎないよう注意してください。
また、家族への感染を防ぐため、以下の対策も忘れずに:
- タオルや食器は別にする
- こまめな手洗いと手指消毒
- 部屋の換気を定期的に行う
- マスクの着用(特に咳やくしゃみがある場合)
こんな症状が出たらすぐ病院へ 受診の目安
多くの夏の感染症は、適切な休養と水分補給で自然に回復しますが、次のような症状が現れたら、迷わず医療機関を受診してください。
| 症状 | 考えられるリスク | 対応 |
|---|---|---|
| 38.5度以上の高熱が3日以上続く | 細菌感染の可能性、脱水症状の進行 | 速やかに受診 |
| 激しい頭痛・首の硬直 | 髄膜炎の可能性 | 緊急受診 |
| 意識がもうろうとする | 重度の脱水、熱中症の合併 | 救急車を呼ぶ |
| 呼吸が苦しい・胸が痛い | 肺炎などの合併症 | 緊急受診 |
| 血便・激しい腹痛 | 腸管出血性大腸菌感染症など | 速やかに受診 |
| 尿が出ない・極端に少ない | 重度の脱水症状 | 速やかに受診 |
特に注意が必要なのは、乳幼児や高齢者、持病のある方です。
これらの方は症状が急激に悪化することがあるため、早めの受診を心がけてください。
乳幼児の場合は、以下の症状にも注意が必要です:
- ぐったりして反応が鈍い
- 泣き声が弱い、または泣かない
- おむつが6時間以上濡れていない
- 目がくぼんでいる
- 皮膚の弾力がなくなっている
受診する際は、症状がいつから始まったか、どのような経過をたどっているか、服用している薬があるかなどをメモしておくと、医師への説明がスムーズになります。
夏の感染症は、適切な対処をすれば多くの場合は数日で回復します。
しかし、「いつもと違う」と感じたら、無理せず医療機関を受診することが大切です。
自己判断で市販薬を使い続けるよりも、医師の診断を受けて適切な治療を受けることが、早期回復への近道となります。
6. まとめ
夏の感染症は、高温多湿な環境や人が集まる場所で特に広がりやすくなります。
プールや海水浴、キャンプ、お祭りなど、夏ならではの楽しいイベントも、正しい知識がないと感染症のリスクを高めてしまうかもしれません。
でも大丈夫。
基本的な手洗いや手指消毒、こまめな水分補給、そして免疫力を高める生活習慣を心がけることで、多くの感染症は予防できます。
もし体調を崩してしまったら、無理をせず早めに休養を取り、症状が重い場合は迷わず医療機関を受診しましょう。
正しい知識と予防法を身につけて、健康で楽しい夏を過ごしてくださいね。
商品カテゴリから探す