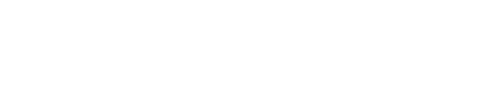健考彩都コラム
- TOP
- 知らないと損!夏の皮膚トラブル対策|あせも・虫刺され・日焼けの正しい知識とNG行動

知らないと損!夏の皮膚トラブル対策|あせも・虫刺され・日焼けの正しい知識とNG行動
2025年7月18日
夏になると急増するあせも、虫刺され、日焼け。
これらの皮膚トラブルに悩まされた経験、ありませんか?
かゆみや痛みに耐えながら「もっと早く対策しておけばよかった」と後悔することも。
実は、正しい知識があれば、これらのトラブルの多くは予防できるんです。
この記事では、夏の三大皮膚トラブルの原因から具体的な対策、できてしまった時の正しいケア方法まで、皮膚科医も推奨する最新の情報をわかりやすくお伝えします。
間違った対処法は症状を悪化させることもあるので、正しい知識を身につけて、快適な夏を過ごしましょう。
- 1. 夏に多発する皮膚トラブル その原因とは
- 夏の環境が皮膚に与える影響
- 夏に増える三大皮膚トラブルのメカニズム
- 皮膚トラブルを悪化させる意外な要因
- 2. 【症状別】夏の三大皮膚トラブル徹底対策
- あせも(汗疹)の正しい対策とケア方法
- かゆくてつらい虫刺されの対策
- 日焼けの正しい対策とアフターケア
- 3. まだある夏の皮膚トラブル とびひ・水虫にも注意
- とびひ(伝染性膿痂疹)の症状と対策
- じめじめした夏に増える水虫の対策
- 4. 夏の皮膚トラブル対策に関するよくある質問
- 子どものあせも対策で気をつけることは
- 虫除けと日焼け止めはどちらを先に塗るべきか
- 日焼け後の皮むけはどうすればいいか
- 5. まとめ
1. 夏に多発する皮膚トラブル その原因とは
夏になると「肌がかゆい」「赤くなってヒリヒリする」「ブツブツができた」なんて経験、ありませんか?
楽しいはずの夏が、皮膚トラブルのせいで憂鬱になってしまうこと、実は多くの人が経験しています。
実は、夏の皮膚トラブルには高温多湿な環境が大きく関係しているんです。
気温が上がると汗をかきやすくなり、湿度が高いと汗が蒸発しにくくなる。
この組み合わせが、さまざまな皮膚トラブルを引き起こす原因となっています。
夏の環境が皮膚に与える影響
日本の夏は特に高温多湿。
この環境下では、皮膚にこんな変化が起きています。
| 環境要因 | 皮膚への影響 | 起こりやすいトラブル |
|---|---|---|
| 高温(30℃以上) | 汗腺が活発化し、大量の汗を分泌 | あせも、かぶれ |
| 高湿度(70%以上) | 汗が蒸発しにくく、皮膚表面に滞留 | 細菌・真菌の繁殖 |
| 強い紫外線 | メラニン生成の活性化、皮膚の炎症 | 日焼け、シミ、そばかす |
| 屋外活動の増加 | 虫との接触機会が増える | 虫刺され、かゆみ |
さらに、エアコンの効いた室内と屋外の温度差が激しいことも、皮膚にストレスを与える要因になっています。
急激な温度変化は、皮膚のバリア機能を低下させ、トラブルを起こしやすくしてしまうのです。
夏に増える三大皮膚トラブルのメカニズム
あせも(汗疹)が発生する仕組み
あせもは、汗腺の出口が詰まることで起こります。
大量の汗をかいても、それがスムーズに排出されないと、汗が皮膚の中に溜まってしまう。
すると、小さな水ぶくれや赤いブツブツができてしまうんです。
特に、首筋や肘の内側、膝の裏など、皮膚が密着しやすい部分にできやすいのが特徴。
子どもは大人より汗腺の密度が高いため、あせもになりやすい傾向があります。
虫刺されが増える理由
夏は蚊やブヨなどの虫が活発に活動する季節。
気温が25~30℃、湿度が70%前後の環境は、これらの虫にとって最適な条件なんです。
また、薄着になることで皮膚の露出部分が増え、虫に刺されやすくなるのも大きな要因。
夕方から夜にかけて活動が活発になる蚊も多く、屋外でのレジャーやバーベキューなどで被害に遭うケースが増えています。
日焼けのダメージが深刻化する背景
夏の紫外線量は、冬の約5倍にもなることをご存知でしたか?
特に、午前10時から午後2時頃までは紫外線が最も強い時間帯。
この時間帯に無防備に外出すると、短時間でも日焼けしてしまいます。
紫外線には、UVAとUVBの2種類があり、それぞれ異なるダメージを与えるんです。
UVBは皮膚の表面に炎症を起こし、赤くヒリヒリとした日焼けの原因に。
一方、UVAは皮膚の奥深くまで到達し、シワやたるみの原因となります。
皮膚トラブルを悪化させる意外な要因
実は、夏の皮膚トラブルを悪化させているのは、私たちの何気ない習慣かもしれません。
| 悪化要因 | 具体的な行動 | 皮膚への悪影響 |
|---|---|---|
| 過度な洗浄 | 1日に何度もボディソープで洗う | 皮脂を取りすぎてバリア機能低下 |
| 冷房の使いすぎ | 設定温度を低くしすぎる | 皮膚の乾燥、血行不良 |
| 水分補給不足 | 喉が渇いてから飲む | 皮膚の水分量低下、回復力の低下 |
| 睡眠不足 | 夜更かしや浅い眠り | 皮膚の修復機能が働かない |
また、ストレスも見逃せない要因です。
夏バテによる体調不良や、暑さによるイライラは、自律神経のバランスを崩し、皮膚のトラブルを引き起こしやすくすることがわかっています。
これらの原因を理解することで、効果的な対策が見えてきます。
次の章では、それぞれのトラブルに対する具体的な対策方法を詳しく解説していきます。
2. 【症状別】夏の三大皮膚トラブル徹底対策
夏になると、汗をかく機会が増えて、虫も活発になり、紫外線も強くなります。
「去年も同じような症状で悩んだな...」と思い出す方も多いのではないでしょうか?
実は、これらの皮膚トラブルは正しい知識があれば、かなり防げるんです。
でも、間違った対処法をしてしまうと、症状が悪化したり、跡が残ったりすることも。
ここでは、夏の代表的な皮膚トラブルである「あせも」「虫刺され」「日焼け」について、それぞれの原因から対策まで詳しく解説していきます。
あせも(汗疹)の正しい対策とケア方法
「子どもの首や背中に赤いブツブツが...」「大人になってもあせもができるなんて」そんな経験はありませんか?
あせもは子どもだけの問題ではありません。
大人でも汗をかきやすい部位にできやすく、かゆみで日常生活に支障をきたすこともあります。
あせもの原因は汗と汚れ
あせもは、汗腺(汗の出口)が詰まることで起こる皮膚トラブルです。
汗をかいたまま放置すると、汗に含まれる塩分や皮脂、ほこりなどが混ざって汗腺をふさいでしまいます。
特に、首回り、わきの下、ひじの内側、ひざの裏側など、皮膚が重なりやすく汗がたまりやすい部位に発生しやすいのが特徴です。
あせもには大きく分けて3つのタイプがあります。
| 種類 | 見た目の特徴 | 症状 | できやすい人 |
|---|---|---|---|
| 水晶様汗疹 | 透明な小さな水ぶくれ | かゆみはほとんどない | 新生児や乳幼児 |
| 紅色汗疹 | 赤い小さなブツブツ | 強いかゆみを伴う | 子どもから大人まで |
| 深在性汗疹 | 肌色の平たい発疹 | かゆみは少ない | 高温多湿環境で働く人 |
あせもを防ぐための具体的な対策
あせもの予防で最も大切なのは、汗をかいたらすぐに拭き取ることです。
でも、仕事中や外出先では、すぐにシャワーを浴びるわけにもいきませんよね。
そんなときは、以下の対策を心がけてみてください。
まず、服装選びがポイントです。
通気性の良い綿や麻素材の服を選び、締め付けの少ないゆったりとしたデザインのものを着用しましょう。
吸湿速乾素材のインナーも効果的です。
次に、こまめな汗の処理が重要です。
濡れタオルやウェットティッシュで汗を拭き取り、可能であれば着替えを持ち歩くことをおすすめします。
エアコンの効いた場所で体を冷やすことも効果的ですが、急激な温度変化は避けましょう。
自宅では、ぬるめのシャワーで汗を流し、石鹸は泡立ててやさしく洗うようにします。
ゴシゴシこすると皮膚を傷つけて、かえってあせもができやすくなってしまいます。
できてしまった時の正しいケアとNG行動
あせもができてしまったら、まず患部を清潔に保ち、かきむしらないことが大切です。
かゆみが強いとついかいてしまいますが、これは絶対にNGです。
かくことで皮膚が傷つき、細菌感染を起こして「とびひ」になる可能性があります。
正しいケア方法として、まず患部を水で優しく洗い流し、清潔なタオルで水分を吸い取るように拭きます。
その後、市販のあせも用ローションやパウダーを薄く塗布します。
かゆみが強い場合は、保冷剤をタオルで包んで患部を冷やすと楽になります。
よくあるNG行動をまとめました。
| NG行動 | なぜダメなのか | 正しい対処法 |
|---|---|---|
| 患部をかきむしる | 皮膚が傷つき細菌感染のリスク | 冷やしてかゆみを抑える |
| 熱いお湯で洗う | かゆみが増し、皮膚が乾燥する | ぬるま湯で優しく洗う |
| ベビーパウダーの使いすぎ | 汗腺を詰まらせる原因に | 薄く均一に塗布する |
| 市販薬を長期間使用 | 皮膚が薄くなる副作用の可能性 | 1週間で改善しなければ受診 |
あせもにおすすめの市販薬と病院に行く目安
軽いあせもなら、市販薬でも十分対処できます。
かゆみ止め成分(ジフェンヒドラミン)や抗炎症成分(グリチルレチン酸)が配合されたローションやクリームがおすすめです。
「ポリベビー」「ユースキンあせもクリーム」などが代表的な商品です。
ただし、以下の症状がある場合は、すぐに皮膚科を受診してください。
発熱を伴う場合、患部が化膿して黄色い膿が出ている場合、市販薬を1週間使っても改善しない場合、あせもの範囲が広がっている場合などは、医師の診察が必要です。
かゆくてつらい虫刺されの対策
「キャンプから帰ってきたら、足が虫刺されだらけ...」「公園で遊んでいたら、子どもが蚊に刺されて大きく腫れてしまった」夏のアウトドアは楽しいけれど、虫刺されは避けられない悩みですよね。
蚊やブヨなど虫の種類と症状の違い
実は、虫の種類によって症状や対処法が異なることをご存知でしょうか?
適切な対処をするためには、まず何に刺されたのかを見極めることが大切です。
| 虫の種類 | 刺された直後の症状 | その後の経過 | 特徴的な症状 |
|---|---|---|---|
| 蚊 | すぐにかゆくなる | 数時間で治まることが多い | 赤い小さな膨らみ |
| ブヨ(ブユ) | 刺された時は気づかない | 翌日以降に強い腫れ | 硬いしこりができる |
| ダニ | 就寝中に刺される | 1週間以上かゆみが続く | 複数箇所を刺される |
| 毛虫 | 触れた瞬間に痛み | 赤い発疹が広がる | 線状の発疹 |
特に注意が必要なのは、ブヨによる虫刺されです。
山間部や水辺に生息し、刺された時は痛みを感じないため気づきにくいのですが、翌日以降に患部が大きく腫れ上がり、強いかゆみと痛みを伴います。
虫刺されを未然に防ぐ効果的な対策
虫刺されは、事前の対策でかなり防ぐことができます。
まず基本となるのは、虫除けスプレーの正しい使用です。
有効成分であるディートやイカリジンが配合されたものを選び、露出している肌にムラなく塗布します。
効果は2〜4時間程度なので、こまめに塗り直すことが大切です。
服装も重要な防御策です。
長袖・長ズボンを着用し、明るい色の服を選びましょう。
蚊は黒や紺などの暗い色に引き寄せられる習性があります。
また、香水や柔軟剤の強い香りも虫を引き寄せるので、アウトドアの際は控えめにしましょう。
環境対策として、蚊取り線香や電気蚊取り器を活用し、網戸の破れがないか確認することも大切です。
庭やベランダの水たまりは蚊の発生源になるので、こまめに水を捨てるようにしましょう。
刺された後の正しい対処法とNG行動
虫に刺されてしまったら、まず患部を水で洗い流し、冷やすことが基本です。
かゆみを我慢できずにかいてしまうと、皮膚が傷つき、細菌感染のリスクが高まります。
応急処置の手順は以下の通りです。
まず、刺された部位を流水で洗い、石鹸で優しく洗浄します。
清潔なタオルで水分を拭き取り、保冷剤や冷たいタオルで患部を冷やします。
その後、虫刺され用の薬を塗布します。
絶対に避けたいNG行動があります。
爪でバツ印をつける行為は、皮膚を傷つけるだけでなく、かゆみも治まりません。
また、民間療法として唾液を塗る人もいますが、口の中の雑菌が傷口に入る可能性があるので避けましょう。
熱いシャワーを当てることも、一時的にかゆみは和らぐものの、その後さらにかゆみが増すので逆効果です。
虫刺され薬の選び方と皮膚科を受診すべき症状
虫刺され薬は、症状の程度によって使い分けることが大切です。
軽いかゆみには、抗ヒスタミン成分配合の薬(ムヒ、ウナコーワなど)で十分です。
腫れが強い場合は、ステロイド成分配合の薬(フルコートF、リンデロンVGなど)が効果的ですが、長期使用は避けましょう。
以下の症状が現れたら、すぐに医療機関を受診してください。
全身に蕁麻疹が出た場合、呼吸が苦しくなった場合、発熱や激しい頭痛がある場合、刺された部位が化膿している場合、リンパ節が腫れている場合などは、アナフィラキシーショックや二次感染の可能性があります。
日焼けの正しい対策とアフターケア
「日焼け止めを塗ったはずなのに、肩が真っ赤に...」「曇りの日だから大丈夫と思ったら、意外と焼けてしまった」そんな経験はありませんか?
日焼けは単なる肌の色の変化ではなく、皮膚へのダメージそのものです。
うっかり日焼けが招く肌へのダメージ
日焼けは、紫外線による皮膚の炎症反応です。
紫外線にはUVAとUVBの2種類があり、それぞれ肌に与える影響が異なります。
UVBは肌の表面に作用し、赤みや痛みを引き起こします。
一方、UVAは肌の奥深くまで到達し、シワやたるみの原因となります。
短期的な影響として、日焼け直後は肌が赤くなり、ヒリヒリとした痛みを感じます。
重度の日焼けでは水ぶくれができることもあります。
長期的には、シミやそばかすの原因となり、肌の老化を早めます。
さらに深刻な場合は、皮膚がんのリスクも高まります。
日焼け止めの効果的な選び方と塗り方
日焼け止めを選ぶ際は、使用シーンに合わせてSPFとPAの数値を確認することが大切です。
日常生活ではSPF20〜30、PA++程度で十分ですが、海やプールなどのレジャーではSPF50+、PA++++の製品を選びましょう。
| 使用シーン | 推奨SPF | 推奨PA | 塗り直し頻度 |
|---|---|---|---|
| 日常生活(買い物など) | SPF20〜30 | PA++ | 3〜4時間ごと |
| 屋外スポーツ | SPF30〜50 | PA+++ | 2〜3時間ごと |
| 海・プール | SPF50+ | PA++++ | 2時間ごと、水から上がるたび |
| 登山・長時間の屋外活動 | SPF50+ | PA++++ | 2時間ごと |
正しい塗り方も重要です。
外出の15〜30分前に塗布し、顔の場合は500円玉大、体の場合は各部位にたっぷりと塗ります。
耳の後ろ、首の後ろ、手の甲、足の甲など、塗り忘れやすい部位も忘れずに。
また、汗をかいたり、タオルで拭いたりした後は必ず塗り直しましょう。
日焼けしてしまった後の正しいアフターケア対策
日焼けしてしまったら、72時間以内のケアが肌の回復を左右します。
まず、冷やすことが最優先です。
冷たいシャワーを浴びるか、濡れタオルで患部を冷やします。
その際、氷を直接当てるのは刺激が強すぎるので避けましょう。
次に、保湿が重要です。
日焼け後の肌は極度に乾燥しているため、刺激の少ない化粧水をたっぷりと使い、その後、保湿クリームでしっかりと蓋をします。
アロエベラ配合の製品は、炎症を抑える効果があるのでおすすめです。
内側からのケアも忘れずに。
水分補給を心がけ、ビタミンCやビタミンEを多く含む食品を摂取しましょう。
トマトに含まれるリコピンには、紫外線ダメージを軽減する効果があります。
シミを作らないために知っておきたい日焼けのNG行動
日焼け後のNG行動を避けることで、シミやそばかすのリスクを減らせます。
まず、日焼け直後の美白化粧品の使用は避けましょう。
炎症を起こしている肌に刺激の強い成分を使うと、かえって色素沈着を起こす可能性があります。
また、皮がむけてきても無理にはがさないことが大切です。
自然にはがれるのを待ち、保湿を続けましょう。
熱いお風呂も避け、ぬるめのシャワーで済ませます。
アルコールの摂取も、脱水を促進し回復を遅らせるので控えめにしましょう。
日焼け後1週間は、再び紫外線を浴びないよう特に注意が必要です。
外出時は日焼け止めをしっかり塗り、帽子や日傘、UVカット素材の衣類で物理的に紫外線をブロックしましょう。
3. まだある夏の皮膚トラブル とびひ・水虫にも注意
あせもや虫刺され、日焼けだけが夏の皮膚トラブルではありません。
高温多湿な日本の夏は、細菌や真菌が繁殖しやすく、とびひや水虫といった感染性の皮膚トラブルも起こりやすい季節です。
これらは適切な対策を知らないと、症状が長引いたり、家族にうつしてしまうこともあるんです。
とびひ(伝染性膿痂疹)の症状と対策
子どもの夏の皮膚トラブルで特に注意したいのが「とびひ」です。
正式には伝染性膿痂疹といい、細菌感染によって水ぶくれやかさぶたができ、それが全身に広がっていく病気です。
とびひの原因と感染経路
とびひは主に黄色ブドウ球菌や溶血性連鎖球菌が原因で起こります。
虫刺されやあせもを掻きむしった傷口から細菌が入り込み、感染が始まります。
特に夏は汗をかきやすく、皮膚が不潔になりがちなため、細菌が繁殖しやすい環境になってしまうんです。
感染した部分を触った手で他の部位を触ると、火の粉が飛び散るように次々と感染が広がることから「とびひ」と呼ばれています。
兄弟間での感染も多く、タオルの共用などでうつることもあります。
とびひの症状と見分け方
| 症状の種類 | 特徴 | 好発部位 |
|---|---|---|
| 水疱性膿痂疹 | 透明な水ぶくれができて破れやすい | 顔、手足、体幹 |
| 痂皮性膿痂疹 | 厚いかさぶたができる | 顔面、四肢 |
初期症状として、虫刺されのような赤い発疹から始まることが多く、その後水ぶくれができます。
水ぶくれは簡単に破れて、じゅくじゅくした状態になり、そこから感染が広がっていきます。
とびひの治療と予防対策
とびひは抗生物質による治療が必要な細菌感染症です。
市販薬での対処は難しく、皮膚科での診察を受けることが大切です。
処方される抗生物質の内服薬と外用薬を、医師の指示通りに使用します。
予防対策として最も重要なのは、虫刺されやあせもを掻かないことです。
爪を短く切り、手洗いを徹底し、タオルや衣類の共用は避けましょう。
プールや海水浴は、完全に治るまで控える必要があります。
じめじめした夏に増える水虫の対策
梅雨から夏にかけて、足のかゆみに悩まされる人が増えます。
その原因の多くが水虫です。
日本人の5人に1人は水虫に感染しているといわれており、決して他人事ではありません。
水虫が夏に増える理由
水虫の原因は白癬菌というカビの一種です。
この菌は高温多湿を好むため、汗をかきやすく靴の中が蒸れやすい夏は、まさに水虫にとって絶好の繁殖環境なんです。
特に問題なのは、革靴やスニーカーを長時間履き続けることです。
足の指の間は汗がたまりやすく、通気性も悪いため、白癬菌が増殖しやすい環境になってしまいます。
水虫の症状と種類
| 水虫の種類 | 主な症状 | 特徴 |
|---|---|---|
| 趾間型 | 指の間がふやけて皮がむける | 最も多いタイプ |
| 小水疱型 | 土踏まずに小さな水ぶくれ | 強いかゆみを伴う |
| 角質増殖型 | かかとがガサガサになる | かゆみは少ない |
初期症状は軽いかゆみから始まることが多く、「ただの汗疹かな」と見過ごしてしまいがちです。
しかし、放置すると症状が悪化し、爪にまで感染が広がることもあります。
水虫の効果的な治療と予防
水虫の治療には、抗真菌薬を根気よく使い続けることが重要です。
症状が改善しても、菌が完全に死滅するまでには時間がかかるため、最低でも1〜2ヶ月は薬を続ける必要があります。
予防対策として大切なのは、足を清潔に保ち、しっかり乾燥させることです。
毎日同じ靴を履かず、2〜3足をローテーションで使用しましょう。
また、家族に水虫の人がいる場合は、バスマットやスリッパの共用は避け、床掃除をこまめに行うことも大切です。
市販薬で改善しない時は皮膚科へ
市販の水虫薬を2週間使用しても改善が見られない場合は、別の皮膚疾患の可能性もあります。
また、爪水虫は市販薬では治療が困難なため、皮膚科での診察が必要です。
糖尿病などの基礎疾患がある方は、水虫が重症化しやすいため、早めの受診をおすすめします。
4. 夏の皮膚トラブル対策に関するよくある質問
夏の皮膚トラブルについて、多くの方が抱える疑問や悩みがあります。
ここでは、特に質問の多い内容について、皮膚科医の見解も踏まえながら詳しく解説していきます。
正しい知識を身につけることで、家族みんなの肌を守ることができるでしょう。
子どものあせも対策で気をつけることは
子どもは大人よりも汗をかきやすく、体温調節機能も未熟なため、あせもができやすい傾向にあります。
特に赤ちゃんや幼児は、自分で「暑い」「かゆい」と伝えることが難しいため、保護者の細やかな観察が必要です。
まず、室温は26〜28度、湿度は50〜60%を目安に調整しましょう。
エアコンの風が直接当たらないよう、風向きを調整することも大切です。
衣服は綿100%など吸湿性の高い素材を選び、汗をかいたらこまめに着替えさせてください。
入浴時は、ぬるめのお湯で優しく洗い、石鹸の使いすぎは避けましょう。
保湿剤は、さらっとしたローションタイプがおすすめです。
オムツをしている赤ちゃんは、オムツかぶれとあせもが併発しやすいため、頻繁にオムツ交換を行い、おしりふきで拭いた後は十分に乾かしてから新しいオムツをつけることが重要です。
| 年齢 | 特に注意すべき部位 | 対策のポイント |
|---|---|---|
| 0〜1歳 | 首まわり、背中、オムツ周辺 | 授乳後の汗を拭く、背中に汗取りパッドを使用 |
| 1〜3歳 | ひじの内側、ひざの裏、首筋 | 外遊び後はシャワーで汗を流す、着替えを持参 |
| 3〜6歳 | 髪の生え際、背中、脇の下 | 帽子をかぶる、汗拭きシートを活用 |
また、かきむしることで症状が悪化するため、爪は短く切り、就寝時にはミトンの使用も検討しましょう。
症状が改善しない場合や、発熱を伴う場合は、早めに小児科や皮膚科を受診することをおすすめします。
虫除けと日焼け止めはどちらを先に塗るべきか
夏のお出かけで悩むのが、虫除けと日焼け止めの使用順序です。
正しい順番は「日焼け止め→虫除け」です。
この順序には、それぞれの成分の特性に基づいた明確な理由があります。
日焼け止めは肌に密着して紫外線をブロックする必要があるため、素肌に直接塗ることで効果を発揮します。
一方、虫除けは揮発性の成分が空気中に広がることで虫を寄せ付けない仕組みなので、最後に塗ることで効果的に作用します。
具体的な使用方法として、まず日焼け止めを塗り、15〜20分程度待ってから虫除けを使用しましょう。
この待ち時間により、日焼け止めが肌にしっかりと定着します。
スプレータイプの虫除けを使う場合は、日焼け止めが完全に乾いてから使用することが大切です。
| 製品タイプ | 塗り直しの目安 | 注意点 |
|---|---|---|
| 日焼け止め(クリーム) | 2〜3時間ごと | 汗をかいたら塗り直す |
| 日焼け止め(スプレー) | 1〜2時間ごと | ムラになりやすいので重ね塗り |
| 虫除け(ローション) | 3〜4時間ごと | 衣服の上からも使用可能 |
| 虫除け(スプレー) | 2〜3時間ごと | 風向きに注意して使用 |
両方を塗り直す場合も、同じ順序で行います。
ただし、汗を大量にかいた後は、一度タオルで汗を拭き取ってから塗り直すことで、より効果的に肌を守ることができます。
日焼け後の皮むけはどうすればいいか
日焼け後に起こる皮むけは、紫外線によってダメージを受けた表皮細胞が剥がれ落ちる自然な現象です。
しかし、無理に皮をむいてしまうと、新しい皮膚を傷つけ、色素沈着や感染のリスクが高まります。
皮むけが始まったら、まず保湿を徹底することが重要です。
アロエベラ配合のジェルや、セラミド配合の保湿クリームを1日3〜4回塗布しましょう。
お風呂はぬるめのお湯にし、タオルでゴシゴシこすらず、優しく押さえるように水分を拭き取ります。
どうしても皮がめくれて気になる場合は、清潔なハサミで浮いている部分だけを慎重にカットし、その後必ず保湿剤を塗ってください。
皮むけの期間中は、新たな日焼けを避けることが特に重要です。
外出時は必ず日焼け止めを使用し、できるだけ肌の露出を控えましょう。
また、皮むけの回復を早めるために、ビタミンCやビタミンEを多く含む食品を積極的に摂取することもおすすめです。
トマト、ピーマン、キウイフルーツなどは、肌の修復を助ける栄養素が豊富に含まれています。
水分補給も忘れずに、1日1.5〜2リットルを目安に水やお茶を飲むようにしましょう。
皮むけが2週間以上続く場合や、痛みや腫れを伴う場合は、皮膚科を受診することをおすすめします。
適切な治療を受けることで、肌トラブルの長期化を防ぐことができます。
5. まとめ
夏の皮膚トラブル対策、いかがでしたか?
あせも・虫刺され・日焼けは、どれも予防が何より大切です。
汗はこまめに拭き取り、虫除けスプレーは2〜3時間ごとに塗り直し、日焼け止めはSPF30以上のものを選んで2時間おきに重ね塗りする。
これらの基本的な対策を習慣にすることで、夏の肌トラブルの多くは防げます。
もし症状が出てしまったら、掻きむしらない、冷やす、保湿するという3つの基本を守りましょう。
市販薬で改善しない場合は、早めに皮膚科を受診することも大切です。
正しい知識と対策で、快適な夏を過ごしてくださいね。
商品カテゴリから探す