健考彩都コラム
- TOP
- 【2025年最新】花粉症対策の決定版!症状別対策とおすすめ市販品&効果的な使い方

【2025年最新】花粉症対策の決定版!症状別対策とおすすめ市販品&効果的な使い方
2025年4月1日
2025年最新の花粉症対策を症状別に徹底解説。くしゃみ・鼻水・目のかゆみなどを抑える市販薬や便利な対策グッズの紹介と、生活習慣の見直しや花粉情報の活用法も解説。NG行動も押さえて、つらい花粉症にさよならし、快適な春を迎えましょう。
- 1. 花粉症とは?
- 花粉症の原因
- 花粉症のメカニズム
- 花粉症と診断されたら
- 2. 花粉症対策の基本 市販品を使う前に
- ■花粉の侵入を防ぐ
- ■生活習慣の見直し
- ■花粉情報を確認する
- 3. 症状別 花粉症対策とおすすめ市販品
- ■鼻の症状対策
- ■目の症状対策
- ■のどの症状対策
- ■皮膚の症状対策
- 4. 花粉症対策におすすめの市販の内服薬
- ■抗ヒスタミン薬
- ■第二世代抗ヒスタミン薬
- 5. 花粉症対策におすすめの市販の点眼薬
- ■抗ヒスタミン点眼薬
- ■抗アレルギー点眼薬
- ■血管収縮点眼薬
- ■人工涙液
- ■点眼薬の選び方
- 6. 花粉症対策におすすめの市販の点鼻薬
- ■血管収縮剤
- ■ステロイド剤
- ■点鼻薬の効果的な使い方
- 7. 花粉症対策におすすめの市販の保湿クリーム
- ■保湿クリームを選ぶポイント
- ■おすすめの市販保湿クリーム
- ■保湿クリームの効果的な使い方
- 8. 花粉症対策におすすめの市販のマスク
- ■マスクの種類と特徴
- ■マスクの選び方
- ■マスクの効果的な使い方
- 9. 花粉症対策におすすめの市販の空気清浄機
- ■空気清浄機を選ぶポイント
- ■おすすめメーカーと製品例
- 10. 花粉症対策でやってはいけないNG行動
- ■花粉を家の中に持ち込む行動
- ■生活習慣におけるNG行動
- ■間違った花粉症対策
- 11. よくある質問
- Q. 花粉症の症状はいつ頃まで続きますか?
- Q. 市販薬で効果がない場合はどうすれば良いですか?
- Q. 花粉症の検査はどのように行いますか?
- Q. 花粉症対策に効果的な食べ物や飲み物はありますか?
- Q. マスクはどのタイプが効果的ですか?
- Q. 空気清浄機は効果がありますか?
- Q. 子供の花粉症対策はどうすれば良いですか?
- Q. 妊娠中や授乳中に花粉症の薬は飲めますか?
- Q. 花粉症と風邪の違いは?
- Q. 日常生活でできる花粉症対策はありますか?
- Q. レーザー治療は効果がありますか?
- Q. 舌下免疫療法とはどのような治療法ですか?
- 12. まとめ
つらい花粉症の症状に悩まされていませんか?くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみ…もう憂鬱な春とはおさらばしましょう。
この記事では、2025年最新の花粉症対策を症状別に徹底解説!
市販薬の効果的な使い方や、おすすめの商品(アレグラFX、パブロン鼻炎カプセルSα、AGノーズアレルカットSなど)もご紹介。
内服薬、点眼薬、点鼻薬、保湿クリーム、マスク、空気清浄機など、様々な対策法を網羅しているので、自分にぴったりの対策が見つかるはずです。
さらに、花粉症対策でやってはいけないNG行動も紹介。この記事を読めば、つらい花粉症を乗り越え、快適な毎日を送るための知識が身につきます。
1. 花粉症とは?

花粉症とは、植物の花粉が原因となって引き起こされるアレルギー性鼻炎の一種です。正式には「季節性アレルギー性鼻炎」と呼ばれます。
スギやヒノキ、ブタクサなど、風媒花と呼ばれる風によって花粉が運ばれる植物の花粉が主な原因となります。これらの花粉が鼻や目などの粘膜に付着すると、体内の免疫システムが過剰に反応し、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみなどのアレルギー症状が現れます。
花粉症の原因
花粉症は、免疫システムの過剰反応によって引き起こされます。
通常、免疫システムは体内に侵入した異物(抗原)を攻撃し、体を守っています。しかし、花粉症の場合は、無害な花粉を異物と認識し、過剰に攻撃してしまうのです。この過剰反応によって、ヒスタミンなどの化学物質が放出され、アレルギー症状を引き起こします。
花粉の種類と飛散時期
花粉症を引き起こす植物は様々ですが、日本では特にスギとヒノキの花粉症患者が多く、全体の約7割を占めていると言われています。
その他にも、ブタクサ、イネ、カモガヤなど、様々な植物の花粉がアレルギーの原因となります。
| 植物 | 飛散時期 |
|---|---|
| スギ | 2月~4月 |
| ヒノキ | 3月~5月 |
| ブタクサ | 8月~10月 |
| イネ | 8月~10月 |
| カモガヤ | 5月~7月 |
これらの飛散時期は地域や気候によって多少前後することがあります。
近年は地球温暖化の影響で、花粉の飛散時期が早まったり、飛散量が増加したりする傾向が見られます。
花粉症のメカニズム
花粉が鼻や目に侵入すると、粘膜にある肥満細胞という細胞に付着します。肥満細胞の表面には、IgE抗体と呼ばれる物質が存在し、花粉と結合します。この結合によって肥満細胞が活性化し、ヒスタミンなどの化学伝達物質が放出されます。
これらの化学物質が、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみなどのアレルギー症状を引き起こします。
一度花粉に感作されると、次に同じ花粉に曝露された際に、より強いアレルギー反応が起こりやすくなります。
※IgE抗体とは
IgE抗体は、免疫グロブリンEと呼ばれるタンパク質の一種で、アレルギー反応に関与する抗体です。花粉症患者では、特定の花粉に対するIgE抗体の値が高くなっていることが多く、血液検査で測定することができます。
花粉症と診断されたら
花粉症の症状が疑われる場合は、耳鼻咽喉科やアレルギー科を受診しましょう。医師による問診や診察、アレルギー検査などによって診断されます。
自己判断で市販薬を使用するのではなく、まずは医療機関を受診し、適切な治療を受けることが重要です。
花粉症は、適切な治療と対策を行うことで症状を軽減し、日常生活への影響を最小限に抑えることができます。
早期に診断を受け、自分に合った治療法を見つけることが大切です。
2. 花粉症対策の基本 市販品を使う前に

花粉症対策は、市販薬に頼る前にできることがたくさんあります。
これらの基本的な対策をしっかり行うことで、症状を軽減し、薬の使用を最小限に抑えることができます。また、市販薬の効果をより高めることにも繋がります。
■花粉の侵入を防ぐ
花粉症対策の基本は、花粉を体内に侵入させないことです。以下の対策を心がけましょう。
外出時の対策
外出時は、以下の対策を徹底することで、花粉の付着を減らすことができます。
- マスクの着用:花粉の侵入を効果的に防ぎます。顔にフィットするものを選び、隙間がないように正しく着用しましょう。不織布マスクは、花粉の捕集率が高いのでおすすめです。メガネも併用すると、目への花粉侵入を防ぐ効果が高まります。
- 衣類の工夫:花粉が付着しにくい素材の服を選びましょう。表面がツルツルした素材がおすすめです。ウールやモヘアなどの起毛素材は花粉が付着しやすいため避けましょう。帽子をかぶるのも効果的です。
- 帰宅時のケア:帰宅したら、玄関先で服や髪についた花粉を払い落とし、すぐに着替えるようにしましょう。室内に花粉を持ち込まないことが大切です。
室内での対策
室内でも花粉対策は重要です。以下の点に注意しましょう。
- 換気の工夫:花粉の飛散量が少ない時間帯を選び、短時間で行いましょう。換気扇や空気清浄機を併用すると効果的です。
窓を開ける際は、レースカーテンを閉めることで花粉の侵入を軽減できます。 - 洗濯物の取り込み:花粉の飛散量が多い日は、屋外に洗濯物を干すのは避けましょう。室内干しにするか、乾燥機を使用することをおすすめします。
どうしても外に干す場合は、花粉の飛散が少ない時間帯を選び、取り込む際にしっかりと花粉を払い落としましょう。 - 掃除:こまめな掃除で室内に溜まった花粉を除去しましょう。
掃除機をかける際は、排気口から花粉が排出されないように、高性能フィルターを搭載した掃除機を使用するか、窓を開けて換気をしながら行いましょう。
床は水拭きが効果的です。 - 空気清浄機の使用:高性能フィルターを搭載した空気清浄機は、室内の花粉を除去するのに役立ちます。適切な場所に設置し、定期的にフィルターを交換しましょう。
■生活習慣の見直し
規則正しい生活習慣は、免疫力を高め、花粉症の症状を軽減するのに役立ちます。
| 項目 | 具体的な対策 |
|---|---|
| 睡眠 | 質の良い睡眠を十分にとりましょう。睡眠不足は免疫力を低下させ、花粉症の症状を悪化させる可能性があります。 |
| 食事 | バランスの良い食事を心がけ、免疫力を高めましょう。 ヨーグルトなどの発酵食品や、ビタミンC、ビタミンDを多く含む食品を積極的に摂取するのがおすすめです。 |
| ストレス | ストレスは免疫力を低下させるため、適度な運動やリラックスできる時間を作るなど、ストレスを溜めないように工夫しましょう。 |
■花粉情報を確認する
花粉の飛散状況を把握することで、適切な対策をとることができます。
環境省のウェブサイトや、天気予報などで花粉情報をこまめに確認し、飛散量が多い日は特に注意しましょう。
花粉飛散予報を活用して、外出の予定を立てたり、対策を強化したりすることで、症状を悪化させずに過ごすことができます。
これらの基本的な対策をしっかりと行うことで、花粉症の症状を軽減し、快適に過ごすことができます。
市販薬を使用する際は、これらの対策と併用することで、より効果的に症状を抑えることができます。
3. 症状別 花粉症対策とおすすめ市販品
花粉症の症状は人それぞれ。鼻水やくしゃみ、目のかゆみなど、様々な症状が現れます。
ここでは、症状別に効果的な対策とおすすめの市販品をご紹介します。
■鼻の症状対策
鼻づまり
鼻づまりは、花粉が鼻の粘膜に付着することで炎症を起こし、鼻腔が狭くなることで発生します。
粘膜の腫れを抑える点鼻薬や、鼻腔の通りをよくする成分を含む点鼻薬が効果的です。
また、鼻づまりがひどい場合は、抗ヒスタミン薬やロイコトリエン拮抗薬などの内服薬も併用すると良いでしょう。
加湿器を使って鼻の粘膜を乾燥させないことも重要です。
| 商品名 | 特徴 |
|---|---|
| ナザール「スプレー ポンプ」(点鼻薬) | 血管収縮剤で鼻づまりを素早く解消 |
| AGノーズアレルカットS(点鼻薬) | 抗アレルギー剤で鼻づまり、鼻みず、くしゃみを抑える |
| アレグラFX(内服薬) | 抗ヒスタミン薬で、眠くなりにくい |
鼻水
鼻水は、鼻の粘膜が炎症を起こして過剰に分泌されることで発生します。
サラサラとした水のような鼻水には抗ヒスタミン薬、粘り気のある鼻水には抗アレルギー薬が効果的です。
また、鼻をかみすぎると鼻の粘膜を傷つけてしまうため、優しく鼻をかむようにしましょう。
点鼻薬の使用も効果的ですが、使用頻度を守って正しく使うことが大切です。
| 商品名 | 特徴 |
|---|---|
| パブロン鼻炎カプセルSα(内服薬) | 鼻みず、鼻づまりに効果的なカプセルタイプ |
| コンタック鼻炎Z(内服薬) | 持続性のある鼻炎薬 |
くしゃみ
くしゃみは、鼻の粘膜に付着した花粉を体外に出そうとする反応です。
くしゃみと同時に鼻水が出る場合は、抗ヒスタミン薬が効果的です。
また、マスクの着用や外出を控えることで、花粉の吸入を防ぎ、くしゃみを軽減することができます。
アルコールや刺激物の摂取はくしゃみを誘発する可能性があるため、控えるようにしましょう。
■目の症状対策
かゆみ
目のかゆみは、花粉が目に入って炎症を起こすことで発生します。
抗アレルギー成分配合の点眼薬を使用することで、かゆみを抑えることができます。
また、目をこすってしまうと症状が悪化するため、こすらないように注意しましょう。洗眼薬で目を洗い流すことも効果的です。
| 商品名 | 特徴 |
|---|---|
| ロート アルガード クリアマイルドEXa(点眼薬) | 抗アレルギー成分配合で、かゆみを鎮める |
| アイボンAL(洗眼薬) | 抗炎症成分配合で、炎症を鎮める |
充血
目の充血は、花粉による炎症で血管が拡張することで起こります。血管収縮作用のある点眼薬を使用することで、充血を軽減することができます。
ただし、使いすぎると rebound 現象を起こす可能性があるため、使用頻度には注意が必要です。冷湿布で目を冷やすことも効果的です。
涙目
涙目は、目から花粉を洗い流そうとする体の防御反応です。抗アレルギー点眼薬を使用することで、涙目の症状を緩和することができます。
また、人工涙液で目を潤すことも効果的です。涙を拭き取る際は、清潔なガーゼやティッシュを使用しましょう。
■のどの症状対策
痛み
のどの痛みは、花粉がのどの粘膜に付着して炎症を起こすことで発生します。
イソジンなどのうがい薬でうがいをする、のど飴を舐める、温かい飲み物を飲むなどでのどの痛みを和らげることができます。
また、加湿器を使ってのどの乾燥を防ぐことも重要です。
イガイガ
のどのイガイガは、花粉による炎症や乾燥によって引き起こされます。マヌカハニーやのど飴を舐めると、イガイガを和らげることができます。
また、マスクの着用や加湿によって、のどの乾燥を防ぐことも効果的です。刺激の強い食べ物や飲み物は避け、消化の良いものを摂取するようにしましょう。
■皮膚の症状対策
かゆみ
皮膚のかゆみは、花粉が皮膚に付着することでアレルギー反応が起こり、炎症を引き起こすことで発生します。
抗ヒスタミン薬の内服やステロイド外用薬の使用が効果的です。
かゆい部分を掻きむしってしまうと症状が悪化するため、冷やす、保湿などでかゆみを抑えるようにしましょう。
また、低刺激性の石鹸や洗剤を使用することも大切です。
| 商品名 | 特徴 |
|---|---|
| アレルギールクリーム | 抗ヒスタミン成分配合で、かゆみを鎮める |
| ユースキンI(アイ) | かゆみを伴う乾燥肌に |
炎症
皮膚の炎症は、花粉によるアレルギー反応が原因で起こります。ステロイド外用薬を塗布することで炎症を抑えることができます。
また、炎症を起こしている部分を冷やすことも効果的です。症状がひどい場合は、皮膚科を受診しましょう。
4. 花粉症対策におすすめの市販の内服薬

つらい花粉症の症状を緩和するために、様々な市販薬が販売されています。
ここでは、効果的な内服薬の種類と、それぞれの特徴について解説します。自分に合った薬を選ぶ際の参考にしてください。
■抗ヒスタミン薬
抗ヒスタミン薬は、花粉症の代表的な治療薬です。ヒスタミンのはたらきを抑えることで、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみなどのアレルギー症状を緩和します。
眠気などの副作用が少ない第二世代抗ヒスタミン薬が多く市販されています。
主な市販薬
| 商品名 | 有効成分 | 特徴 |
|---|---|---|
| アレグラFX | フェキソフェナジン塩酸塩 | 1日2回の服用で効果が持続します。 |
| アレジオン20 | エピナスチン塩酸塩 | 即効性があり、1日1回の服用で効果が持続します。 |
| クラリチンEX | ロラタジン | 眠気が少なく、1日1回の服用で効果が持続します。 |
■第二世代抗ヒスタミン薬
第二世代抗ヒスタミン薬は、第一世代に比べて眠気などの副作用が少ないのが特徴です。そのため、日常生活への影響を最小限に抑えながら花粉症対策ができます。
効果や持続時間も様々なので、自分に合った薬を選ぶことが重要です。
主な市販薬
| 商品名 | 有効成分 | 特徴 |
|---|---|---|
| アレグラFX | フェキソフェナジン塩酸塩 | 持続性の高い抗ヒスタミン薬です。 |
| アレジオン20 | エピナスチン塩酸塩 | 即効性と持続性を両立した抗ヒスタミン薬です。 |
| クラリチンEX | ロラタジン | 眠気が少なく、1日1回の服用で効果が持続します。 |
市販薬を選ぶ際には、自分の症状や体質に合ったものを選ぶことが重要です。薬剤師や登録販売者に相談しながら、適切な薬を選ぶようにしましょう。
また、妊娠中や授乳中、持病がある場合は、医師に相談してから服用するようにしてください。
5. 花粉症対策におすすめの市販の点眼薬

花粉症のつらい症状の一つである目のかゆみ、充血、涙目。これらの症状を緩和するために、市販の点眼薬は効果的な選択肢となります。
様々な種類の点眼薬が販売されていますが、それぞれに特徴があるので、ご自身の症状や好みに合わせて選ぶことが重要です。
ここでは、おすすめの市販点眼薬とその特徴、選び方について詳しく解説します。
■抗ヒスタミン点眼薬
かゆみを抑える効果に優れています。即効性があるため、かゆみが強い時に効果的です。
| 商品名 | 特徴 |
|---|---|
| アルガードクリアブロックEXa | 清涼感のある使用感で、かゆみを素早く抑えます。 |
■抗アレルギー点眼薬
アレルギー反応を抑えることで、かゆみ、充血、涙目の発生を予防します。花粉飛散前に使用することで、症状の悪化を防ぐ効果が期待できます。
■血管収縮点眼薬
充血を抑える効果があります。ただし、使い続けると効果が弱まったり、逆に充血が悪化することがあるので、注意が必要です。
一時的な症状緩和に用いるのが適切です。
| 商品名 | 特徴 |
|---|---|
| スマイル40EXゴールド | 清涼感があり、疲れた目の充血にも効果的です。 |
| サンテFXネオ | 強い清涼感で、リフレッシュ効果も期待できます。 |
■人工涙液
涙の成分を補うことで、目の乾燥やかゆみを和らげます。防腐剤無添加のものがおすすめです。他の点眼薬と併用することもできます。
| 商品名 | 特徴 |
|---|---|
| ロートCキューブ ソフトワンモイストa | 防腐剤無添加で、コンタクトレンズを装着したままでも使用可能です。 |
| スマイルコンタクト ファインフィットプラス | コンタクトレンズ装着時の異物感にも効果があります。 |
■点眼薬の選び方
点眼薬を選ぶ際には、ご自身の症状に合わせて適切な種類を選ぶことが大切です。
かゆみが強い場合は抗ヒスタミン点眼薬、アレルギー反応を抑えたい場合は抗アレルギー点眼薬、充血が気になる場合は血管収縮点眼薬、乾燥やかゆみが気になる場合は人工涙液がおすすめです。
また、コンタクトレンズを使用している場合は、コンタクトレンズに対応した点眼薬を選ぶようにしましょう。
複数の症状がある場合は、異なる種類の点眼薬を併用することも可能です。
ただし、点眼薬の種類によっては併用できない場合もあるので、医師や薬剤師に相談することが重要です。
また、点眼薬を使用する際には、使用期限を守り、正しい使用方法に従うようにしましょう。
6. 花粉症対策におすすめの市販の点鼻薬

花粉症の鼻づまりに効果的な市販の点鼻薬は、大きく分けて血管収縮剤とステロイド剤の2種類があります。
それぞれの特徴を理解して、自分に合った点鼻薬を選びましょう。
■血管収縮剤
血管収縮剤は、鼻の粘膜の血管を収縮させることで、鼻づまりを迅速に改善します。
即効性があるのが特徴ですが、使い続けると効果が弱まったり、逆に鼻づまりが悪化したりする可能性があるので、使用は短期間(3~5日程度)にとどめましょう。
また、妊婦や授乳中の方、高血圧や心臓病の方は使用前に医師や薬剤師に相談してください。
7.1.1 代表的な血管収縮剤
| 商品名 | 成分 | 特徴 |
|---|---|---|
| ナザール「スプレーポンプ」 | ナファゾリン塩酸塩 | 鼻づまりに効果が高い。 |
| パブロン点鼻 | 塩酸テトラヒドロゾリン | 持続時間が長い。 |
| エージーノーズアレルカットS | オキシメタゾリン塩酸塩 | 1日2回の使用で効果が持続する。 |
■ステロイド剤
ステロイド剤は、鼻の炎症を抑えることで、鼻づまり、鼻水、くしゃみなどの症状を改善します。
血管収縮剤のような即効性はありませんが、根本的な治療につながります。
効果が現れるまでに数日かかる場合もありますが、継続して使用することで効果が高まります。
副作用が少ないため、比較的長期にわたって使用できます。
代表的なステロイド剤
| 商品名 | 成分 | 特徴 |
|---|---|---|
| フルナーゼ点鼻薬 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 1日1回で効果が持続する。 |
■点鼻薬の効果的な使い方
点鼻薬を使用する際は、正しい使用方法を守ることが重要です。
使用前に鼻をかんで鼻腔内をきれいにし、容器をよく振ってから使用します。
頭を軽く後ろに傾け、ノズルを鼻腔に挿入し、薬液を噴霧します。
噴霧後は軽く鼻をつまんで、薬液を鼻腔全体に行き渡らせます。
血管収縮剤は指定された回数以上使用しないように注意し、ステロイド剤は医師の指示に従って使用しましょう。
また、点鼻薬の種類によっては、使用後に鼻が乾燥することがあります。その場合は、保湿剤を使用するなどして、鼻の乾燥を防ぎましょう。
点鼻薬を使用しても症状が改善しない場合は、医師に相談するようにしてください。自己判断で他の薬と併用するのは危険です。
市販薬で効果がない場合や、症状が重い場合は、耳鼻咽喉科を受診し、適切な治療を受けるようにしましょう。
7. 花粉症対策におすすめの市販の保湿クリーム

花粉症による肌のかゆみ、炎症、乾燥は、肌のバリア機能が低下することで悪化しやすくなります。
保湿クリームで肌のバリア機能を維持・回復することは、花粉症による肌トラブルの予防・改善に効果的です。
肌に優しい低刺激性の保湿クリームを選び、適切に使用することで、つらい症状を和らげることができます。
■保湿クリームを選ぶポイント
花粉症対策として保湿クリームを選ぶ際には、以下のポイントに注目しましょう。
- 低刺激性:無香料、無着色、アルコールフリーなど、肌への刺激が少ないものを選びましょう。敏感肌の方にもおすすめです。
- 保湿力:セラミド、ヒアルロン酸、コラーゲンなど、保湿成分が配合されているものが効果的です。
- 伸びの良さ:肌に負担をかけずに塗り広げられる、伸びの良いテクスチャーのものが使いやすいです。
- ベタつきの少なさ:ベタつきが少ないクリームは、メイク前に使用しても問題ありません。
■おすすめの市販保湿クリーム
| 商品名 | 特徴 | 価格帯 | 対象 |
|---|---|---|---|
| キュレル 潤浸保湿フェイスクリーム | セラミド機能成分配合で、乾燥性敏感肌の方にもおすすめ。 | 2,000円~3,000円 | 乾燥性敏感肌 |
| アトリックス ビューティーチャージ ナイトスペリア | 夜用の高保湿クリーム。うるおいを長時間持続。 | 1,000円~2,000円 | 乾燥肌 |
| ニベアクリーム | 高保湿で、顔にも体にも使える万能クリーム。 | 500円~1,000円 | 乾燥肌 |
| ユースキンA | ビタミン系クリームで、肌荒れを防ぎ、健康な肌へ導く。 | 1,000円~2,000円 | 乾燥肌、肌荒れ |
| ヴァセリン オリジナルピュアスキンジェリー | 高純度のワセリンで、肌を外部刺激から保護。 | 500円~1,000円 | 超乾燥肌、敏感肌 |
■保湿クリームの効果的な使い方
保湿クリームの効果を最大限に引き出すためには、正しい使い方を心がけることが重要です。
- 洗顔後、化粧水などで肌を整えた後に使用します。
- 適量を手に取り、顔全体に優しくなじませます。特に乾燥しやすい目元や口元は重ね塗りすることで、集中的に保湿できます。
- 朝晩2回の使用がおすすめです。乾燥が気になる場合は、日中もこまめに塗り直しましょう。
- 花粉の付着を防ぐため、外出前にも塗布すると効果的です。
- ボディにも使用することで、全身の乾燥を防ぎ、花粉の付着によるかゆみを軽減できます。
適切な保湿クリームを選び、正しく使用することで、花粉症による肌トラブルを予防・改善し、快適に過ごしましょう。
症状が重い場合は、皮膚科医に相談することをおすすめします。
8. 花粉症対策におすすめの市販のマスク
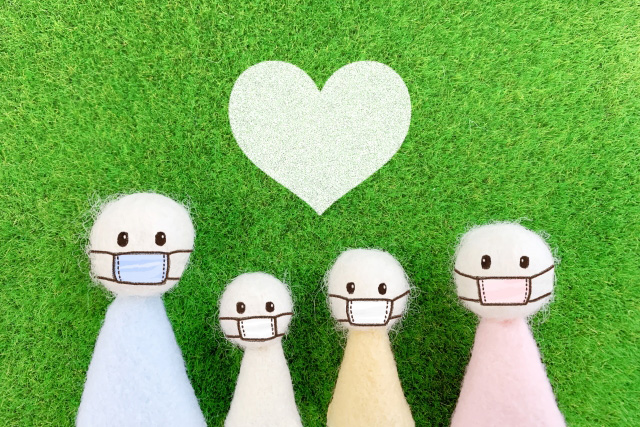
花粉症の症状を軽減するには、花粉を吸い込まないことが重要です。そのため、マスクの着用は基本的な対策となります。
市販されているマスクの種類は豊富で、それぞれ特徴があります。自分に合ったマスクを選ぶことで、より効果的に花粉をブロックし、快適に過ごすことができます。
■マスクの種類と特徴
| 種類 | 特徴 | メリット | デメリット | おすすめポイント |
|---|---|---|---|---|
| 不織布マスク | 使い捨てで衛生的。様々な形状やサイズがあり、価格も比較的安価。 | 手軽に入手でき、衛生的に使える。通気性が良いものも多い。 | 密着性が低いと花粉が侵入する可能性がある。 | 日常使いに最適。プリーツタイプは顔にフィットしやすい。 |
| ウレタンマスク | 洗って繰り返し使える。柔らかい素材でつけ心地が良い。 | 経済的。肌触りが良い。 | 花粉捕集率が低いものもある。洗濯が必要。 | 短時間の外出や、肌が弱い人におすすめ。 |
| 布マスク | 洗って繰り返し使える。デザインが豊富。 | 経済的。ファッションの一部として楽しめる。 | 花粉捕集率が低いものもある。洗濯が必要。 | おしゃれを楽しみたい人におすすめ。花粉対策としては補助的に使用するのが良い。 |
| 高機能マスク | 花粉やウイルス飛沫などを高性能フィルターでブロック。立体構造で顔にフィットしやすい。 | 花粉捕集率が高い。呼吸がしやすい。メガネが曇りにくい。 | 価格が高い。 | 花粉症が重症の人や、より高い防御効果を求める人におすすめ。代表的な商品として、PITTA MASKや三次元マスクなどがある。 |
■マスクの選び方
マスクを選ぶ際には、以下のポイントに注目しましょう。
花粉捕集率
PFE、BFE、VFEといった表記で示されるフィルター性能を確認しましょう。
数値が高いほど、花粉やウイルス飛沫などをブロックする効果が高いです。99%カット以上のものを選ぶのがおすすめです。
顔へのフィット感
隙間があると花粉が侵入しやすいため、自分の顔のサイズに合ったマスクを選ぶことが重要です。
ノーズフィッター付きのものは、鼻周りの隙間を減らすのに効果的です。
通気性
マスクをしていると息苦しさを感じることがあります。通気性の良いマスクを選ぶことで、快適に過ごせます。
■マスクの効果的な使い方
マスクを正しく着用することで、花粉症対策の効果を高めることができます。
- 鼻と口を完全に覆うように着用する
- ノーズフィッターを鼻の形に合わせて調整する
- 隙間ができないようにする
- 汚れたら交換する(使い捨てマスクの場合)
- 定期的に洗濯する(洗えるマスクの場合)
また、マスクだけでなく、メガネや帽子、花粉ガードスプレーなどを併用することで、さらに効果を高めることができます。
9. 花粉症対策におすすめの市販の空気清浄機

空気清浄機は、花粉を含む空気中の汚れを除去し、室内環境を改善することで花粉症の症状緩和に役立ちます。
様々なメーカーから多様な機種が販売されているため、花粉への効果に加えて、適用床面積、機能、価格などを比較検討し、自身に最適な一台を選びましょう。
■空気清浄機を選ぶポイント
空気清浄機を選ぶ際には、いくつかのポイントを考慮することが重要です。以下のポイントを参考に、自分に合った製品を選びましょう。
適用床面積
空気清浄機の性能は、適用床面積で示されます。部屋の広さに合った適用床面積の空気清浄機を選ぶことで、効果的に花粉を除去できます。
部屋よりも適用床面積が小さい空気清浄機を選んでしまうと、十分な効果が得られない可能性があります。
フィルター性能
HEPAフィルターは、0.3μmの微粒子を99.97%以上除去できる高性能フィルターです。
花粉だけでなく、PM2.5やハウスダストなどの微粒子も除去できるため、花粉症対策にはHEPAフィルター搭載の空気清浄機がおすすめです。
活性炭フィルターは、タバコの煙やペットの臭いなどの脱臭に効果的です。その他にも、集じんフィルターや脱臭フィルターなど、様々な種類のフィルターがあります。それぞれのフィルターの特徴を理解し、除去したい物質に合ったフィルターを搭載した空気清浄機を選ぶことが大切です。
機能
空気清浄機には、様々な付加機能が搭載されています。例えば、加湿機能付きの空気清浄機は、乾燥対策にも効果的です。
また、PM2.5センサーやニオイセンサーを搭載した空気清浄機は、空気の状態を自動で感知し、運転を調整してくれるため便利です。
その他、チャイルドロック機能やタイマー機能など、様々な機能があります。自身の生活スタイルやニーズに合った機能を搭載した空気清浄機を選ぶと、より快適に使用できます。
価格
空気清浄機の価格は、機能や性能によって大きく異なります。予算に合わせて適切な価格帯の空気清浄機を選ぶことが重要です。
高価格帯の空気清浄機は高性能なものが多く、様々な機能が搭載されていますが、低価格帯の空気清浄機でも十分な性能を持つ製品もあります。
■おすすめメーカーと製品例
| メーカー | 特徴 |
|---|---|
| ダイキン | 加湿ストリーマ空気清浄機。加湿機能とストリーマ技術による強力な脱臭・除菌機能が特徴。 |
| シャープ | プラズマクラスターNEXT搭載。静電気を抑える効果も期待できる。 |
| パナソニック | ナノイーX搭載。花粉やウイルスを抑制する効果に加え、お部屋の空気を清潔に保つ。 |
| 日立 | 自動おそうじ機能搭載。フィルターのメンテナンスの手間を軽減。 |
上記以外にも様々なメーカーから優れた空気清浄機が販売されています。それぞれの製品の特徴を比較検討し、自身に最適な一台を選びましょう。
空気清浄機は、花粉症対策に効果的なアイテムの一つです。適切な空気清浄機を選ぶことで、快適な室内環境を実現し、花粉症の症状を軽減しましょう。
ただし、空気清浄機だけで花粉症対策が完結するわけではありません。他の対策と併用することで、より効果的に花粉症対策を行うことができます。
10. 花粉症対策でやってはいけないNG行動

せっかく様々な対策を講じていても、間違った行動によって花粉症の症状が悪化したり、対策の効果が薄れてしまうことがあります。ここでは、花粉症対策でやってはいけないNG行動を紹介します。
■花粉を家の中に持ち込む行動
花粉の飛散が多い時期は、家の中に花粉を持ち込まない工夫が重要です。
窓を開けっぱなしにする
花粉の飛散量が多い日は、窓を開けっぱなしにすると大量の花粉が家の中に侵入してしまいます。
換気は必要ですが、短時間で行い、すぐに窓を閉めるようにしましょう。
洗濯物を外に干す
洗濯物に花粉が付着し、それを室内に取り込むことで花粉症の症状が悪化することがあります。花粉の飛散量が多い日は、部屋干しや乾燥機を利用しましょう。
どうしても外干ししたい場合は、花粉ガードスプレーを使用したり、取り込む前にしっかりはたくなどの対策が必要です。
玄関で花粉を落とさない
玄関から家の中に入る際に、衣服や髪の毛に付着した花粉を落とさないまま入ると、室内に花粉が拡散してしまいます。
玄関に粘着テープ式のクリーナーを置いて衣服に付着した花粉を除去したり、コートや帽子は玄関に置いておくなどの工夫をしましょう。
■生活習慣におけるNG行動
日常生活における何気ない行動が、花粉症の症状を悪化させる可能性があります。
睡眠不足
睡眠不足は免疫力を低下させ、花粉症の症状を悪化させる原因となります。規則正しい生活を心がけ、十分な睡眠時間を確保しましょう。
栄養バランスの偏り
栄養バランスの偏った食事は、免疫機能の低下につながります。バランスの良い食事を摂り、免疫力を高めるように心がけましょう。特に、ビタミンC、ビタミンD、EPAなどの栄養素は花粉症対策に効果的と言われています。
アルコールの過剰摂取
アルコールは血管を拡張させ、鼻粘膜の腫れを悪化させる可能性があります。花粉症の症状がひどい時期は、アルコールの摂取を控えるか、適量に留めるようにしましょう。
過度なストレス
ストレスは免疫機能を低下させ、アレルギー反応を悪化させる可能性があります。ストレスを溜め込まないように、適度にリラックスする時間を設けましょう。
■間違った花粉症対策
良かれと思って行っている対策が、実は逆効果になっている場合もあります。
点鼻薬の過剰使用
点鼻薬は鼻づまりを解消するのに効果的ですが、使いすぎると逆に鼻づまりが悪化することがあります。
使用上の注意をよく読み、用法・用量を守って使用しましょう。
また、市販の点鼻薬の中には血管収縮剤が含まれているものがあり、長期連用すると薬剤性鼻炎を引き起こす可能性があります。
医師に相談しながら使用するようにしましょう。
目のかゆみに対してこする
目のかゆみが強い時に目をこすってしまうと、症状が悪化したり、結膜炎などを引き起こす可能性があります。
目のかゆみを感じた時は、冷たいタオルで目を冷やす、あるいは人工涙液タイプの点眼薬を使用するなどして対処しましょう。
| NG行動 | 正しい行動 |
|---|---|
| 窓を開けっぱなしにする | 換気は短時間で行い、すぐに窓を閉める |
| 洗濯物を外に干す | 部屋干しや乾燥機を利用する |
| 玄関で花粉を落とさない | 粘着テープ式のクリーナーで花粉を除去する |
| 睡眠不足 | 十分な睡眠時間を確保する |
| 栄養バランスの偏り | バランスの良い食事を摂る |
| アルコールの過剰摂取 | アルコールの摂取を控える |
| 過度なストレス | 適度にリラックスする |
| 点鼻薬の過剰使用 | 用法・用量を守って使用する |
| 目のかゆみに対してこする | 冷たいタオルで目を冷やす、点眼薬を使用する |
これらのNG行動を避けることで、花粉症の症状を少しでも軽減し、快適に過ごすことができるでしょう。
自分に合った対策を見つけ、実践していくことが重要です。
11. よくある質問

花粉症に関するよくある質問と回答をまとめました。
Q. 花粉症の症状はいつ頃まで続きますか?
花粉の種類によって飛散時期が異なり、症状が出る期間も違います。
スギ花粉の場合は2月から4月頃、ヒノキ花粉の場合は3月から5月頃、ブタクサ花粉の場合は8月から10月頃が主な飛散時期です。
症状の持続期間は個人差がありますが、飛散時期が終わっても症状が続く場合もあります。
Q. 市販薬で効果がない場合はどうすれば良いですか?
市販薬で効果がない場合は、耳鼻咽喉科やアレルギー科などの医療機関を受診しましょう。
医師の診察を受けて、自分に合った薬を処方してもらうことが大切です。
自己判断で市販薬を併用したり、使用量を増やしたりすることは危険です。
Q. 花粉症の検査はどのように行いますか?
花粉症の検査には、主に血液検査と皮膚テストがあります。
血液検査では、特定の花粉に対するIgE抗体の量を測定します。
皮膚テストでは、少量の花粉エキスを皮膚に塗布または注射し、アレルギー反応の有無を確認します。
どちらの検査も医療機関で受けることができます。
Q. 花粉症対策に効果的な食べ物や飲み物はありますか?
ヨーグルトなどの乳酸菌を含む食品や、ポリフェノールを含む緑茶、甜茶などが花粉症対策に良いと言われています。
ただし、これらの食品だけで花粉症の症状が劇的に改善するわけではありません。バランスの良い食事を心がけ、免疫力を高めることが大切です。
Q. マスクはどのタイプが効果的ですか?
花粉症対策には、花粉を99%以上カットできる高性能なマスクがおすすめです。不織布マスクやN95マスクなどが効果的です。
マスクのサイズが合っていないと効果が下がってしまうため、自分の顔に合ったサイズを選びましょう。また、正しく着用することも重要です。
Q. 空気清浄機は効果がありますか?
空気清浄機は、室内の花粉やハウスダストなどを除去するのに効果的です。
HEPAフィルターを搭載した空気清浄機を選ぶと、より効果的に花粉を除去できます。
空気清浄機を使用する際は、定期的にフィルターを交換することが重要です。
Q. 子供の花粉症対策はどうすれば良いですか?
子供の花粉症対策も、大人と同様に、症状に合わせて市販薬を使用したり、医療機関を受診したりする方法があります。
子供に市販薬を使用する場合は、年齢や症状に合った薬を選ぶことが重要です。医師に相談するのが安心です。
Q. 妊娠中や授乳中に花粉症の薬は飲めますか?
妊娠中や授乳中に花粉症の薬を服用する場合は、必ず医師や薬剤師に相談しましょう。
妊娠中や授乳中は使用できない薬もあるため、自己判断で服用することは危険です。
Q. 花粉症と風邪の違いは?
| 項目 | 花粉症 | 風邪 |
|---|---|---|
| 原因 | 花粉 | ウイルス |
| 症状 | くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみなど | くしゃみ、鼻水、鼻づまり、咳、発熱など |
| 期間 | 花粉の飛散時期が続く | 数日から1週間程度 |
| 熱 | 通常出ない | 出る場合が多い |
上記以外にも、鼻水の粘り気や目の症状の有無などでも区別できます。自己判断が難しい場合は、医療機関を受診しましょう。
Q. 日常生活でできる花粉症対策はありますか?
花粉を家の中に持ち込まない、外出時の服装に気を付ける、帰宅後はすぐに着替える、洗顔やうがいをするなど、日常生活でできる花粉症対策はいくつかあります。
こまめな対策を心がけることで、症状を軽減できる可能性があります。
Q. レーザー治療は効果がありますか?
花粉症のレーザー治療は、鼻粘膜の状態を改善することで症状を軽減する治療法です。効果には個人差がありますが、
手術に比べて体への負担が少ないというメリットがあります。医療機関で相談してみましょう。
Q. 舌下免疫療法とはどのような治療法ですか?
舌下免疫療法は、少量のアレルゲンを舌の下に投与することで、体をアレルゲンに慣れさせていく治療法です。
根本的な治療法として期待されていますが、効果が出るまでに時間がかかるという点に注意が必要です。医療機関で相談してみましょう。
12. まとめ
この記事では、2025年最新の花粉症対策として、症状別に効果的な市販品と、その効果的な使い方を紹介しました。
鼻づまりには点鼻薬、鼻水やくしゃみには抗ヒスタミン薬、目の症状には点眼薬など、症状に合わせた適切な市販薬を選ぶことが重要です。
内服薬は用法・用量を守り、点眼薬や点鼻薬は正しい使用方法を理解して使用しましょう。
また、保湿クリームやマスク、空気清浄機などのグッズも併用することで、より効果的な対策ができます。
花粉症対策で重要なのは、自分に合った対策方法を見つけることです。この記事を参考に、つらい花粉症の症状を軽減し、快適な春を過ごしましょう。
商品カテゴリから探す
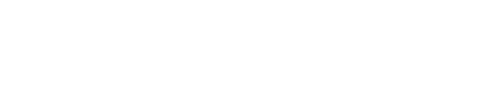










![大正製薬クラリチンEX 14錠 [第2類医薬品 鼻炎薬]](https://kenkosite.jp/storage/item_photo/MqgmYgWo457tzmonTe3ZDzisrYD9mELjfLRpvkKH.jpg)









![ニベア NIVEA ニベアクリーム 大缶 169g [スキンケアクリーム]](https://kenkosite.jp/storage/item_photo/jzNTEq7IYH6RnoPBJr8uwwDGrH5p7DOlIyyN76B8.jpg)

